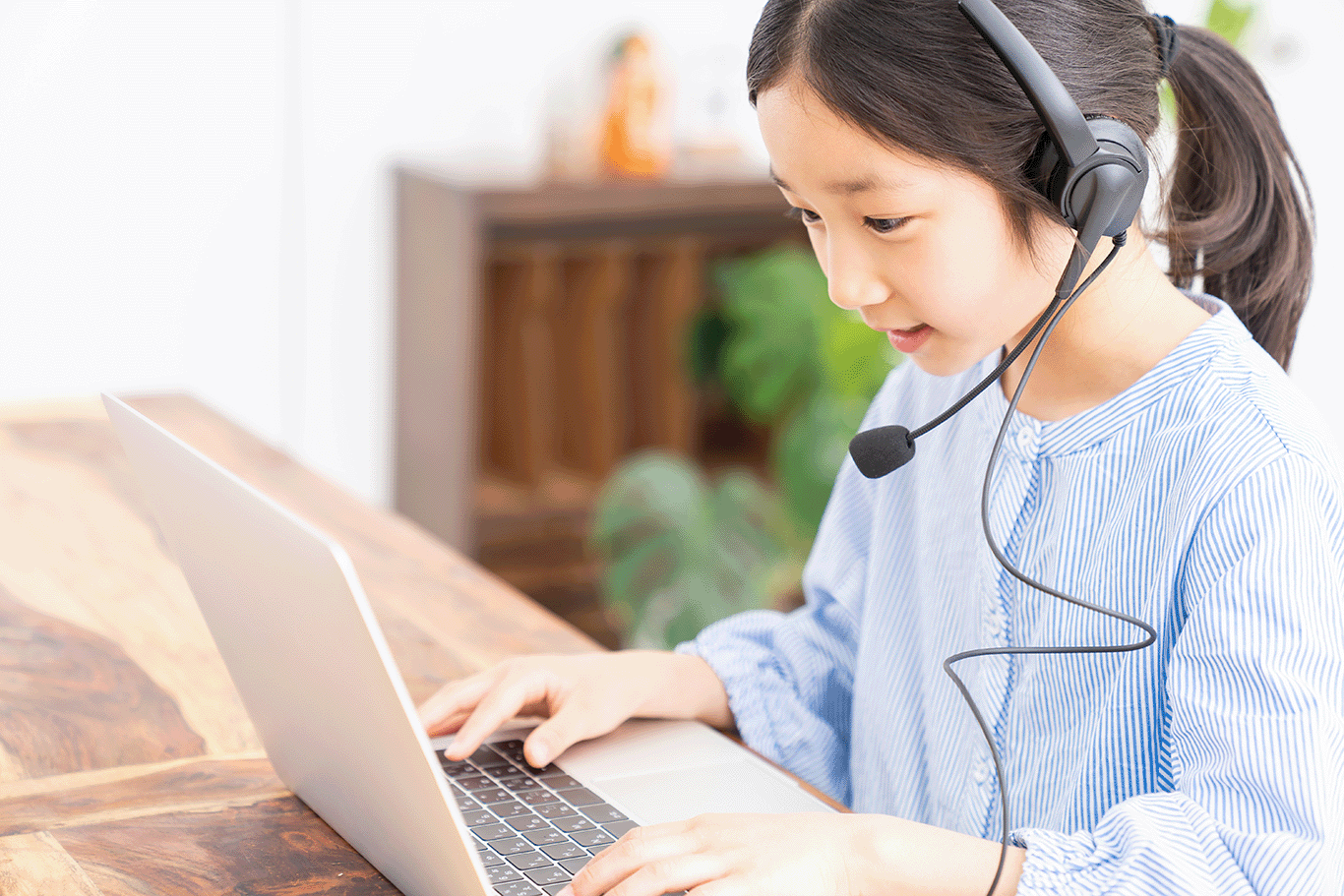「個別最適な学び」とは?GIGAスクールで実現する学び方を解説


「個別最適な学びって、結局どういうこと?」「ICTを使えば、児童や生徒一人一人に合った学習環境を用意できる?」といった疑問を抱いたこともあるのではないでしょうか。
教育現場では、授業のスピードについていけない児童生徒が出てしまう、児童生徒全員に目が行き届かないといった課題を抱える先生が少なくありません。個々の理解度や進度に合わせた学習指導は、学習の質を高められるだけでなく、子どもたちが情報化の進む社会や予測できない将来に対しても順応できるスキルを身につけやすくなるでしょう。
この記事では、「個別最適な学び」の意味をわかりやすく説明し、重要とされる理由や実現するために必要なもの、実践例などをご紹介します。現状の改善や新しいICT機器の導入など、教育現場をアップデートしたいと考えている先生方はぜひご参考にしてください。
個別最適な学びを実現するためには、児童生徒一人一人に寄り添った学習サポートや、心のケアが重要です。Microsoft社では、このような個別最適な学びを実現すべく、AIを活用した機能「Reading Progress (リーディング プログレス)」や「Microsoft Reflect (リフレクト)」などを提供しています。
SB C&Sでは、これらの機能を持った教育機関向けのWindows 11 Pro Education 搭載パソコンの導入サポートを行っています。Windows 11 Pro Educationが持つ詳しい機能などは、以下のサービスページをご確認ください。
「個別最適な学び」をわかりやすく説明すると?
教育現場では、「個別最適な学び」という言葉が注目されています。これは、従来の一斉指導型授業では対応しきれなかった、生徒一人一人の理解度や興味、学習ペースの違いに寄り添う学びのあり方を指します。
その背景には、児童生徒の多様化や情報化が進む社会における教育環境の適応、文部科学省が提唱するGIGAスクール構想の推進などがあります。
ICTを活用することで、教師一人でカバーしきれなかった指導が可能となり、全ての児童生徒が自分に最適な学びを進められる環境を整備できます。
「個別最適な学び」は、「指導の個別化」と「学習の個性化」の2つの要素から成り立ちます。以下では、「指導の個別化」と「学習の個性化」についてご紹介します。
「指導の個別化」とは
「指導の個別化」とは、教師が生徒一人一人の学習進度や理解度、課題を把握し、それぞれに合った指導を行うことを指します。
例えば、算数の授業でつまずいている生徒には基礎問題を繰り返し練習させ、得意な生徒には応用問題に挑戦させる、といった対応です。
これまでは教師の経験や勘に頼る部分が大きく、全員に均等な指導を行うことは難しいとされてきました。しかし、ICTの導入により、各児童生徒の理解状況をデータで可視化したり、AIが分析しておすすめの教材や課題を提示したりできるようになったことから、教師はこれに基づき、より適切な指導や個別フォローを行えます。
なお、文部科学省の「学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料」では、以下のように説明されています。
全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等や、自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには、教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや、子供一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の個別化」が必要である。
出典:学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料|文部科学省
「学習の個性化」とは
「学習の個性化」とは、児童生徒自らが興味や関心、目標に基づいて学びを選び、進めていくことです。つまり、教師が提供する内容をそのまま受け取るだけではなく、子どもたちが自分にとって必要だと思う教材を選んで理解が浅い部分を繰り返し学習したり、逆に興味のある分野を深掘りしたりする姿勢を指します。
ICTの力を活用することで、デジタル教材やオンライン学習プラットフォーム、個々に合わせた課題の提案など、学びの選択肢を大幅に広げられるだけでなく、メタ認知(自分の学びを振り返る力)を育む効果も期待されています。
生徒が自ら主体的に学ぶ姿勢を育てることによって、自己肯定感の向上や、子どもが将来やりたいことに向かって学習に取り組む意欲を養うことにもつながるでしょう。
なお、文部科学省の「学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料」では、以下のように説明されています。
基礎的・基本的な知識・技能等や、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力等を土台として、幼児期からの様々な場を通じての体験活動から得た子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、探究において課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子供自身が学習が最適となるよう調整する「学習の個性化」も必要である。
出典:学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料|文部科学省
「個別最適な学び」と「個別最適化された学び」の違い
「個別最適な学び」と「個別最適化された学び」は、言葉の響きは似ているものの、教育現場において、両者は区別されています。
「個別最適な学び」は学習者側に、「個別最適化された学び」は教師側に焦点を当てた言葉です。「個別最適な学び」は、児童生徒自身が自らの理解度や関心、学習スタイルに応じて進める主体的な学びを指します。
一方で、個別最適化された学びは、教師がICTなどを用いて児童生徒の理解度や進度を分析し、それぞれの子どもに適切な教材や課題を用意・提供する指導方法です。
現在は、子どもの主体性を重視した「個別最適な学び」のほうが重視されていますが、「個別最適な学び」と「個別最適化された学び」をあわせて実践することで、学習効果を最大限発揮できます。
個別最適な学びが重要な理由
ここまで、「個別最適な学び」の意味についてご紹介しました。教育現場において個別最適な学びが求められる背景には、教育環境や社会の変化があり、GIGAスクール構想による1人1台端末の整備や児童生徒の多様化、情報化が進む社会といった要素が絡み合うことで、従来型の一斉指導では十分に対応しきれない点が大きな要因です。ここでは、個別最適な学びが今なぜ重要視されているのかをご紹介します。
個別最適な学びを推進する環境が整ったため
現在は、文部科学省が推進するGIGAスクール構想のもと、全国の小中学校で1人1台の学習用端末と高速通信ネットワークが整備されています(2022年度末時点で99.9%の自治体が整備完了)。
これにより、従来の紙の教材や教室内での活動に限定された学びから、デジタル教材やクラウドベースの学習ツールを活用した、より柔軟で個別最適な学びが可能となっています。教師はデジタル端末やデータを通じて生徒一人一人の学習履歴や進度を把握しやすくなり、生徒自身も興味関心や習熟度に応じて学習内容を選択できる環境が整いました。
参照:義務教育段階における1人1台端末の整備状況|文部科学省
児童生徒が多様化しているため
現代の学校では、学習スタイル、理解度、興味関心、家庭環境、文化背景が異なる児童生徒が集まっています。
従来の一斉指導型の授業では、児童生徒一人一人の理解度や進度に対応しきれず、授業内容が簡単すぎて退屈してしまう子や、授業に追いつけず取り残されてしまう子が生じてしまいがちでした。個別最適な学びは、こうした多様な子どもたちのニーズに応える手段として重要です。
それぞれの学習ペースや理解度に応じた学習環境を提供することで、児童生徒は自信を持って学びに向き合えるようになり、教員側も無理なく一人一人に寄り添えます。
予測ができない時代に備えるため
未知のウイルスの感染拡大や国際紛争をはじめ、AI、ロボット、グローバル化の進展などにより、今ある職業が将来消滅したり、新しい職業が生まれたりすることも予測されています。
この予測困難な時代を生き抜くためには、ただ知識を暗記するだけでなく、主体的に学び続ける力や仲間と協力する力、自ら課題を発見し解決する力が求められます。個別最適な学びとして、児童生徒が自分に合った学び方を見つけるといった主体性を育む機会を学校が提供することで、これからの社会を生きるための力を養えます。
児童生徒の学習意欲が低下しているため
近年の調査では、学習に対する意欲が低下している児童生徒が少なくないことが指摘されています。
東京大学とベネッセ教育総合研究所の「子どもの生活と学びに関する親子調査 2021」によると、「勉強しようという気持ちがわかない」に対する肯定率が2019年で45.1%、2020年で50.7%、2021年で54.3%と年々向上しており、学習意欲が低下していることがわかります。
参照:「子どもの生活と学びに関する親子調査 2021」結果速報|東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所
上記の調査結果では、子どもたちが上手な勉強の仕方について理解できるようになることや、授業が楽しいと感じられるようになることが、学習意欲の向上と強く関連していることが分析されています。
個別最適な学びを導入することで、児童生徒は自分に合ったレベルの教材や学習テーマを選べるため、自分ごととして学びに取り組めるようになります。結果として学習意欲が向上し、学びの質も高まることが期待されます。
情報化が進む社会に児童生徒を適応させるため
現代の社会では、目指すべき未来社会の姿として、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」であるSociety 5.0が提唱されています。これに合わせてデジタル化・情報化が急速に進む中で、基礎的なITスキルや情報リテラシーは、現代社会で生きるうえで必須の力となっています。
しかし、内閣府の「ICT活用状況の国際比較」によると、日本の学校教育ではまだICT活用の定着が十分とはいえない場面も見られます。

個別最適な学びを実現するためにICTを日常的に活用することで、子どもたちは自然にデジタル機器の扱い方や情報の取捨選択、オンラインでの学習法などを身につけることができます。これにより、情報社会を生き抜くための力を実践的に習得できます。
個別最適な学びの実現に必要なもの
ここまで、個別最適な学びが重要とされる理由をご紹介しました。個別最適な学びを実現するためには、単にICT機器を導入し、ネットワーク環境を整えるだけでは十分ではありません。
教育現場では、教員の配置や指導体制の見直し、ICTを活用した授業設計や学習評価の工夫など、多角的な取り組みが求められます。ここでは、個別最適な学びの実現に必要なものをご紹介します。
少人数での指導体制の整備
個別最適な学びを進めるためには、教員が一人で多くの生徒を一斉に指導する従来の体制から、少人数指導や複数のグループごとに指導する体制への移行が重要です。少人数の指導体制では、教員が児童生徒の理解度や学習態度に目を向けやすくなり、個々の課題に応じた支援や声かけがしやすくなります。
また、複数の教員で役割を分担しながら指導を行うことで、授業内容の質を高めるだけでなく、生徒の多様なニーズに対応できます。
なお、文部科学省による『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現~(答申)』では、小学校高学年以降での教科担任制の導入が呼びかけられています。同省の公式サイトでは教科担任制の導入事例集も公開されているため、参考にしながら導入を進めるとよいでしょう。
参照:「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現~(答申)|文部科学省
参照:小学校高学年における教科担任制に関する事例集~小学校教育の活性化に繋げるために~(令和5年3月)|文部科学省
ICTを活用した授業や学習評価
個別最適な学びを実現するためには、これまで以上にICTを活用して授業や学習評価を行うことが重要です。
『「学習の個性化」とは』でも触れたように、パソコンやタブレット、デジタル教材やオンライン学習プラットフォームを用いることで、児童生徒は自分の理解度に応じた課題に取り組むことができ、教員は子どもたちの学習状況や理解度をリアルタイムで把握できます。
また、AIを活用してアダプティブラーニング(一人一人に最適化された学習内容を提供すること)を行うことで、児童生徒は自身のレベルに合った問題や解説を自動的に受け取れるため、「わからない部分があるまま学習を進めなければならない」といった状況を避けながら効率的に学習を進められるでしょう。
さらに、学習評価においても、ICTを活用することで小テストの自動採点や、提出物のデータ管理などが可能になり、教員のチェックやフィードバックにかかる負担軽減につながります。
学校のタブレットでできることは、以下の記事でご紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
個別最適な学びの実践例

ここまで、個別最適な学びの実現に必要なものをご紹介しました。実際に、個別最適な学びを実現するための授業改善は全国的に行われています。以下では、個別最適な学びを実現した学校の実践例をご紹介します。
英語が苦手な生徒が主体的に取り組める授業の実現
高知県の高知市立城東中学校では、英語が苦手で、話したり書いたりする活動に消極的な生徒がいることや、これまでの学習内容の理解度や定着度に生徒ごとに差がある点に課題を感じていました。
そこで、音読の練習は教科書の音声機能などをクラスで一斉に聞かせるのではなく、一人一人が聞きたい場所を聞きたいスピードで聞けるよう、個別で聞かせる活動を取り入れました。
また、リーディング時は文章を読む目的をあらかじめ明確にしたうえで、デジタル教科書を用いて生徒自身にキーワードへの線引きや文章構造の理解のための色分けを委ねることで、読む目的を理解しつつ主体的に文章を理解できるようになりました。
これらの改善により、英語が苦手な生徒も主体的に学習に取り組めるようになり、理解度や定着度の向上が見られました。
事例の詳細は、文部科学省による事例集をご確認ください。
参照:授業改善・地域内展開 実践事例集|文部科学省
これからの生活に生かせる
視野の広さを養う学習の実現
北海道の名寄市立名寄小学校では、自身の考えを表現することが苦手な児童が多いことや、周囲とのコミュニケーションが苦手で授業に積極的に参加できていない児童がいることを課題に感じていました。
そこで、ワークシートを使って課題を提示し、解決に至るまでの思考の過程を児童に自由にワークシート上に表現してもらいながら授業を進めました。また、ワークシートの提出・共有時には、児童の理解度に応じて色分けをしてもらい、児童同士で教え合うことでコミュニケーションの活性化を促進させました。
これにより、児童はデジタル教科書を使いながら自身に合った方法で考えをワークシートにまとめられるようになり、ワークシートによって可視化された理解度に基づいて、児童同士での交流が活発に行われるようになりました。
事例の詳細は、文部科学省による事例集をご確認ください。
参照:授業改善・地域内展開 実践事例集|文部科学省
まとめ
この記事では、「個別最適な学び」の意味や重要とされる背景、実現のために必要なものなどを詳しくご紹介しました。
個別最適な学びは、児童生徒自らが自分に合った学習方法を選択し、学習を進められるよう学校側で生徒一人一人の理解度や興味、学習ペースなどに合わせて学習環境を提供することが重要で、実現には教員側の指導体制の整備や、ICTのさらなる活用が不可欠です。
特に、GIGAスクール構想の推進によって一人一台端末の環境が整った今、教育現場ではデジタル技術を有効に活用し、多様化した児童生徒に対応することが求められています。記事内でご紹介した事例などを参考に、子どもたちが主体的に学び、将来の社会で活躍できる力を育める教育環境を整備しましょう。
「そろそろ端末をリプレイスしなければならないが、どうしたらよいかわからない」「不要な端末をどうすればよいかわからない」といった方は、SB C&Sへご相談ください。
SB C&Sでは、各学校でスムーズに端末を導入し、学習に適したICT教育環境を実現するために、導入した端末の管理側・や端末側の初期設定といった導入支援をはじめ、端末の下取りなども行っています。ご相談は無料ですので、ぜひ以下からサービス内容をご確認のうえ、お気軽にお問い合わせください。