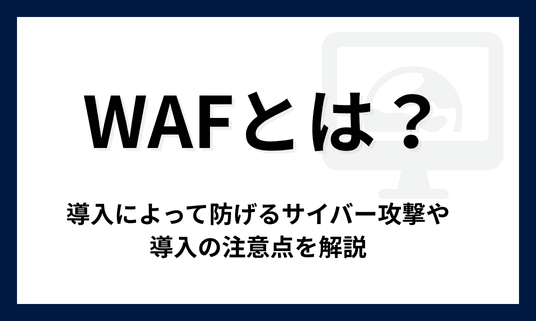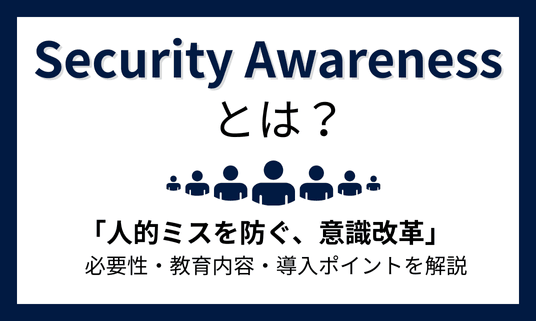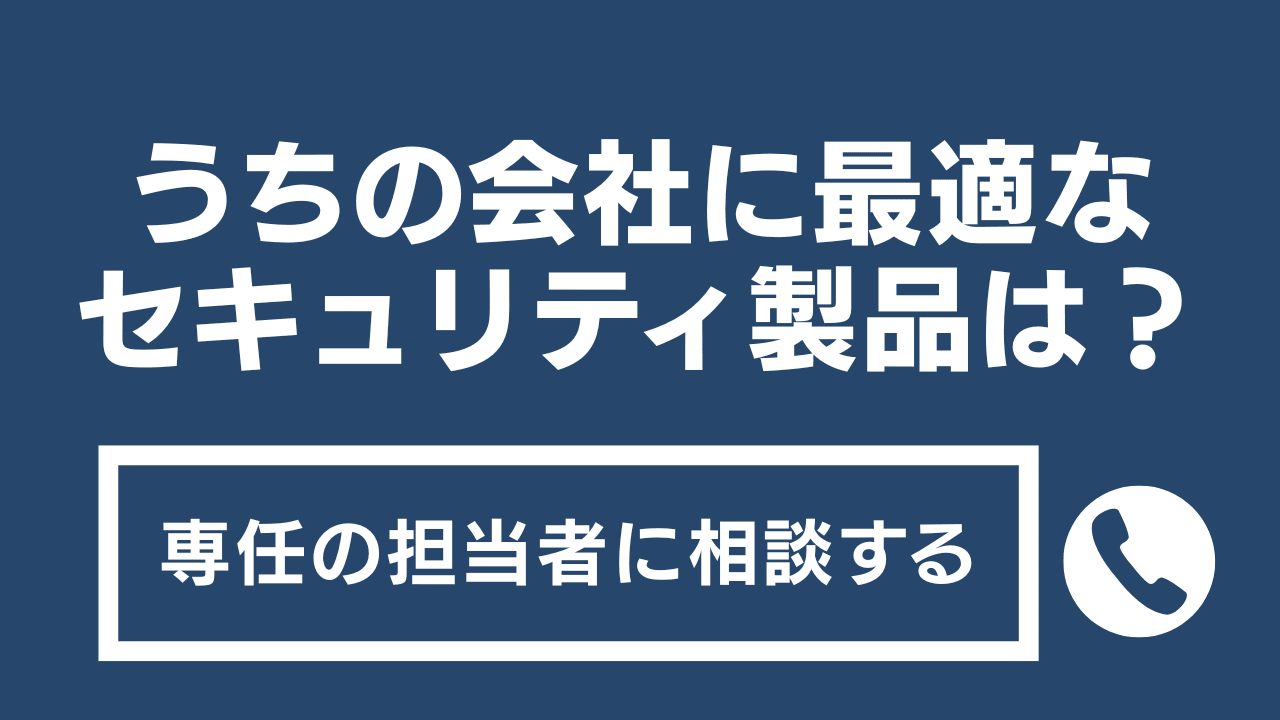2025.9.3
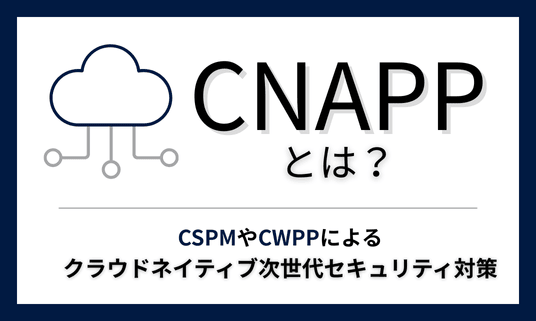
CNAPP(シーナップ)とは、Cloud Native Application Protection Platformの略で、クラウドネイティブアプリケーションを保護するための統合型セキュリティプラットフォームを指します。
クラウドネイティブ環境の普及により、従来のセキュリティ対策では対応困難な新たな課題が生まれており、これを解決するのがCNAPPです。本記事では、CNAPPの基本概念から導入メリット、選定ポイントをわかりやすく解説します。
CNAPPの基礎知識
まずはCNAPPの基本的な仕組みと、企業に求められるようになった背景を解説します。
CNAPP(Cloud Native Application Protection Platform)とは?
CNAPPとはクラウドネイティブ環境に特化して設計された、統合型のセキュリティプラットフォームです。従来のセキュリティツールがそれぞれ単一機能に特化していたのに対し、CNAPPは複数の機能を一つにまとめ、開発からデプロイ、運用までを包括的に保護するのが特徴といえるでしょう。
かつてのオンプレミス環境では、ネットワークの境界に防御を施す「境界型」のセキュリティモデルが一般的でした。しかしクラウドネイティブな環境ではシステム構成が動的に変化しているため、柔軟で包括的な保護が不可欠となっています。CNAPPはそのニーズに応える新しいアプローチとして注目されています。
CNAPPが求められる背景
企業のクラウド活用が加速するなかで、セキュリティの在り方にも大きな転換が求められています。クラウド環境では「責任共有モデル」が採用されており、クラウド事業者だけでなく利用企業側にも、設定ミスやアクセス管理など自らの領域に対する責任が生じます。
さらに、IaC(Infrastructure as Code)やCI/CDパイプライン、コンテナ、サーバーレス、Kubernetesなどの先進的な開発技術の普及によって、開発スピードは飛躍的に向上しました。一方で、構成ミスや権限設定の不備といった人為的な脆弱性も発生しやすくなっており、クラウド上に集約される企業データを狙ったサイバー攻撃が増加しています。
このような環境下では、従来の「発生後に対応する」対症療法的なセキュリティではリスクに追いつけません。開発・運用の各フェーズで継続的にリスクを可視化し、早期に対処する「予防型」のセキュリティアプローチが求められています。
こうした背景から、クラウドネイティブ環境におけるリスクを一元的に管理し、セキュリティをライフサイクル全体に組み込めるCNAPPが注目を集めています。
CNAPPを構成する代表的な機能
CNAPPはCSPMやCWPPなどの複数の要素で成り立っています。ここでは主要な構成要素を見ていきましょう。
CSPM
CSPM(Cloud Security Posture Management)は、クラウドサービスの設定状態を監視・管理する機能です。設定ミスによる情報漏洩やセキュリティインシデントのリスクを軽減する役割を担います。
たとえば、S3バケットの公開設定ミスや、セキュリティグループの過剰な許可ルールといった問題を自動で検出し、アラートを発信。CIS(セキュリティのベストプラクティス集)やNIST(アメリカ国立標準技術研究所)、PCI DSS(クレジットカード情報の国際的なセキュリティ基準)などのガイドラインに沿って、今のクラウド環境がどれだけ安全かを見える化します。その結果、設定ミスなどのリスクを早めに発見し継続的にセキュリティを改善できます。
CWPP
CWPP(Cloud Workload Protection Platform)は、クラウド上で稼働する仮想マシンやコンテナ、サーバーレスアプリケーションなど、さまざまな「ワークロード」を保護するための機能です。
脆弱性スキャンやリアルタイムでの脅威検出、アンチマルウェア機能、行動分析などを通じて包括的に監視・防御。特にコンテナ環境では、イメージのスキャンからランタイム保護まで対応し、未知の脅威にも機械学習を活用して備えられます。
関連記事:脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?種類から実施方法まで解説
CIEM
CIEM(Cloud Infrastructure Entitlement Management)は、クラウドインフラ上での権限管理に特化した機能です。ユーザーやサービスアカウントの権限を細かく把握・制御し、「最小権限の原則」を実現します。
具体的には、不要な権限や過剰なアクセス許可を洗い出し、リスクを最小化。また、JIT(Just-In-Time)アクセスやJEA(Just-Enough-Access)といった仕組みにより、必要なときに必要な分だけアクセス権を付与することが可能です。これにより、セキュリティと業務効率の両立が図れます。
IaC
IaC(Infrastructure as Code)は、クラウド環境の設定や構成をコードとして記述・管理する仕組みです。インフラ構築や設定作業を人手に頼らず、自動で実行できるようになります。
たとえば、仮想サーバーやネットワーク構成をコードで定義することで、毎回同じ設定を正確に再現でき、作業のばらつきや人的ミスを防止できます。環境構築のスピードが上がるだけでなく、再利用や変更も容易になるため、運用の効率化と安定化に貢献します。
つまり、従来は人が手動で行っていたインフラの準備や更新を、プログラムで自動化できる点がIaCのメリットです。
CNAPP導入のメリット
ここではCNAPPの導入メリットを紹介します。
セキュリティ対策を一元管理できる
CNAPPはCSPMやCWPP、CIEM、脆弱性管理など複数のセキュリティ機能をひとつのプラットフォームに統合します。従来のようにツールごとに個別管理していた手間を削減でき、連携ミスや見落としによるリスクも低減。ダッシュボード上でセキュリティ全体を俯瞰できるため、異常の早期発見につながります。
クラウド全体の見えないリスクを可視化できる
CNAPPはクラウドインフラからアプリケーション、ユーザーのアクセス権限まで一括で可視化します。「誰がどのリソースにアクセスできるか」「どこに設定ミスがあるか」「どんな異常が発生しているか」を一目で把握可能です。技術者だけでなく、非エンジニアの管理者でもセキュリティ状況を把握しやすくなる点がメリットです。
コンプライアンス対応が容易になる
CNAPPは、CISやNIST、PCI DSSなどの業界基準に沿ったチェックや監査ログの取得を自動化。継続的なモニタリングとレポート出力により、監査準備や説明責任対応がスムーズになり、法的リスクの低減にもつながります。
インシデントへの初動と復旧が早くなる
CNAPPは異常の検知から対処までの流れを自動化できます。アラート・対応手順・ワークフローが統合されているため、手動による判断や操作を最小限に抑え、迅速な封じ込めと復旧が可能です。脅威インテリジェンスとも連携できるため、新たな攻撃手法にも柔軟に対応できます。
「シフトレフト型」のセキュリティ対策が可能になる
CNAPPは、通常後工程で行われるテストやセキュリティチェックを、より早い開発段階で実施する「シフトレフト」の考え方を実現し、開発初期段階からコードや設定ファイルのセキュリティチェックを自動化します。
CI/CDパイプラインに組み込めば、開発スピードを落とすことなく脆弱性を検出・修正でき、セキュリティとアジリティを両立できます。
CNAPP導入の注意点
CNAPPはクラウドネイティブ環境における包括的なセキュリティ対策として有効ですが、導入にあたっていくつか注意点を押さえておく必要があります。
コスト面への配慮が必要
CNAPPは多機能で強力なセキュリティを提供する一方で、導入や運用にかかるコストが大きくなる可能性があります。特に保護対象が広範かつ構成が複雑なクラウド環境では、初期設定や運用体制の整備に相応の投資が求められます。
場合によっては、管理コストが保有するクラウド資産の規模を上回るリスクもあるため、費用対効果を見極めたうえで導入判断を行うことが重要です。
CNAPPだけではカバーしきれない領域もある
CNAPPが対応するのは主にクラウド環境やインフラ層のセキュリティです。そのためアプリケーション層の脆弱性対策やエンドポイントの保護には、WAFやEDRなど、他のソリューションとの併用が必要になることがあります。
関連記事:WAFとは?導入によって防げるサイバー攻撃や導入の注意点を解説
ハイブリッド環境では効果が限定的な場合も
CNAPPはクラウドネイティブな環境を前提に設計されているため、オンプレミス中心のシステムやクラウドとオンプレミスが混在するハイブリッド環境では、十分な効果を発揮できない可能性もあります。
CNAPPを有効活用するには、セキュリティ運用体制の成熟度やスキルレベルを踏まえた段階的な導入と、継続的な改善活動が求められます。導入前は自社の適合性や実行可能な運用モデルを十分に検討することが重要です。
CNAPPの導入選定ポイント
CNAPPの導入を成功させるためには、適切な選定と実装計画が欠かせません。
現状分析して守るべき資産を見極める
まずはクラウド環境の棚卸しを行い、保護すべき資産やデータ、アクセス権限の実態を把握しましょう。セキュリティ要件を明確にしたうえで、既存ツールとの重複や連携の有無を確認し、CNAPPが効果を発揮する領域を特定することが重要です。
製品ごとのメリットとデメリットを確認する
市場には多様なCNAPP製品があるため、機能・コスト・サポート体制を比較し、自社の要件に合った製品を選びましょう。PoC(概念実証)で効果を検証しながら、段階的な導入を進めるとスムーズです。
エージェントレス型とエージェント型に惑わされない
CNAPPにはエージェントレス型とエージェント型があります。エージェントレス型は導入が容易で管理が軽い反面、監視の精度に限界があります。エージェント型は詳細な監視が可能ですが、運用負荷が増すことが懸念点です。どちらが適しているかは、運用体制やセキュリティ要件によって判断する必要があります。
まとめ
CNAPPは、クラウドネイティブ環境に特化した統合型セキュリティプラットフォームです。CSPMやCWPPなどの機能を組み合わせ、開発から運用までを幅広く保護します。
導入することで、セキュリティ対策の一元管理や可視性の向上が実現し、コンプライアンス対応やインシデント対応の迅速化にもつながるでしょう。さらに、コードやインフラの構成段階からリスクを検知できる機能を活用すれば、「シフトレフト型セキュリティ」の推進にも効果的で、開発のスピードと安全性を両立できます。
まずは、自社のクラウド環境にどのような課題があるかを明確にし、それに合った製品を選定することが重要です。一度にすべてを導入するのではなく、段階的に導入を進めることで、無理なく定着させることができるでしょう。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
須賀田 淳
最新のトレンドや事例をリサーチ。専門的なテーマも、初めての方が理解しやすいように噛み砕いて発信しています。