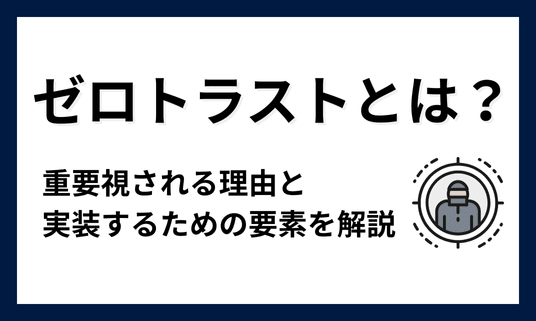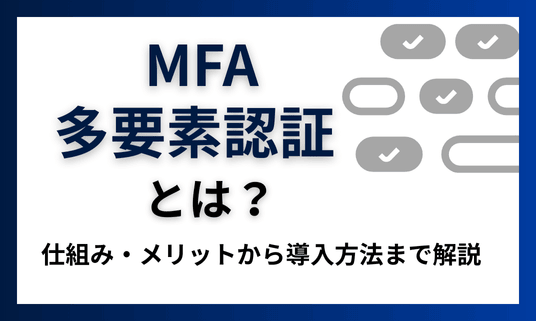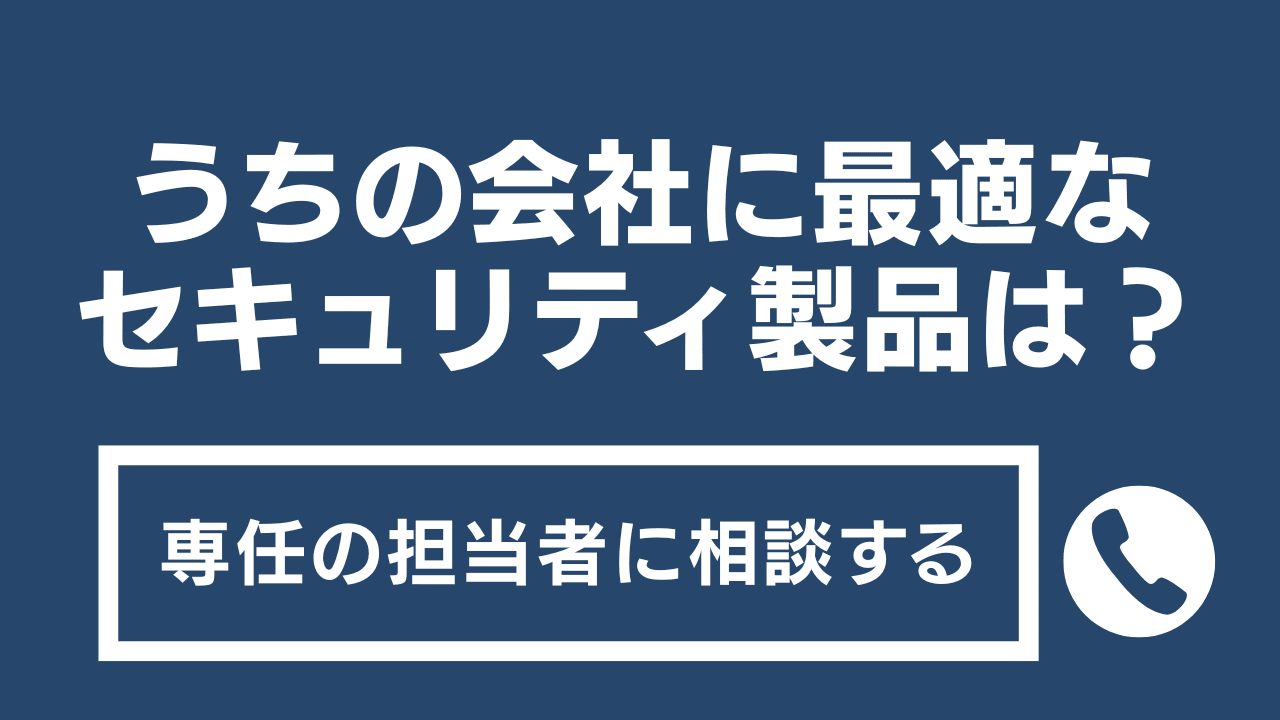2025.9.3
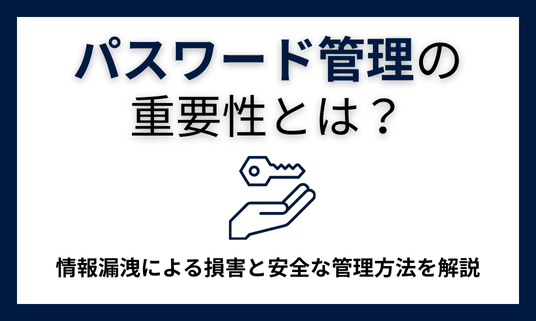
目次
サイバー攻撃が高度化する中、企業にとって「パスワード管理」は最も基本かつ重要なセキュリティ対策の一つです。実際に、情報漏洩の多くがパスワードの使い回しや簡易な設定によって引き起こされています。
本記事では、パスワード管理がなぜ企業にとって重要なのか、管理を怠ることで発生し得る損害、安全に運用するための実践的な方法について、具体例とともにわかりやすく解説します。この機会にパスワード管理の方法を見直し、セキュリティ対策を強化していきましょう。
企業でパスワード管理が重要な理由
近年、企業や組織で発生する情報漏洩事故において、「パスワード管理の怠慢」が起因しているケースが増えています。ここからは、情報漏洩とパスワード管理の関連性、パスワード管理の脆弱性を突いて行われる不正攻撃について解説します。
近年の情報漏洩事件に共通する原因
近年の情報漏洩事件に共通する原因の一つが、「パスワードの使い回し」や「単純すぎるパスワード設定」です。令和5年に検挙された不正アクセス禁止法違反の検挙件数(475件)のうち、「識別符号窃用型の不正アクセス行為」の内訳を見ると、「利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手」という手口がその42.7%を占めています。
近年の漏洩事件ではパスワード再利用と安易なパスワード設定が大きな要因となっており、強固で推測されにくいパスワードを使用することの重要性が浮き彫りになっています。
出典:令和6年 不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況|国家公安委員会・総務大臣・経済産業大臣![]()
クラッキングの手法と危険性
パスワードを狙ったクラッキング(不正な解読)手法として代表的なのが、「総当たり攻撃(ブルートフォースアタック)」と「辞書攻撃(ディクショナリーアタック)」です。総当たり攻撃とは考え得るすべての文字の組み合わせを機械的に試す手法で、制限やロックアウト機能がない場合は無数に攻撃を繰り返せるため、桁数の少ないパスワードは非常に危険です。
辞書攻撃はあらかじめ用意した単語リスト(辞書)を用いて推測する方法で、よく使われる単語やパターンが標的になります。人名や地名、辞書に載る単語などが狙われるため、推測されやすい情報をパスワードに含めることは避けなければなりません。
この他にも「パスワードリスト攻撃」という手法もあります。過去に流出したIDとパスワードのセットを使ってログインを試みる方法で、使い回されたパスワードが狙われます。別のサービスから情報が漏洩していた場合でも、同じパスワードを使い回していると簡単に突破されてしまうリスクがあります。
このように、不正攻撃の手口は年々複雑化しており、パスワード管理の甘さに起因する情報漏洩の危険性が高まっているのです。
パスワード管理の怠慢がもたらす損害
パスワード管理を怠ることによって企業が被る損害は、金銭面に留まらず多岐にわたります。ここからは、パスワード管理の甘さが引き起こす代表的な損害を金銭面・信用面・法的リスクの観点から解説します。
金銭的損害
パスワード管理の不備により、企業は直接的・間接的に大きな金銭的損害を被る可能性があります。たとえば、社員のパスワード流出がきっかけで社内システムに侵入され、保存されていた顧客のクレジットカード情報が盗まれれば、不正利用による補償費用やカード再発行対応など多額のコストが発生します。
また、侵入した攻撃者がシステムにコンピュータウイルスの一種であるランサムウェアを仕掛ければ、データの暗号化解除や情報流出を防ぐための身代金要求が行われ、対応せざるを得ない状況に陥るケースも少なくありません。実際、企業がランサムウェア攻撃で被った被害額は平均で約2.2億円にも上るとの調査結果があります。
情報漏洩に伴う損害賠償も無視できません。漏洩した個人情報の件数や内容によっては被害者から巨額の賠償請求を受け、数千万円規模の支払いが発生するケースもあります。企業にとってはこのような金銭的打撃が経営を揺るがす致命傷となりかねないため、徹底したパスワード管理でリスクを低減する取り組みが急務と言えるでしょう。
出典:ランサムウェアの被害金額は平均2.2億円~最新調査から被害傾向を読み解く~|トレンドマイクロ![]()
社会的信用の失墜
一度情報漏洩事故を起こすと、企業の社会的信用は大きく損なわれます。たとえば情報漏洩によって企業のブランドイメージを著しく損ない、顧客離れや株価下落につながったり、失った信用を取り戻せずに、長年築いてきたブランド価値が一瞬で失墜したりする可能性もゼロではありません。
実際にある企業の内部システムのパスワード管理ミスにより個人情報が流出した事件では、SNS上で批判が殺到し炎上状態となった事例もあります。一度でも「情報管理が甘い会社」という烙印を押されれば、取引停止や新規顧客獲得の困難といった負の連鎖になりかねません。
大切な顧客やビジネスパートナーからの信頼を守るためにも、日頃から万全なパスワード管理と迅速な漏洩防止策が求められるのです。
法的リスク
パスワード管理の不備による情報漏洩は、企業に法的な責任をもたらします。日本国内では、顧客の氏名や連絡先などの個人情報が漏洩した場合、「個人情報保護法」に基づき所管官庁(個人情報保護委員会)への報告と被害者への通知が義務付けられています。
対応が不十分と判断されれば、行政指導や業務改善命令といった処分が下される可能性もあり、信頼や存続にも関わる問題です。
一方、グローバルに事業を展開する企業は海外の厳しいデータ保護規則にも注意を払わねばなりません。たとえば、EUのGDPR(一般データ保護規則)では、個人データの漏洩は重大な違反とみなされ、全世界売上高の2%以下または1,000万ユーロのうち高い方の金額で制裁金が科される可能性があります。
このようにプライバシー保護の規制は国内外で強化されています。高額な罰金や訴訟リスクを避けるためにも、徹底したパスワード管理体制の構築が必要不可欠と言えるでしょう。
出典:漏えい等報告・本人への通知の義務化について|個人情報保護委員会![]()
出典:個人情報保護制度に対する関心事項|個人情報保護委員会![]()
企業がパスワードを安全に管理する方法
パスワード管理の重要性とリスクを踏まえ、企業はどのようにして安全な管理体制を構築すればいいのか、ここからは実践すべき具体的な対策を紹介します。
複雑なパスワードを作る
まず基本となるのは、一人ひとりが複雑で推測されにくいパスワードを設定することです。日本の内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)のガイドラインでは、ウェブサービスのログイン用パスワードについて「英大文字・英小文字・数字・記号を組み合わせ、ランダムに10桁以上」を安全圏として推奨しています。
たとえば、総当たり攻撃の際、8文字のパスワードを10文字に延ばすだけでも、解読に必要な試行回数は桁違いに増加します。アルファベット大文字・小文字、数字、記号など多様な文字種を混ぜることで推測をさらに困難にできるでしょう。
また、意味のある単語は避けランダムな文字列にする、もしくは複数の単語を記号や数字で繋いだ長いフレーズ型パスワード(パスフレーズ)にするのも有効です。これにより、辞書攻撃や総当たり攻撃への耐性が格段に向上します。
IDとパスワードを安全に保管する
強力なパスワードを作った後は、その保管方法にも注意が必要です。まず避けるべきは、「パスワードを書いたメモをPCモニターに貼る」「机の引き出しに鍵を掛けず保管する」といった行為です。
こうした物理的なメモは盗難や覗き見のリスクが高く、火災や紛失で消失する恐れもあります。また、パスワード一覧を暗号化せずにExcelファイルやスマホのメモ帳に保存すると、端末が紛失・盗難に遭ったりマルウェアに感染したりした場合、そこから一度にすべてのパスワードが流出してしまう可能性があります。
パスワードを安全に保管するには、パスワードを記録する場合でも鍵付きの保管場所にしまう、ファイルなら暗号化する、スマホのメモなら端末ロックを掛けるなど、第三者に容易に見られないように工夫しましょう。
また、従来ではパスワードを定期的に変更することが推奨されていましたが、現在ではパスワードは必ずしも定期的に変更する必要はないという認識に変化しつつあります。日本政府も方向転換しており、「実際にパスワードを破られアカウントが乗っ取られる等のサービス側から流出した事実がない場合は、パスワードを変更する必要はありません。」と明示しています。
引用元:安全なパスワードの設定・管理|国民のためのサイバーセキュリティサイト![]()
これは、定期的にパスワードを変更することによって、かえって覚えやすい単純なパスワードに設定してしまい、セキュリティが低下するリスクがあるためです。強固なパスワードを設定したら厳重に管理し、不正なログイン通知など、情報漏洩の恐れがあるときのみ対処するのが有効と言えます。
シングルサインオン(SSO)とMFAの導入
企業全体の認証セキュリティを高めるには、シングルサインオン(SSO)と多要素認証(MFA)の導入が効果的です。SSOとは、一度のログイン認証で社内の複数システムやクラウドサービスにアクセスできる仕組みのことで、これにより従業員は覚えるパスワードを最小限にできます。
SSOを導入すれば、サービスごとに別々のパスワードを入力する手間が省けるだけでなく、ログイン回数の低減、パスワードの使い回し回避につながります。一方、MFAは、パスワードだけに頼らず複数の認証要素を組み合わせてログインさせる仕組みです。
ワンタイムパスワードや生体認証(指紋・顔認証)などがこれに該当します。MFAを導入すれば、仮にパスワードが漏洩しても第2の要素で不正ログインをブロックできます。MFAで複数段階の認証を行い、SSOで各システムへシームレスにログインできるようにすれば、セキュリティと利便性の両立が可能です。
関連記事:多要素認証(MFA)とは?仕組み・メリットから導入方法まで解説
ID管理(IAM)を徹底する
安全なパスワード管理には、IDおよびアカウント自体の適切な管理(IAM:Identity and Access Management)も欠かせません。これは「誰が何にどの範囲までアクセスできるか」を厳格に管理・見直しする仕組みです。
具体的には、社員ごとに必要最小限のアクセス権限を与えるアクセス制御の原則(最小権限の原則)を適用し、部署変更や役職変更時には権限を即座に見直す運用を徹底します。また、退職者のアカウントを放置しないことも重要です。
過去には退職した元社員のIDが削除されずに残っていたことで悪用され、不正アクセスの踏み台となったケースも報告されています。こうしたリスクを防ぐには、人事部門と連携し、入社・異動・退職のタイミングでアカウントの発行から削除までを自動化・迅速化することが理想です。
最近ではIAMツールを導入し、入退社に伴うアカウントの自動作成・削除を実現する企業も増えています。管理者の作業負担を軽減しつつ、退職者による不正アクセス防止にもつなげることができます。
パスワード管理ができるセキュリティツールを導入する
複数のシステムやサービスのパスワードを安全に扱うために、パスワード管理ツール(パスワードマネージャー)の導入も検討すべきです。パスワードマネージャーとは、マスターパスワード一つで社内の多数のID・パスワードを暗号化して一括管理できるツールです。
このツールを導入すれば、サービスごとに長く複雑なパスワードを設定しても、利用者自身は覚える必要がなくなり、パスワードの使い回しや安易なパスワード設定といったヒューマンエラーを防止できます。信頼性の高いパスワード管理ツールでは、保存されたパスワードは強力な暗号技術で保護され、提供元ですら中身を閲覧できない「ゼロ知識」設計になっているため、漏洩リスクを最小化できます。
さらに、ほとんどの管理ツールは多要素認証(MFA)に対応しており、マスターパスワードに加えて生体認証やワンタイムパスワード等を要求できるため、ツール自体のセキュリティも万全です。企業向けの製品には、管理者が従業員のアカウントを一元的にコントロールできる機能や、利用ログの監査、共有フォルダ(複数のユーザーで安全に共有できるストレージ領域)なども備わっています。
まとめ
パスワード管理の甘さは、不正アクセスによる情報漏洩や経済的損失、信用失墜、法的処分など、企業経営に深刻な影響を及ぼします。しかし、日頃からパスワード運用を徹底し、必要なセキュリティ対策を講じておけば、かなりの割合で未然に防ぐことが可能です。
本記事で紹介した複雑なパスワードの設定、安全な保管方法の徹底、SSO・MFAの導入、IAMによるアカウント管理、管理ツールの活用といった施策を組み合わせ、自社の実情に合ったパスワード管理ポリシーを構築してください。安全なパスワード運用を習慣づけ、安心してビジネスに取り組める環境を整えていきましょう。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
須賀田 淳
最新のトレンドや事例をリサーチ。専門的なテーマも、初めての方が理解しやすいように噛み砕いて発信しています。