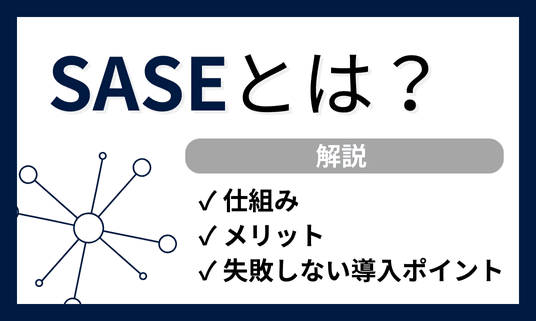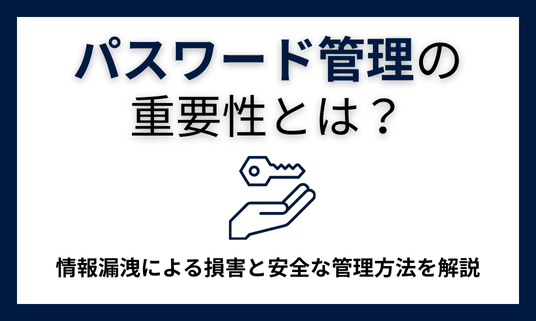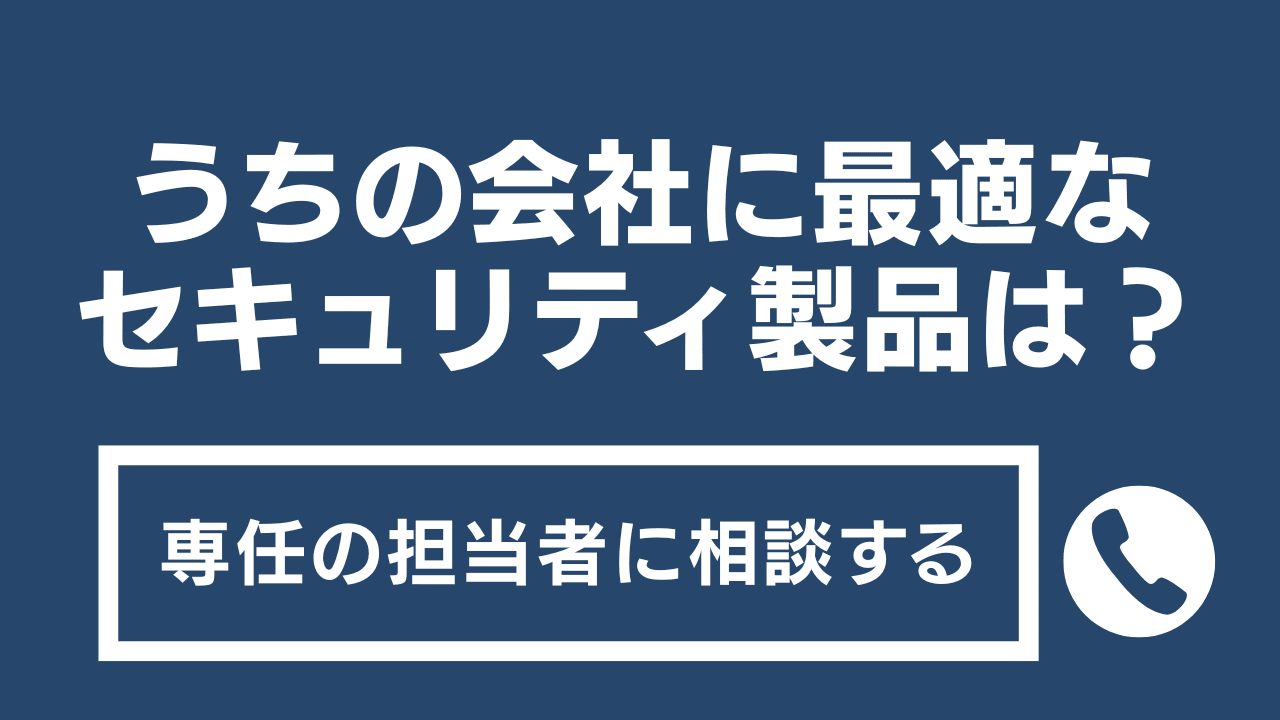2025.9.3
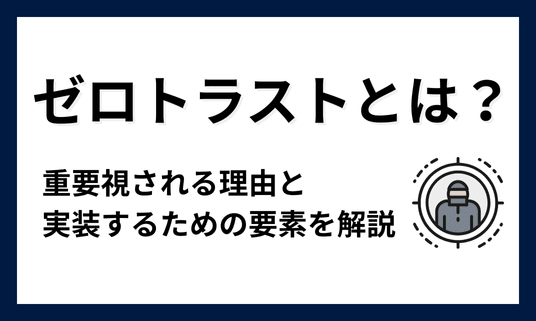
目次
近年、サイバー攻撃の巧妙化やクラウド利用、リモートワークの普及により、従来の境界型セキュリティでは十分に情報資産を守れなくなっています。こうした背景から注目されているのが「ゼロトラスト(Zero Trust)」という考え方です。
本記事では、ゼロトラストモデルの基本や重要視される理由、導入に必要な要素をわかりやすく解説します。ぜひ参考にして、社内サーバ外のセキュリティも強化していきましょう。
ゼロトラスト(ゼロトラストモデル)とは?わかりやすく解説
ゼロトラスト(ゼロトラストモデル)とは、「内部ユーザーやシステムであっても無条件に信頼せず、アクセス時に毎回検証する」ことを前提としたセキュリティモデルです。「ゼロトラストセキュリティ」とも呼ばれています。完全に誰も信じないわけではなく、ユーザーや端末の安全性を都度確認し、必要最小限の権限を与えることでリスクを抑えます。
従来は内部と外部のネットワークを分けて、外部からの攻撃を防ぐことを重視した「境界型防御モデル」が一般的でしたが、クラウドの普及により、機密情報が社外のサービス上に存在するケースも増え、内部・外部を問わず一貫したセキュリティ対策が必要となりました。
そこで注目されているのが、内部・外部のすべてのアクセスに対して常に確認と制御を行う「ゼロトラスト(ゼロトラストモデル)」なのです。
関連記事:サイバーセキュリティとは?サイバー攻撃の種類や代表的な対策方法を解説
「ゼロトラスト」が重要視される理由
ゼロトラストが重要視されているのは、IT環境の変化とセキュリティ脅威の増大による従来モデルの限界が背景にあります。
従来の境界型防御モデルではセキュリティの限界がある
従来はファイアウォールやVPNで社内ネットワークと外部を分離する「境界型防御」が基本でした。しかし、リモートワークやテレワークの普及、従業員の私用端末利用(BYOD)の増加、SaaSをはじめとするクラウドサービスの活用拡大により、社外から社内システムへアクセスする機会が日常化しています。
その結果、社内と社外の明確な境界が崩れ、旧来の境界防御だけでは保護しきれない情報資産が増えているのです。
不正アクセスなどによる情報漏洩被害の増加
近年はサイバー攻撃による情報漏えい事件が相次ぎ、攻撃手法も高度化しています。特に内部関係者による不正行為やミスによる情報漏洩、取引先や関連会社などサプライチェーンの弱点を悪用した攻撃が大きな脅威となっています。
IPAの「情報セキュリティ10大脅威 2024![]() 」では「内部不正による情報漏えい」が組織に対する脅威の第3位にランクインしました。また「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」も上位に挙げられ、年々被害が深刻化しています。
」では「内部不正による情報漏えい」が組織に対する脅威の第3位にランクインしました。また「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」も上位に挙げられ、年々被害が深刻化しています。
こうした背景から、ゼロトラストによる包括的な内部対策の必要性が高まっているのです。
法令・コンプライアンス対応の観点からも必須
昨今は法令や規制の面でも、より厳格な情報保護が求められています。たとえば日本の個人情報保護法の強化やマイナンバー制度の運用、EUのGDPRなどにより、機密データへのアクセス制御や操作ログの管理が企業に義務付けられています。
ゼロトラストを導入すれば「誰がいつどこにアクセスしたか」を詳細に記録・監視でき、不正アクセスの抑止だけでなく、コンプライアンスや監査対応においても有効です。
ゼロトラストを導入するメリット
ゼロトラストを実践することで、企業はセキュリティ面で多くのメリットを得られます。ここでは代表的なメリットを3つ紹介します。
情報漏洩・不正アクセスのリスクを大幅に軽減できる
ゼロトラストでは「常に検証」と「最小権限付与」を徹底するため、たとえ攻撃者が侵入しても被害の拡大を最小限に抑えることができます。ユーザーや端末を毎回認証・認可し、必要最低限の権限しか与えないことで、なりすましによる不正アクセスや内部犯行、侵入後の横展開による被害を大きく減らせます。
さらに、リアルタイムでアクセス状況を監視することで、通常とは異なる挙動を即座に検知し、即時に遮断することも可能です。
コンプライアンスや監査対応がしやすくなる
ゼロトラスト環境ではアクセスのたびに認証とアクセス制御が行われ、すべての操作ログが詳細に記録されます。誰がいつどの情報にアクセスしたかが可視化されるため、不正の抑止だけでなく後からの追跡も容易です。
これにより内部統制の強化や監査対応がスムーズになり、セキュリティ対策とコンプライアンス対応を両立できる点もゼロトラスト導入の大きな利点です。また、個人情報保護法やGDPRなどの法令対応にも有効であり、外部からの評価にも対応しやすくなります。
運用の自動化によってセキュリティ人材不足を補える
ゼロトラストの考え方では、AIによる監視やSOARなど自動化技術を活用したセキュリティ運用が可能です。ゼロトラストの導入により、EDRやSOAR、AIを活用した自動化対応が可能になり、少人数のチームでも効率的に脅威を検知・封じ込めやすくなります。完全にSOC(セキュリティ監視センター)不要になるわけではありませんが、従来よりも少ないリソースで高いセキュリティ水準を維持できます。
さらに、手動では難しい大量のアラートの振り分けや優先度判断も自動で実施。限られた人的リソースをより重要な業務に集中できます。
関連記事:SOARとは?基礎知識やSIEMとの違い、導入ポイントについて解説
ゼロトラストの基本前提と構成要素
ゼロトラストを理解するには、その基本となる前提原則と主要な構成要素を押さえておく必要があります。ここではゼロトラストの3つの前提と、システムを構成する主な要素について解説します。
ゼロトラストの3つの基本前提
ゼロトラストには3つの基本前提があります。
- 常に検証(Always Verify):全ユーザー・全端末のアクセスを、毎回厳密に認証・認可する
- 最小権限(Least Privilege):業務に必要な最小限のアクセス権だけを与える
- 侵害を前提とする(Assume Breach):侵入は避けられないという前提で内部対策を強化する
これらの前提に基づくことで、内部のユーザーや端末であっても無条件に信頼せず、常にリスクを最小限に抑える設計が可能となります。特にクラウドやリモート環境では、この3つの前提に基づいてセキュリティ環境を構築することで不正アクセスや内部不正の早期発見・遮断につながります。
ゼロトラストを構成する要素
ゼロトラストは主に以下の5つの要素で構成されています。
- ユーザーの認証・認可:ID管理や多要素認証(MFA)で正当な利用者のみアクセスを許可
- デバイスの状態確認:パッチ適用やEDR導入済みなど安全が確認された端末だけを許可
- 通信の暗号化・ネットワーク制御:全通信の暗号化とネットワーク細分化で侵入後の拡散を防止
- リソースへのアクセス制御:各アプリやデータごとに権限を設定し、ABACによる動的な許可判断を導入
- ログ・行動の可視化と異常検知:SIEMでログ監視・分析を行い、SOARで自動対処する常時監視体制
これらの要素を組み合わせることで、ユーザーやデバイスごとに最適なアクセス制御を行い、万が一の侵入後も被害の拡大を最小限に抑えることが可能になります。デジタル庁も、ゼロトラストの導入においてID管理・や端末管理、ネットワーク分離、ログ管理の重要性を明示しており、公共・民間問わず実装が求められています。
出典:ゼロトラストアーキテクチャ適用方針|デジタル庁![]()
関連記事:多要素認証(MFA)とは?仕組み・メリットから導入方法まで解説
関連記事:IDaaSとは?機能や導入メリット、選定時のポイントなどをわかりやすく解説
ゼロトラストを実装するための5大要素
実際に自社システムにゼロトラストを導入するには、特に重視すべき5つのポイントがあります。以下にその5大要素を順に説明します。
認証・認可の集中管理
ゼロトラストを実装するためには、ユーザー認証と権限認可を一元的かつ動的に管理する仕組みが必要です。SSOやID管理基盤を導入し、社員がどの条件下でどのリソースにアクセスできるかを一括で制御します。
アクセスのたびに都度ポリシーに基づき認証・認可を再評価し、状況に応じてセッションを制限または終了させることで、常に最新の条件で安全性を担保します。
端末セキュリティの強化
ゼロトラスト導入には、利用端末の安全性確保も欠かせません。アクセス前に端末がパッチ適用済み、マルウェア未感染といったように最新の状態であるかをチェックし、安全と確認できた端末のみ接続を許可します。
必要に応じてMDM(モバイルデバイス管理)で端末を統制し、改ざんされたデバイスや非セキュアな端末からのアクセスを遮断することも重要です。
ネットワーク制御の変更
従来の境界型ネットワーク設計を見直し、クラウド利用を前提とした柔軟なネットワーク制御に移行します。ゼロトラストの思想に基づき、仮想ネットワーク上でアクセス制御を行うことで、場所を問わず安全性の高い接続が実現可能です。
たとえばデジタル庁の政府共通プラットフォーム(GSS)ではゼロトラストセキュリティとオーバーレイネットワークを組み合わせ、通信ごとに厳密なアクセス制御を実現しています。このようにマイクロセグメンテーションやSD-WANを活用し、ネットワーク全体にゼロトラストを適用することが重要です。
出典:ガバメントソリューションサービス(GSS)について|デジタル庁![]()
属性ベースのアクセス制御(ABAC)適用
ゼロトラストを支える認可方式として、属性ベースアクセス制御(ABAC)の導入が効果的です。ABACではユーザーの属性、アクセスするリソースの属性、アクセス元の環境やデバイスの状態など複数の要素に基づき、細かい条件付きでアクセス可否を判断します。
日本のデジタル庁もゼロトラストアーキテクチャでのABAC適用に関する技術要件や手順を示したガイドラインを公開しています。こうした指針を参考に、自社のセキュリティポリシーに基づいたABACルールを策定し、動的かつ柔軟なアクセス制御を実現しましょう。
出典:ゼロトラストアーキテクチャ適用における属性ベースアクセス制御に関する技術レポート|デジタル庁![]()
常時監視と継続的リスク評価(CRSA)
ゼロトラスト環境では、システムを常に安全な状態に保つためリアルタイム監視と継続的なリスク評価が欠かせません。ネットワーク上の各端末の脆弱性やアクセス挙動を常時監視し、リスクレベルを点数化して管理します。
デジタル庁はこの仕組みをCRSAアーキテクチャとして推奨しており、日常的にリスク診断と対処を行うことで組織の「未然防止力」や「インシデント対応力」の向上を目指しています。常時監視と自動対処を取り入れることで、万が一侵入された後でも被害を最小化し、システム全体のセキュリティ水準を継続的に維持できるでしょう。
まとめ
ゼロトラスト(ゼロトラストモデル)は、従来の「内部は安全・外部は危険」という前提を捨て、「何も信頼しない」を基本とする新しいセキュリティ戦略です。リモートワークやクラウド活用が当たり前となった現代では、このゼロトラストの考え方が自社の重要情報を守る上で不可欠となっています。
ゼロトラストを導入して、サイバー攻撃による情報漏洩や不正アクセスのリスクを低減していきましょう。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
若園 直子
専門的な内容でも、読者にとって親しみやすく、実践につながる形で伝えることを大切にしています。