![]() コラム
コラム
多要素認証とは?
なぜ必要になっているの?その現状や実例を徹底解説!
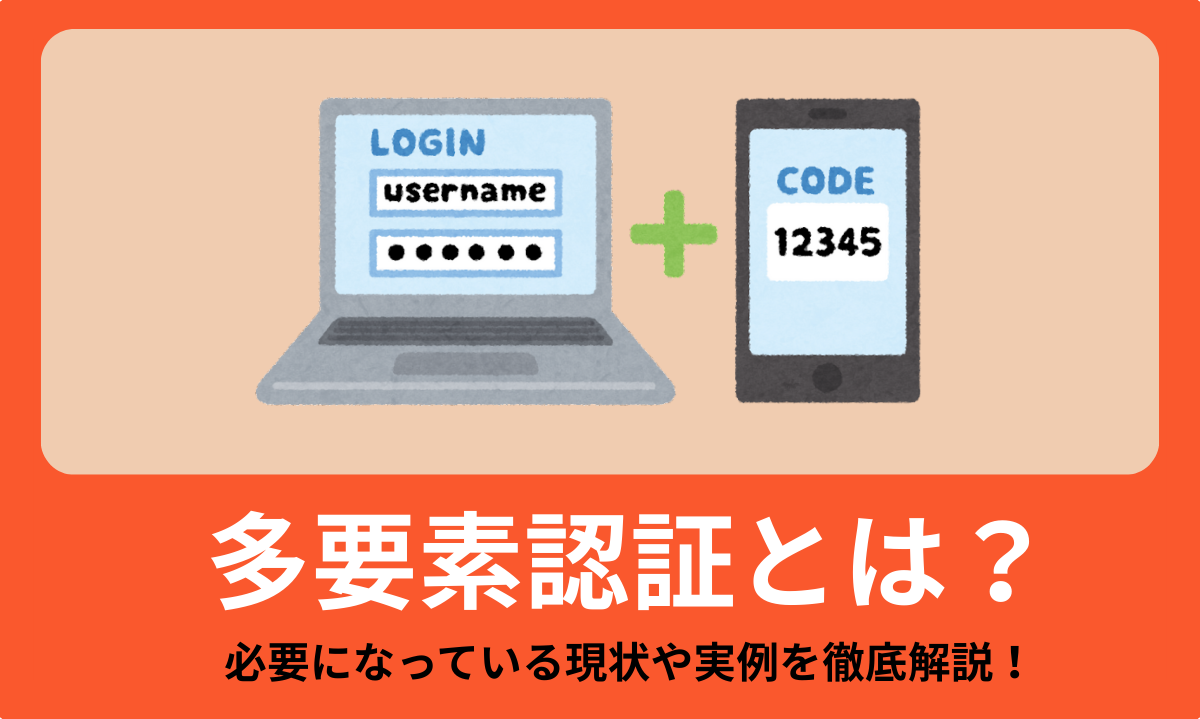
![]() 最終更新日:
最終更新日:
多要素認証(MFA:Multi-Factor Authentication)とは、IDとパスワード(知識情報)に加え、スマートフォンなどの所持情報や指紋・顔認証といった生体情報を組み合わせて本人確認を行う仕組みです。
本記事では、多要素認証の基本から導入するメリットや注意点、導入されている実例を挙げて解説します。
多要素認証とは
はじめに多要素認証とはどういった認証方法か、必要とされている背景や二段階認証との違いを解説します。
多要素認証は認証信頼性を高める方法のこと
多要素認証は2つ以上の情報を合わせて認証を行うことで、認証の信頼性を高める方法です。3つの認証要素(知識情報・所持情報・生体情報)のうち2つ以上を使うことで、1つの要素が破られても不正アクセスを防ぐことができ、パスワード認証の限界を補う強力なセキュリティ対策として、多くのクラウドサービスや企業システムで導入が進んでいます。
多要素認証が必要とされる背景
近年サイバー攻撃や不正アクセスはますます巧妙化しており、パスワードだけに頼る認証では十分に対処できなくなっています。 たとえば総当たり攻撃(ブルートフォース)や辞書攻撃、さらにはAIを活用した高速なパスワード解読などサイバー攻撃の脅威は複数に及びます。実際、多くの企業で「推測されやすいパスワードの使用」や「使い回し」が原因となり、情報漏洩が発生しています。
またクラウドサービスやテレワークの普及によって、社内システムへのリモートアクセスが一般化し、社外からの不正アクセスのリスクも高まっています。こうした環境下ではログイン情報の流出によって、社内ネットワーク全体が危険にさらされるケースも少なくありません。
このような背景から、ID・パスワードに加えて第二の認証手段(所持情報や生体情報)を組み合わせる多要素認証の導入が、企業にとって不可欠なセキュリティ対策となっています。多要素認証を導入することで、仮にパスワードが流出しても不正ログインのリスクを大幅に低減できます。
多要素認証と二要素認証、二段階認証の違い
多要素認証は、以下のような異なる認証要素を2つ以上組み合わせて本人確認を行う方法です。
- 知識情報:パスワードや秘密の質問など
- 所持情報:スマートフォンやICカードなど
- 生体情報:指紋や顔認証など
たとえば「パスワード」+「スマートフォンで届く認証コード」のように、別種類の要素を組み合わせて認証することで、不正アクセスを防ぐ強固なセキュリティを実現できます。
二要素認証は多要素認証の一部で、以下の例のように3つの認証要素のうち異なる2つを組み合わせる方法です。
- パスワード(知識情報)+ワンタイムパスワード(所持情報)
- ICカード(所持情報)+指紋認証(生体情報)
二段階認証は「認証を2回行う」ことが特徴です。 ただし以下の例のように使われる要素が同じであっても構わないため、安全性には差が出ることがあります。
- パスワード → 秘密の質問(どちらも知識情報)
- パスワード → メールで送られる認証コード(知識+所持)
2回の認証があっても、同じ種類の要素では「二要素認証」にはならないため注意が必要です。
これらの違いを表にまとめると以下のようになります。
| 項目 | 多要素認証 | 二要素認証 | 二要素認証 |
|---|---|---|---|
| 定義 | 3つの要素のうち2つ以上を使う認証方式 | 3要素のうち2つの異なる要素を使う |
2回の認証を行う方式 (要素は同じでもOK) |
| 要素の組み合わせ | 異なる2つ以上 | 異なる2つ |
同じ要素でも可 例:知識情報+知識情報 |
| 具体例 | パスワード+スマホ認証コード | パスワード+ワンタイムパスワード | パスワード+秘密の質問 |
| セキュリティ強度 | 高い | 高い | 同じ要素だと強度はあまり上がらない |
多要素認証で使われる「要素」
多要素認証に用いられる要素は、以下3つから構成された情報により行われています。
知識情報
知識情報は本人だけが知っている情報を用いた認証方式で、パスワードやPINコード、秘密の質問などが該当します。導入コストが低く広く使用されていますが、記憶に依存するため管理が煩雑になりやすく、「使い回し」「推測されやすい単語の使用」「メモによる管理」といった行為が情報漏洩リスクを高めます。そのため、知識情報のみの認証はセキュリティの限界があるとされ、他要素との併用が推奨されます。
| 代表例 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
|
パスワード PINコード 秘密の質問 |
・実装・運用コストが低い ・物理的な機器が不要 ・導入しやすい |
・使い回しや漏洩リスクが高い ・人間の記憶に依存 ・フィッシング被害に脆弱 |
所持情報
所持情報は本人が持っている物を使った認証方式で、ICカード、ワンタイムパスワード(OTP)、QRコード、デジタル証明書などが代表例です。知識情報よりもセキュリティは強固ですが、物理的な紛失・盗難・故障といったリスクがあるため、他要素と組み合わせて使用することが推奨されます。
| 代表例 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
|
スマートフォン ICカード デジタル証明書 |
・オンライン攻撃に強い ・デバイス使用で確実性が高い |
・紛失・盗難のリスク ・管理・運用コストがかかる ・ユーザー教育が必要 |
生体情報
生体情報は指紋・顔・虹彩・声紋・静脈など個人固有の身体的特徴を用いた認証方式です。持ち運び不要で利便性が高く、偽造も困難なためセキュリティ性に優れています。一方で専用デバイスの導入コストや、情報漏洩時に変更ができないリスク、バックアップ用パスワード管理が必要といった課題も伴います。
| 代表例 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
|
指紋認証 顔認証 虹彩認証 静脈認証 |
・持ち運び不要で利便性が高い ・偽造しにくく認証が高速 |
・導入コストが高い ・認証精度にばらつきがある ・一度流出すると変更できない |
多要素認証の実例
実際に実用化されている多要素認証の例を挙げてみましょう。
スマートフォンやタブレットなどのロック解除
スマートフォンやタブレット端末のロック解除を行う際の認証方法として、パスワードに加えて指紋や顔情報が用いられています。これらは、知識情報と生体情報を組み合わせた多要素認証です。
銀行のATM
金融機関のATMを利用する場合も認証が必要になります。ATMは、キャッシュカードとパスワードを組み合わせた多要素認証です。この場合、所持情報と知識情報の組み合わせが認証時に活用されています。
オンラインバンキング
インターネットを通じて銀行の各種サービスを利用できるオンラインバンキングにおいても、多要素認証が取り入れられています。アカウント認証の際に、ID・パスワードに加えてワンタイムパスワードや指紋認証・顔認証といった方法を組み合わせた多要素認証が活用されています。
多要素認証を導入するメリット
多要素認証を取り入れることで得られるメリットを紹介します。
セキュリティの向上
多要素認証を導入する最大のメリットは、セキュリティ強化にあります。パスワード(知識情報)だけでは防ぎきれない不正アクセスも、指紋認証やワンタイムパスワードなど異なる認証要素を組み合わせることで、突破されるリスクを大幅に低減できます。
特にクラウドサービスの普及やリモートワーク拡大により、社外からアクセスが増える今、企業の機密情報や顧客データを守るためにも、多要素認証導入は必須といえるでしょう。セキュリティ体制強化は、取引先や顧客からの信頼獲得にも直結します。
サイバー攻撃への対策
サイバー攻撃である総当たり攻撃やフィッシング、マルウェアなど手口は年々巧妙化しています。特に「パスワードの使い回し」や「推測しやすい設定」はリスクとなり、AIを活用した自動攻撃によって突破されるケースも増えています。
このような背景から、異なる認証要素を組み合わせて本人確認を行う多要素認証は必要不可欠といえるでしょう。多要素認証を導入すれば、パスワードが漏れても他要素で不正ログインを防ぐことができ、情報漏洩や不正アクセスリスクを軽減できます。
クラウドサービスへの対策
リモートワークなどの業務形態が浸透したことで、外部の事業者が提供するクラウドサービスを活用した働き方が増加しています。社内の情報を外部サービスにアクセスして業務を行うクラウドサービスの特性上、情報保護の対策が必須といえます。
クラウドサービスを選択する際には、多要素認証といったセキュリティ面が十分に整備されているかということも重視して決定するようにしましょう。
多要素認証を導入する際の注意点
多要素認証の導入にあたって注意したい点を紹介します。
ユーザーの利便性を考慮する
多要素認証はセキュリティ強化に有効ですが、面倒で時間がかかると感じるケースもあります。たとえば、ログイン毎に認証アプリでコード確認したり、顔認証や指紋認証を求められたりすると、操作の手間やストレスにつながります。特に業務用システムのような1日に何度もログインする環境では、生産性低下の要因にもなりかねません。
そのため、導入時にはセキュリティ強度と使いやすさのバランスが重要です。たとえば次のような工夫が必要になるでしょう。
- 信頼済みの端末には一定期間ログイン省略設定にする
- シングルサインオン(SSO)で複数サービスの認証を一元化する
- 生体認証など負担の少ない手段を導入する
利便性を損なわずにセキュリティを高める設計が、多要素認証を成功させるポイントです。
導入・運用コストがかかる
多要素認証はセキュリティを高める一方で、導入・運用にコストがかかります。特に生体認証は専用機器の購入や保守が必要で、初期投資も高額です。ICカードやトークンも同様に管理負荷がかかります。コストを抑えたい場合は、スマートフォン認証アプリなど低コストな手段を選ぶのも有効です。必要なセキュリティレベルと予算のバランスを見極めた設計を心がけましょう。
総合セキュリティ対策なら
パロアルトネットワークス
多要素認証の導入には、利便性とコスト面での検討が欠かせません。導入効果を最大化するには、企業ごとの業務フローやIT環境に即した適切な設計・運用が必要です。
パロアルトネットワークスは多要素認証に関連する製品に留まらず、さまざまなセキュリティ製品を提供している実績豊富なサイバーセキュリティ企業です。セキュリティレベルの高い多要素認証の導入にあたって、不明点や問題点などをお悩みのご担当者様は、ぜひパロアルトネットワークスへご相談ください。
まとめ
多要素認証の導入には、利便性の低下や導入・運用コストといった課題をクリアしつつ、慎重な設計が欠かせません。今後ますます高まるセキュリティリスクに備えるためにも、早期に現実的な対策を検討・実施していきましょう。

