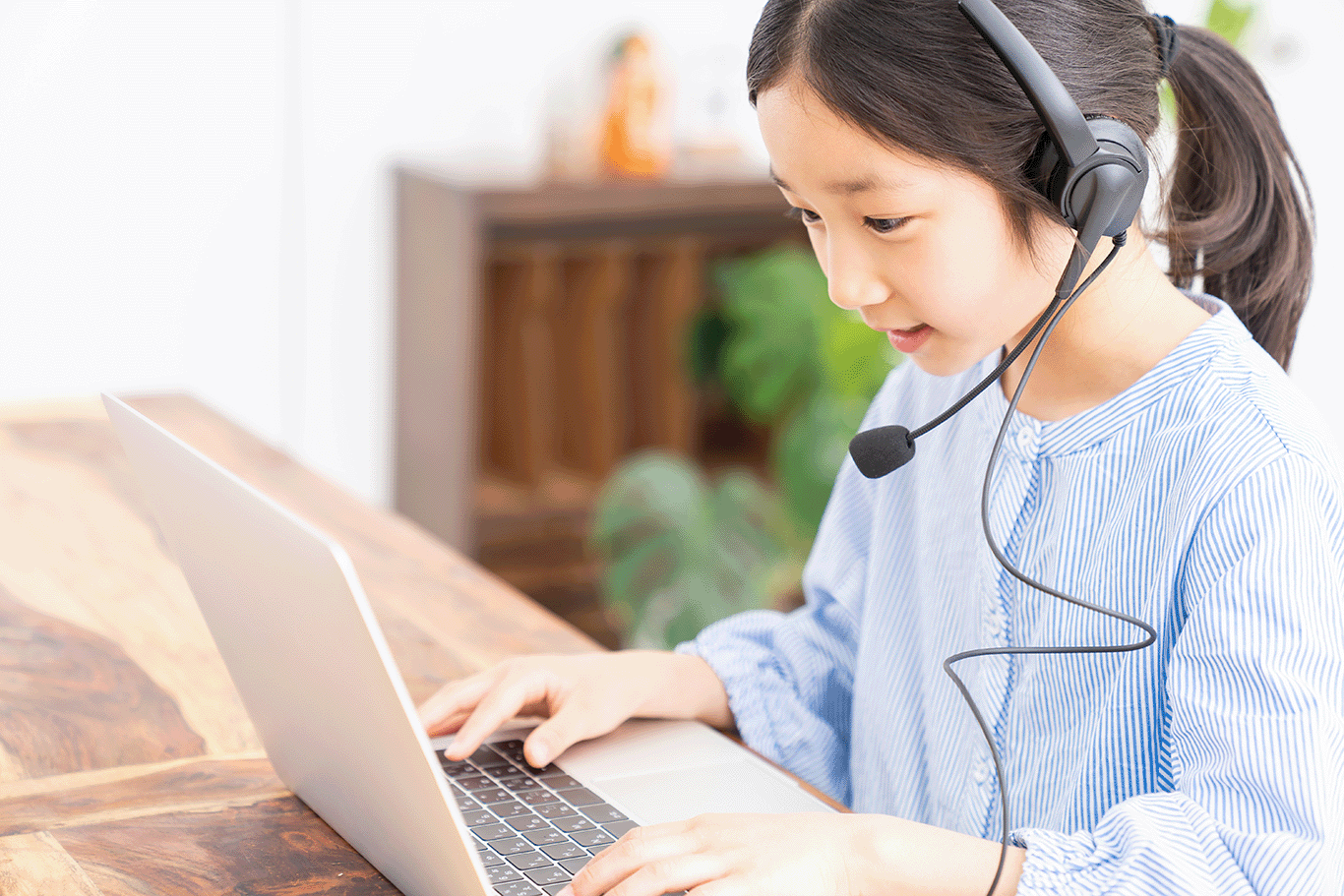学校のタブレットでできることとは?活用事例とメリットを紹介


「学校でタブレットを導入したものの、実際にどう活用すればいいのかわからない」「ICT教育に力を入れたいが、タブレットのどのような使い方が効果的なのか見えてこない」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
GIGAスクール構想第2期(NEXT GIGA)に切り替わり、ICTの利活用がより重視されるようになった中、これらの具体的な活用法や活用するメリット・デメリットなどを体系的に理解している教育現場はまだ多くありません。
この記事では、学校のタブレットでできることやタブレット活用の具体的な事例をご紹介します。また、新たにタブレットを導入する方に向けて導入時のポイントや導入にかかる費用もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
SB C&Sでは、教育現場で活用できるLearning Accelerators (ラーニング アクセラレーターズ)を強みとしたWindows 11 Pro Education 搭載パソコンの導入サポートを行っています。
タブレットとして使用できる機種もあるため、ぜひ興味のある方は以下のページをご覧いただき、お気軽にご相談ください。
学校のタブレットでできること

現在はGIGAスクール構想の推進により、全国の学校で一人一台のタブレット端末が整備され、教育現場でのICT活用が進んでいます。
学習用のタブレットは、授業の効率化や学習の質の向上、児童生徒の主体的な学びを促進するツールとして注目されています。ここでは、学校のタブレットでできることを具体的にご紹介します。
一斉学習
一斉学習においてタブレットを活用することで、教師一人が同じ授業内容をクラスの児童生徒全員に対して一斉に教える従来の授業スタイルを大きく変え、教師と児童生徒の双方向のコミュニケーションを促進します。
教師は教材の提示や説明をタブレットを介して効率的に行え、児童生徒はタブレットに表示された教材を見たり触ったりしながら理解を深めることが可能です。また、タブレットを用いることでリアルタイムでのフィードバックや意見交換も容易になり、授業の幅も広がっています。
このようにタブレットを介して、場所を問わずに教員が教材の提示や授業を行ったり、児童生徒が学習を進めたりできることから、タブレットは対面での一斉学習だけでなく、オンライン授業での一斉学習でも活用されています。
一斉学習でできる具体的な内容は、次のとおりです。
児童生徒への教材の配布
タブレットを活用することで、教材の配布が迅速かつ効率的に行えます。教師は、PDFや画像、スライドなどの教材をクラウド上にアップロードし、児童生徒は自身の端末からすぐにアクセスが可能です。
これにより、紙の教材を印刷・配布する手間が省け、授業の準備時間を短縮できます。また、児童生徒は自分のペースで教材を閲覧・復習できるだけでなく、自由に拡大・縮小・書き込みなどが行えるため、個々に合った学習を進められます。
例えば、福井県の小学校では、国語の授業でタブレット端末を活用し、タブレット上での挿絵や写真の並び替え、動画撮影、ノート機能などさまざまな機能を使って子どもの理解力や学習意欲の向上を促しています。事例の詳細は、福井県の義務教育課が提供している資料をご確認ください。
授業で使用する動画の配布
教師は、授業内容に関連する動画をクラウド上に共有し、児童生徒は自分の端末で視聴できます。これにより、動画を用いた視覚的な理解が深まり、図やテキストの説明では理解が難しい概念や手順も理解しやすくなります。
また、児童生徒は配布された動画を繰り返し視聴することで、復習や予習にも活用可能です。教師は、各児童生徒の動画の視聴履歴や理解度を把握し、個別の指導にも役立てられるでしょう。
提出物の回収
タブレットを活用することで、児童生徒は課題やレポートをタブレット上で作成し、クラウド上に提出できます。教師は、提出されたデータを一元管理できるため、フィードバックや評価も効率よく行えるようになります。
また、提出状況の把握や未提出者へのリマインドも容易になるため、授業をスムーズに進められるでしょう。
個別学習
タブレットを活用した個別学習は、児童生徒一人一人の理解度や興味関心に応じた学習を可能にします。これにより、学習の効率化や自発的な学習の促進が期待できます。ここでは、タブレットを活用した個別学習の具体的な方法や効果についてご紹介します。
児童生徒の思考を深める学習の実現
タブレットを活用することで、児童生徒は自らの考えを深める学習が可能になります。例えば、シミュレーションアプリや動画教材を用いることで、実際に体験することが難しい実験や現象を視覚的に理解できます。
また、デジタル教材を使って試行錯誤することにより、問題解決能力や論理的思考力を養えます。これらの活動を通じて、児童生徒が主体的に学べるようになり、学習内容に対して深い理解を得られるでしょう。
児童生徒の個々の能力に合わせた学習環境の提供
タブレットを活用することで、児童生徒一人一人の能力や理解度に応じた学習環境を提供できます。AIドリルや学習アプリを用いることで、個々の習熟度に合わせた課題を提示し、効果的な学習が可能になります。
また、学習履歴やつまずいている部分の傾向を分析することで、教師は児童生徒の理解度を把握し、適切な指導を行えます。これにより、全ての児童生徒が自分のペースで自分のレベルに合った学習を進められ、スムーズな学力向上が期待できます。
表現力の育成
タブレットを活用することで、児童生徒の表現力を育成できます。例えば、プレゼンテーションソフトや動画編集アプリを用いて、自分の考えや学んだことを視覚的に表現することが可能です。
また、音声録音や写真撮影、動画撮影を通じて、文章以外の方法で自分の意見や感想を伝える力を養えます。これらの活動を通して、児童生徒の創造力やコミュニケーション能力の向上が期待できるでしょう。
情報収集の効率化
タブレットを活用することで、児童生徒は効率的に情報収集を行えます。インターネットを利用した検索や、デジタル教材を用いた学習により、必要な情報を迅速に得られます。
例えば、理科の授業でタブレットを用いて撮影・編集した写真や動画を活用する観察記録などは、視覚的な情報の整理や分析が容易に行えます。これらの活動を通じて、児童生徒は情報を主体的に収集・判断する力を身につけられるでしょう。
家庭学習への活用
タブレットを家庭学習に活用することで、学校外でも継続的な学習が可能になります。例えば、クラウド上で課題を配信・提出する仕組みを整えることで、教師と児童生徒の間でスムーズなやり取りが行えます。
また、学習アプリを用いたドリル学習や、動画教材を活用した予習・復習により、児童生徒は自分のペースで学習を進めることが可能です。これにより、家庭での学習習慣の定着や、学力の向上が期待できます。
協働学習
タブレットを活用した協働学習は、児童生徒同士が意見を共有し、共同で課題に取り組むことで、コミュニケーション能力や問題解決能力を育成します。タブレットを用いることで、場所や時間にとらわれない協働作業が可能となり、学習の幅を広げることが可能です。
ここでは、タブレットを活用した協働学習の具体的な方法や効果についてご紹介します。
児童生徒同士の意見交換
タブレットを活用することで、児童生徒同士の意見交換を活発にできます。例えば、協働学習を支援する学習アプリなどを使用することで、各自の考えをリアルタイムで共有し、他者の意見を参考に学習を進められます。
これにより、児童生徒は多様な視点を持てることから、思考を深められるだけでなく、他者との意見交換を通じて相手の考えを尊重し、自分の意見を適切に伝える力が養われます。
協働制作
タブレットを活用した協働制作では、児童生徒が役割分担をしながら一つの作品を共同で作り上げることが可能です。例えば、プレゼンテーション資料や動画の制作において、各自が担当部分を作成し、クラウド上で共有・編集することで、効率的な協働作業が実現します。
このような活動を通じて、児童生徒は協力することの大切さや、チームで目標を達成する喜びを学べるでしょう。
授業中の発表
タブレットを活用することで、授業中の発表をより効果的に行えます。例えば、児童生徒が作成した資料を大型提示装置に映し出すことで、クラス全体で共有可能です。
また、発表内容をクラウド上で共有することで、ほかの児童生徒が事前に内容を確認し、質問や意見を準備できます。これにより、発表の質が向上し、活発な意見交換を促せるでしょう。
海外の学校や専門家との学習
タブレットを活用することで、海外の学校や専門家との学習が可能です。例えば、ビデオ会議ツールを利用して、海外の児童生徒と交流したり、専門家から直接指導を受けたりすることができます。
これにより、児童生徒は異文化理解を深め、視野を広げられるでしょう。また、専門家との交流を通じて、学習意欲の向上や将来のキャリア形成にも好影響を与えられます。
学校でのタブレット活用が重要視されている理由
ここまで、学校のタブレットでできることを一斉学習・個別学習・協働学習の側面からご紹介しました。
近年、GIGAスクール構想の推進により、学校教育においてはICTの活用が急速に進められており、特にタブレット端末の導入・活用は、教育の質の向上や学習環境の多様化を実現する手段として注目されています。
ここでは、学校でのタブレット活用が重要視されている背景を詳しくご紹介します。
学校におけるICTの利活用が世界の中でも遅れているため
日本の学校教育におけるICTの利活用は、世界的に見て後れを取っています。
2022年に行われた「生徒の学習到達度調査2022年調査(PISA20228)」では、OECD(経済協力開発機構)加盟国のうち、学校でのICTリソースの利用しやすさは、日本は平均を上回っています。

出典:OECD生徒の学習到達度調査2022年調査(PISA2022)のポイント|国立教育政策研究所
一方で、教科ごとでのICTの利用頻度は、日本はOECD平均を下回っていることから、学校の授業での活用が十分にできていないことがわかります。

出典:OECD生徒の学習到達度調査2022年調査(PISA2022)のポイント|国立教育政策研究所
この結果から、世界的に日本は学校教育におけるタブレットをはじめとしたICT利活用に後れを取っており、さらにICTを活用できる環境を整えることが課題となっています。
GIGAスクール構想(NEXT GIGA)を推進させるため
文部科学省は、教育のICT化を推進するために「GIGAスクール構想」を提唱しました。この構想では、児童生徒一人一台の端末整備や高速大容量の通信ネットワークの構築など、教育現場のICT環境の充実を目指しており、2025年現在は「NEXT GIGA」が推進されています。
GIGAスクール構想の第2期とされるNEXT GIGAでは、端末の整備だけでなく授業での利活用をより促進させることや、端末の整備から約5年が経過し、端末の劣化などによってスムーズな学習が妨げられることを防げるよう更新を支援したり、自治体間での端末活用の格差を解消したりすることが主な目標とされています。
個別最適な学びの環境を実現するため
タブレットの活用は、児童生徒一人一人の特性や学習進度に応じた「個別最適な学び」の実現に貢献します。「学校のタブレットでできること」でも触れたように、タブレットを活用することで、児童生徒の理解度や興味関心に合わせた教材の提供や、学習履歴の分析が可能となり、より効果的な指導が行えます。
これにより、すべての児童生徒が自分のペースで自発的に学習を進められる環境が整備され、学力の向上や学習意欲の喚起などの効果が期待できます。
マイクロソフトは、Microsoft 365 Educationを活用した「個別最適な学び」を提案しています。
ぜひあわせてご覧ください。
学校でのタブレット活用事例
ここまで、学校でのタブレット活用が重視される理由についてご紹介しました。実際に、タブレットは学年や教科を問わず、さまざまな教育現場で効果的に活用されています。ここでは、小学校、中学校、高等学校における具体的な活用例をご紹介します。
小学校での活用例【国語】
小学校の国語の授業では、新出漢字を学習する際に、デジタル筆順辞典を活用しています。デジタル筆順辞典では、漢字を手書き入力で調べられ、タブレットの大きな画面に漢字を表示させながら、一画ずつ書き順や線の動きを確認しつつ漢字練習が行えます。
タブレットに直接指で大きく、普段よりもゆっくりと漢字を丁寧に書くことで、不器用な児童にとっても扱いやすく、「できた」という達成感が学習意欲の向上につながりました。

中学校での活用例【外国語】
中学校の外国語の授業では、タブレットを用いて即興プレゼンテーションを行う授業を行いました。
この授業では、自身が興味を持った国を調べ、当該国の魅力だと思った画像をタブレットに保存します。プレゼンテーションを始める前に、聞き手の生徒は自身の興味があることを話し手に伝えます。話し手は、聞き手の興味に合う画像をタブレットに保存している画像の中から選び、タブレットの画像を見せながら即興でプレゼンテーションを行います。
タブレットで画像検索を簡単に行えるだけでなく、画像を大画面に映し出しながら話せるため、プレゼンテーションを行いやすくなり、英語力・コミュニケーション能力の向上を養えました。

高等学校での活用例【体育】
高等学校の体育の授業では、水泳の授業でタブレットを活用し、水泳の行い方に関する知識をプレゼンテーションソフトで確認しながら、泳ぎの見本動画と自分・ペアの動画を比較して課題を発見し、練習方法を選びました。
なお、練習方法を検討する際も、タブレットの音声入力や文字入力を用いながら生徒同士で話し合う形式にしたことで、自身の課題を見つける力や、課題に対して有効な手段を選ぶ力、相手に伝える力などを養えました。

出典:児童生徒の1人1台のICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集 第4章 ICT端末の実践|スポーツ庁
学校でタブレットを活用するメリット
ここまで、小学校・中学校・高等学校でのタブレット活用例をご紹介しました。上記のように、タブレットの活用は、教育現場に多くの変化をもたらしています。
しかし、タブレットは直感的な操作性や学習の効率化、持ち運びの利便性など、多くのメリットがあります。具体的には、次のとおりです。
タッチだけで操作ができる
タブレット端末は、キーボードやマウスを使用せずに、画面を直接タッチすることで操作が可能です。これにより、ICT機器に不慣れな児童生徒でも直感的に操作でき、学習への導入がスムーズになります。
特にキーボード操作に慣れていない低学年の児童にとっては、タッチ操作による動画やイラストを使った学習が効果的であり、興味・関心を引き出せるでしょう。
学習の質向上や効率化が期待できる
タブレットを活用することで、文字や図だけでなく、動画や音声などのコンテンツを用いた授業が可能となり、学習の質が向上します。
また、デジタル教科書や学習アプリなどのデジタル教材を使用することで、児童生徒の理解度や興味関心に合わせた個別最適な学びが実現し、学習の効率化が期待できます。さらに、AIによる学習分析やツール上での学習状況を一元管理が可能になることで、教員の業務負担の軽減や、授業の進行管理の効率化にも寄与します。
持ち運びやすく活用の幅を広げやすい
タブレットは軽量でコンパクトな作りのため、児童生徒が簡単に持ち運べます。これにより、教室内だけでなく、校庭や図書館、自宅など、さまざまな場所での学習が可能となり、学習の幅が広がります。
また、クラウドサービスを活用することで、学習データの共有や保存も容易になり、教材を持ち運ぶ負担や紛失リスクも払拭できます。
タブレットを導入・活用する際の注意点

タブレットの導入・活用にはここまでご紹介したようなメリットがある一方で、以下のような注意点もあります。タブレットの導入や活用を考える際は、メリットだけでなく、これらの注意点も考慮したうえで最適な方法を検討することが大切です。
生徒のモチベーションを維持する必要がある
タブレットの導入・活用初期には、児童生徒の学習意欲が高まる傾向がありますが、時間の経過とともにモチベーションの維持が課題となることがあります。
特に、デジタル教材の閲覧やドリル学習だけでは、単調さを感じて飽きが生じる可能性があるため、常にタブレットで同じ作業を繰り返すのではなく、文部科学省など各所が公開している事例集などを参考に、新たな活用方法を考える必要があります。
参照:各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料|文部科学省
保護者の理解やサポートが必要になる
学校でタブレットを新規で導入する際は、保護者の理解と協力が必要になります。保護者からは、「学習時間の管理が難しい」「視力や姿勢への影響が心配」「ゲームなどの学習以外に使われないか不安」といった声がよくあがります。
これに対し、学校では、定期的な保護者会を開いて活用事例を紹介したり、家庭でのルール作りを支援するガイドラインを提供したりするとよいでしょう。さらに、ICT支援員による保護者相談窓口の設置や、定期的な保護者だよりの発行など、学校と家庭が協力してタブレット活用を支える仕組みを整えることが大切です。
セキュリティー対策を行う必要がある
タブレットの導入や買い替え時は、セキュリティー対策が不可欠です。タブレットをインターネットに接続することで、情報漏えいやサイバー攻撃のリスクが高まります。
また、児童生徒が不適切なサイトにアクセスしたり、個人情報を誤って共有したりする可能性もあります。これらのリスクを軽減するために、学校では以下のような対策が求められます。
- ● ウイルス対策ソフトの導入と定期的な更新
- ● 不適切なサイトへのアクセスを制限するフィルタリングソフトの活用
- ● パスワードの適切な管理と定期的な変更
- ● 児童生徒への情報モラル教育の実施
- ● 端末の紛失や盗難に備えたリモートロック機能の設定
これらの対策を講じることで、生徒が安心して学習できる環境を構築し、タブレット活用のメリットを最大限に生かせるでしょう。
児童生徒がスムーズに学習に活用できるようサポートする
タブレットを効果的に活用するためには、児童生徒が操作に慣れ、学習にスムーズに取り組めるようサポートすることが重要です。具体的には、以下のような取り組みがあげられます。
- ● 初期導入・買い替え時の操作指導:タブレットの基本的な操作方法や、使用するアプリケーションの使い方を丁寧に指導します。
- ● 学習支援ツールの活用:学習や授業を支援するシステムやアプリを導入することで、児童生徒の学習状況をリアルタイムで把握し、個別にサポートすることが可能です。
- ● ICT支援員の配置:ICT支援員を配置することで、児童生徒の操作に関する質問やトラブルに迅速に対応でき、学習の妨げを最小限に抑えることができます。
これらの取り組みにより、児童生徒がタブレットを効果的に活用し、学習意欲の向上や学習成果の向上につなげられます。
教員向けに研修やサポートを行う
タブレットを活用した授業を効果的に行うためには、教員自身がタブレットの操作や活用方法に習熟していなければなりません。そのため、教員向けの研修やサポート体制の整備が必要となります。
- ● 基本操作研修の実施:タブレットの基本的な操作方法や、授業で使用するアプリケーションの使い方を学ぶ研修を実施します。
- ● 授業設計のサポート:ICTを活用した授業設計や教材作成の支援を行い、教員が自信を持って授業を行えるようにします。
- ● 外部研修サービスの活用:教員向け研修サービスを利用することで、専門的な知識やスキルを習得することが可能です。
これらの取り組みにより、教員のICT活用能力が向上し、タブレットを効果的に活用した授業の実現が期待できます。
SB C&Sでは、教員の方を対象にしたITスキルアップや新たな授業、業務効率化の提案を行うイベント・セミナーを実施しているため、ぜひこちらもご覧ください。
SB C&Sのイベント・セミナー情報を見る
ICT環境を整備する
タブレットを効果的に活用するためには、安定したICT環境の整備が欠かせません。
2024年4月に文部科学省で発表された「学校のネットワークの現状について」では、すべての授業において多数の生徒が同時に高頻度で端末を使用する際に支障が生じない通信環境を満たす学校が、2023年11月~12月時点で全国で2割程度しかない点を課題としてあげています。

文部科学省では、学校におけるICT環境の整備・運用についてのガイドブックを提供しています。このような資料を参考にしながら、各学校の実情に応じたICT環境の整備を進めましょう。
参照:学校のネットワーク改善ガイドブック 令和6年4月|文部科学省
学校でのタブレット導入にかかる費用
ここまで、学校でタブレットを活用する際の注意点をご紹介しました。
学校でタブレットを新たに導入して活用したり、使用中のタブレットを買い替えるには、端末の購入費用だけでなく、ソフトウエアのライセンス料、ネットワーク環境の整備費用、保守・サポート費用など、さまざまなコストが発生します。これらの費用を正確に把握し、予算計画を立てることが重要です。
なお、文部科学省が推進するGIGAスクール構想においては、全国の小中学校および特別支援学校におけるICT環境の整備を、補助金を交付することで支援しています。
【公立学校の端末整備】
- ● 対象:公立の小・中学校および特別支援学校
- ● 補助基準額:5.5万円/台
- ● 予備機:15%以内
- ● 補助率:3分の2
【国私立・日本人学校などの端末整備】
- ● 対象:義務教育段階の国私立・日本人学校など
- ● 補助基準額:5.5万円/台
- ● 予備機:15%以内
- ● 補助率:国立→10分の10、私立→3分の2、日本人学校など→3分の2
この補助金は、児童生徒一人一台端末を新規に整備または更新する際に活用できます。
そのほかにも、通信環境を整備する際に交付される補助金である「公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金」や、高等学校向けの補助金である「高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金」などがあります。
詳しくは、文部科学省の公式サイトをご確認ください。
参照:基金による1人1台端末の更新について|文部科学省
まとめ
この記事では、学校のタブレットでできることを活用例を交えてご紹介しました。タブレットでの学習は、一斉学習、個別学習、協働学習といったさまざまな授業スタイルに活用できるため、個別最適な学びの実現や、より活発なICTの利活用に貢献するでしょう。しかし、効果的な活用には、セキュリティー対策の徹底や快適な通信環境の整備など、運用体制を整えておくことが重要です。
SB C&SのICT導入支援サービスは、端末の初期設定や不要な端末の下取りなどを行っています。iPadやタブレットPCといった多様な機種に対応し、各学校の教育方針や授業スタイルに合わせた端末の導入サポートが可能です。
また、予備機運用やキッティング、端末延長保証サービス「えんちょー先生」など、導入後の運用に役立つサービスも多数提供しているため、「どのような端末が自分の学校に合うか相談したい」「現在の運用状況を改善したい」といった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。