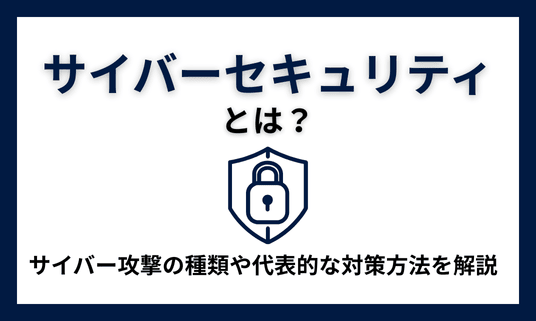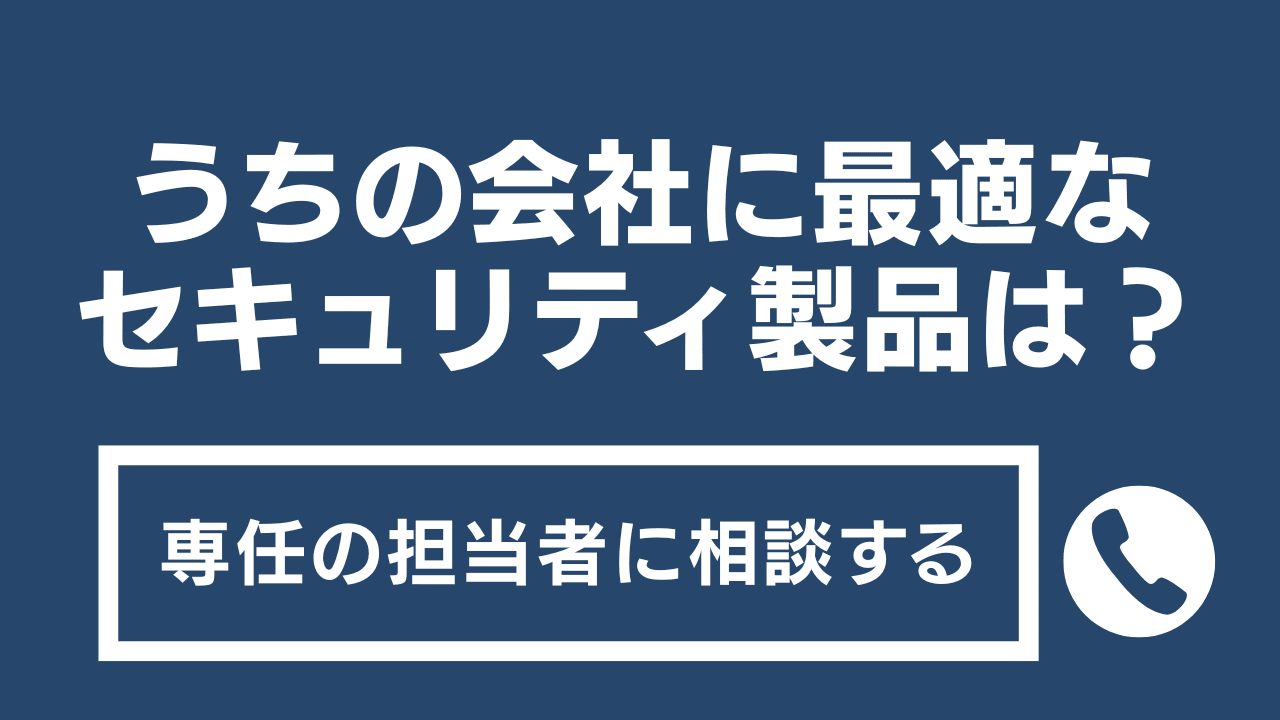2025.9.12

目次
CSIRT(Computer Security Incident Response Team)は、企業や組織内で発生するセキュリティインシデントに対応する専門チームです。インシデント発生時に迅速な初動対応で被害を最小限に抑えるほか、事前の予防対策や脆弱性管理、従業員教育も担います。
近年、サイバー攻撃の巧妙化と頻発により、企業や組織におけるセキュリティインシデント対応の重要性が高まっています。従来の予防中心のセキュリティ対策だけでは限界があり、インシデント発生を前提とした迅速で適切な対応が可能な体制の構築が急務となっています。
そこで注目されているのが、CSIRT(シーサート)という専門組織です。本記事では、CSIRTの基本概念から導入方法まで詳しく解説します。
CSIRT(シーサート)とは
CSIRT(Computer Security Incident Response Team)は、セキュリティインシデントに対応する専門組織のことです。ここでは、CSIRTの必要性や設置状況についてみていきましょう。
CSIRTの必要性について
近年、デジタル化が進む中でサイバー攻撃の手口はますます巧妙になり、企業にとって大きな脅威となっています。これまでの「攻撃を防ぐ」だけの対策では限界があり、「もし攻撃されたらどうするか」を考えた体制づくりが必要になってきました。
CSIRTを社内に設置することで、インシデント発生時の初動対応を迅速に行い、被害を最小限に抑えられます。初動対応が早ければ業務への影響を軽減でき、法律的なトラブルの回避にもつながるのがメリットです。CSIRTは事後対応だけでなく、セキュリティインシデントの予防から復旧まで一貫して対応する包括的な組織として機能します。
CSIRT設置状況について
国内のCSIRT構築運用支援サービス市場は、2016年から2022年にかけて右肩上がりで成長しています。この成長は、企業におけるセキュリティ意識の高まりと、実際のインシデント増加による危機感の表れといえるでしょう。
CSIRTの設置は特に大企業を中心に急速に進んでおり、中小企業においても導入の必要性が認識されつつあります。政府機関や重要インフラ事業者では、法的要求や規制要件を満たすためのCSIRT設置が義務化されているケースも少なくありません。今後もサイバー攻撃の脅威拡大に伴い、組織の規模や業界を問わず、セキュリティインシデント対応能力の向上が課題となるでしょう。
CSIRTとSOC・PSIRTの違い
| 組織名 | 主な目的 | 活動範囲 | 所属部門 | 主な役割 |
|---|---|---|---|---|
| CSIRT(Computer Security Incident Response Team) | 社内で発生するセキュリティインシデントへの対応 | 企業全体の情報システム | 情報システム部門 | インシデント対応、脆弱性管理、教育、再発防止策の実施 |
| SOC(Security Operations Center) | サイバー攻撃の予防・早期発見 | システム・ネットワーク全体 | セキュリティ運用部門 | 24時間365日の監視、異常検知、初期分析 |
| PSIRT(Product Security Incident Response Team) | 自社製品やサービスの脆弱性・セキュリティ問題への対応 | 提供製品・ソフトウェア | 開発・品質管理部門 | 製品の脆弱性対応、パッチ提供、顧客向け情報発信 |
CSIRTと似た役割を持つ組織として、SOCやPSIRTが存在します。それぞれの特徴と役割を理解することで、自社に最適なセキュリティ体制を構築できます。次で詳しく解説します。
SOCとの違い
SOC(セキュリティ・オペレーション・センター)は、企業や組織のシステムやネットワークを24時間365日監視しているセキュリティ部門です。主に予防的な監視活動に重点を置いており、不正アクセスやウイルスの早期発見が主な役割となります。
CSIRTがインシデント発生後の対応に重点を置くのに対し、SOCはシステムやネットワークの監視と異常の検知・分析に重点を置いています。つまり、SOCは「予防と早期発見」、CSIRTは「事後対応と復旧」という役割分担です。実際の運用では、SOCが検知した異常をCSIRTが詳細分析し、対応策を実行する連携体制が構築されることが多くあります。
関連記事:SOC(Security Operations Center)とは?主な機能や役割、構築から運用体制まで解説
PSIRTとの違い
PSIRT(プロダクト・セキュリティ・インシデント・レスポンス・チーム)は、自社が提供する製品やソフトウェアの脆弱性・セキュリティインシデントに対応する組織です。製品の開発段階から販売後の運用まで、安全性を保つために活動しています。
PSIRTが製品を利用している外部のお客様への影響に重点を置いているのに対し、CSIRTは社内のセキュリティを守ることが主な役割です。PSIRTは製品開発や品質管理部門に属することが多く、CSIRTは情報システム部門に属するのが一般的です。また、PSIRTは製品の脆弱性に特化した対応を行う一方、CSIRTは社内全体で発生する幅広いセキュリティインシデントに対応します。
CSIRTの主な役割
CSIRTの役割は主に以下の4つです。
インシデントへの事前対応
事前対応は、セキュリティインシデントの発生を未然に防ぐための予防的な活動です。最新の脅威情報の収集・分析、リスクアセスメントの実施、セキュリティポリシーの策定などを行います。
具体的には、インシデント対応手順の策定や定期的な訓練を実施し、実際の場面で迷わず動けるよう日ごろから準備しておくことが重要です。また、効果的な予防策を実施するためにも、他組織との情報共有も欠かせません。
インシデントへの事後対応
インシデント発生後の対応は、初動が早ければ早いほど被害の広がりを防ぎ、システムの復旧もスムーズに進みます。
事後対応では、インシデントの検知・分析、影響範囲の特定、封じ込め措置を実施します。原因を突き止めてシステムを正常な状態に戻し、再発防止策を策定することが大切です。対応過程で得られた知見は、今後の予防策強化に活用されます。
脆弱性管理
脆弱性管理は、システムやソフトウェアの脆弱性を定期的に発見・評価し、適切な対策を実施する活動です。脆弱性情報の収集、影響度の評価、パッチ適用の優先順位付けなどを行います。
効果的な脆弱性管理により、潜在的な攻撃経路を事前に塞ぎ、セキュリティインシデントの発生リスクを大幅に軽減できます。緊急度の高い脆弱性については、迅速な対応体制を整備することが重要です。
関連記事:脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?種類から実施方法まで解説
セキュリティ教育や強化
組織全体のセキュリティ意識向上のための教育・啓発活動も、CSIRTの欠かせない役割です。従業員向けの定期的な研修、最新の脅威情報の共有、セキュリティガイドラインの策定などを通じて、組織のセキュリティ文化を醸成します。
特にフィッシングメールやソーシャルエンジニアリングなど、人的要因による攻撃への対策として、実践的な教育プログラムや模擬攻撃訓練の実施が効果的です。
関連記事:セキュリティアウェアネスとは?必要性・教育内容・導入のポイントを解説
CSIRTを導入する流れ
CSIRTを導入する際は、以下の流れに沿って進めるとスムーズに行えます。
プロジェクトの立ち上げ
CSIRT導入の第一歩は、経営層の承認を得たプロジェクトの立ち上げです。プロジェクトチームの編成や予算の確保、スケジュールの策定を行います。経営層の支援があれば、全社的な協力も得やすくなります。
情報収集と課題の把握
自社のセキュリティ体制や過去のインシデントを調査し、現状の課題を整理します。業界動向や他社の事例も参考にしながら、自社に合ったCSIRTのあり方を検討しましょう。リスクアセスメントを行うことで、対応すべき優先課題や改善点が把握できます。
CSIRT構築の計画立案
情報収集と課題把握の結果をもとに、CSIRTの組織構成や役割分担、導入すべきツールなどを具体的に計画します。段階的な導入アプローチを採用するほか、柔軟に改善できる体制を意識することが大切です。
CSIRT構築
計画に沿って人員の配置やツールの導入を進め、連絡体制や対応手順を整備します。特に、想定されるインシデントごとの対応フローは、できるだけ具体的に定めておきましょう。関係部署との連携も事前の確認が欠かせません。
CSIRTの運用開始
運用が始まったら、小規模なインシデントや訓練を通じて、対応手順を検証・改善していきます。定期的な訓練により、実践的な対応力とチーム連携を強化します。
改善または再検討
運用後もCSIRTの活動を定期的に評価し、必要に応じて見直します。対応の速さや被害の抑制効果などを確認しながら、新たな脅威や組織の変化にも柔軟に対応できるよう体制をアップデートしましょう。
CSIRTを構築する際のポイント
CSIRTを構築する際は、以下のポイントを意識することが大切です。
経営層の理解を得る
CSIRTの成功には、経営層の理解と支援が不可欠です。セキュリティインシデントが事業に与える影響の大きさを具体的に示し、CSIRT構築の必要性を明確に説明します。
経営層に対しては、投資対効果を定量的に示すことが重要です。インシデント発生時の潜在的な損失額と、CSIRT構築による被害軽減効果を比較し、経営判断に必要な情報を提供します。
活動・責任範囲の明確化
CSIRTの活動範囲と各メンバーの責任を明確に定義することで、効率的で迅速な対応が可能になります。どのような種類のインシデントを対象とするか、どの段階から介入するかを具体的に決定します。
また、関係部署との役割分担を明確にし、重複や漏れがないように努めましょう。緊急時の意思決定権限についても事前に決めておくとスムーズな対応につながります。
他組織と連携・情報共有
CSIRTの効果を最大化するためには、他組織との連携と情報共有は欠かせません。業界団体や政府機関、セキュリティベンダーなどとの情報共有により、最新の脅威情報をすぐに把握できます。
また、同じ業界の企業とも連携し、共通の課題に協力して対応するのも効果的です。ただし、情報共有においては機密性の保持と適切な情報管理が重要であり、明確なルールと体制の整備が求められます。
関連記事:SOARとは?基礎知識やSIEMとの違い、導入ポイントについて解説
まとめ
CSIRTは、現代企業にとって不可欠なセキュリティ対応組織です。サイバー攻撃の高度化により、すべてのリスクを未然に防ぐことはもはや困難であり、インシデント発生後の迅速かつ的確な対応力が企業の存続を左右する時代となっています。
そのため、CSIRTの導入は単なる技術的対策にとどまらず、組織全体でセキュリティ意識を共有し、継続的に改善を図る仕組みとして位置づけられます。経営層の理解と支援を得た上で、計画的に導入・運用することが、組織のセキュリティレベルを大きく引き上げる鍵となるでしょう。
サイバー脅威が今後さらに進化する中で、CSIRTの整備は業種や規模を問わず、すべての企業にとって早急に取り組むべき重要な経営課題といえます。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
若園 直子
専門的な内容でも、読者にとって親しみやすく、実践につながる形で伝えることを大切にしています。