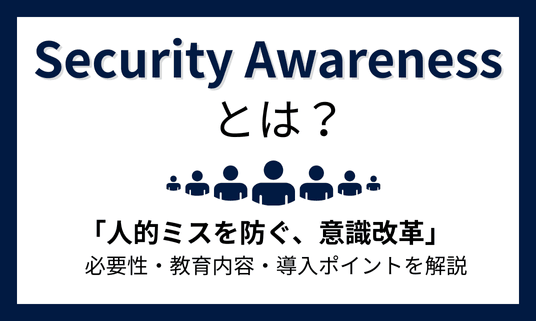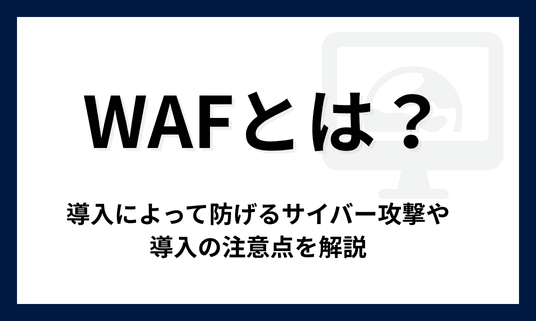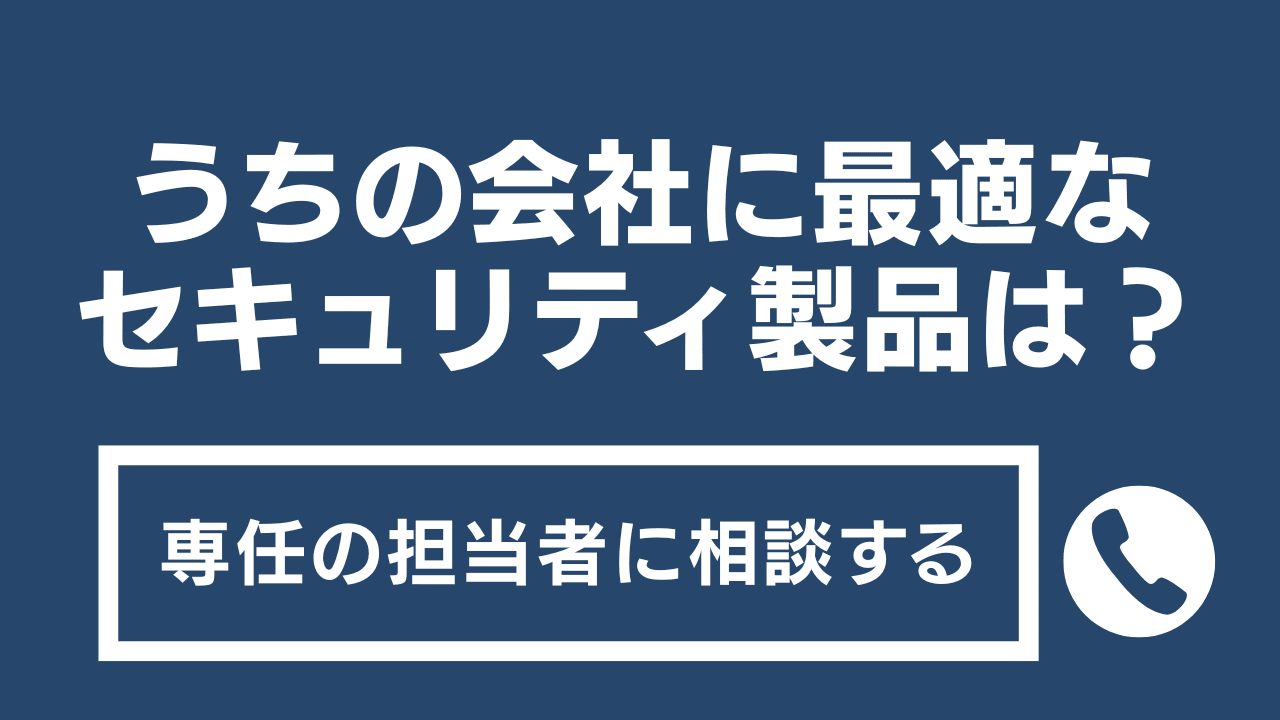2025.9.3
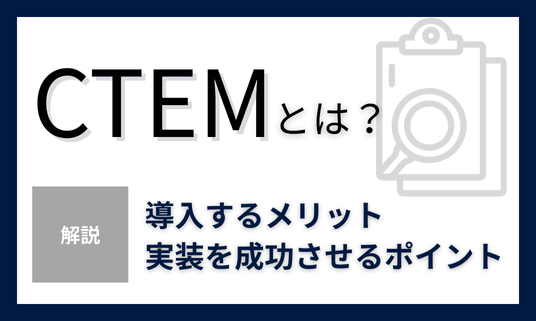
CTEM(Continuous Threat Exposure Management)とは、継続的にIT資産への脅威を洗い出し、リスクを評価・管理するためのサイバーセキュリティフレームワークです。
2022年にガートナーが提唱した概念で、セキュリティ対策を一過性のものではなく、組織全体で継続的に見直し・強化していく取り組みとして位置づけられています。
サイバー攻撃の手法は年々高度化し、個別の脆弱性を修正するだけでは、もはや十分な防御とは言えない時代になりました。全体としてのリスクを俯瞰し、優先順位をつけて対応する新たな視点が求められています。そこで注目されているのがCTEMです。
本記事では、CTEMの基礎知識から導入のメリット、実装成功ポイントまで解説します。
関連記事:サイバーセキュリティとは?サイバー攻撃の種類や代表的な対策方法を解説
CTEM(Continuous Threat Exposure Management)の基礎知識
まずCTEMとは何か、なぜ多くの企業が注目しているのかを解説します。
CTEMとは
CTEM(Continuous Threat Exposure Management)は、2022年にガートナー社が提唱した「継続的脅威エクスポージャー管理」のフレームワークです。企業が日々直面するさまざまな脅威を継続的に把握・評価し、リスクに基づいて優先順位をつけ、対応していくという包括的なアプローチを指します。
従来の脆弱性管理が、個々の技術的な弱点への対応にとどまっていたのに対し、CTEMはビジネス視点を重視し、「どの脅威が事業にとって本当に重要か」を判断基準に据えているのが大きな違いです。
最大の特徴は、リアクティブ(事後対応)からプロアクティブ(事前対応)への転換にあります。潜在的な脅威を早期に発見し、事前に対策を講じることで、組織への影響を最小限に抑えることが可能になります。
関連記事:脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?種類から実施方法まで解説
CTEMが注目される理由
CTEMが多くの企業から注目を集めている背景には、現代のセキュリティ環境における3つの大きな変化があります。
まず挙げられるのが、攻撃手法の高度化と自動化です。AI技術の進化により、攻撃の精度や速度が飛躍的に向上しており、単発的な脆弱性対応だけでは追いつけない状況が生まれています。従来のやり方では、潜在的な脅威を見落とすリスクが高まっているのです。
次に、クラウドサービスやIoT機器、テレワーク環境の普及により、企業が守るべきデジタル資産が急増している点も大きな要因です。攻撃対象が広がったことで、全体のセキュリティリスクを可視化し、体系的に把握・管理する必要性が高まっています。
さらに、すべての脅威に一律に対応するのではなく、事業への影響度を考慮して優先順位をつけることが求められるようになってきました。CTEMはこのような背景を受け、ビジネスリスクを基準にした柔軟かつ効率的な脅威管理を可能にするアプローチとして注目されています。
CTEMとASM(アタックサーフェス管理)の違い
ASM(Attack Surface Management)は、外部からの攻撃対象になり得るIT資産を発見し、把握・整理することに焦点を当てた管理手法です。主にインターネットに公開されているシステムやサービス、ドメイン、アプリケーションなどの攻撃の入口を洗い出し、セキュリティ上の不備や脆弱性がないかをチェックします。攻撃対象となりうる領域を減らすことがASMの主な目的です。
一方のCTEMはASMの可視化機能を土台に持ちつつ、その上で「発見→評価→優先付け→検証→対応」の一連のプロセスを継続的に回していく包括的なリスク管理フレームワークです。
| 比較項目 | ASM | CTEM |
|---|---|---|
| 主な目的 | 外部に晒された資産の特定と攻撃リスクの縮小 | 脅威の可視化から優先付け・対処までの継続的なサイクル |
| 対象範囲 | 主にインターネット経由でアクセス可能な外部資産 | 外部に加え、内部ネットワークやサプライチェーンなども含む全体資産 |
| アプローチ | 資産の把握と脆弱性の発見が中心 | 発見だけでなく、影響評価・対策の検証・改善まで一貫して実施 |
| 実施形態 | 定期的またはスポット的に実施されることが多い | 継続的な運用を前提とするプロセス |
ASMを含める形でCTEMが拡張された関係にあり、連携して活用することでセキュリティ対策をより効果的に推進できます。
CTEMの5つのプロセス
CTEMは以下5つのプロセスで構成され、これらが循環的に実行されることで継続的な脅威管理を実現します。
- スコープ定義(Scoping)
最初のステップでは、保護対象となる組織資産を明確に設定します。物理資産・デジタル資産・人的資産・無形資産といったあらゆる要素を洗い出し、それぞれの価値や事業への影響度を評価します。
加えて、クラウドサービスや外部ベンダー、パートナー企業といった外部依存関係も含めて、攻撃対象となりうる範囲を広く捉えることが重要です。資産ごとの重要度と相互依存関係を可視化することで、リスク管理の土台が整います。
- 発見(Discovery)
次に行うのが、脆弱性やリスクの発見です。自動スキャンや常時モニタリングに加え、脅威インテリジェンスやOSINT(オープンソース情報)、ダークウェブ監視など、多角的な手法を用いて新たな脅威の兆候を早期に察知します。
内部監査や第三者によるセキュリティ評価なども組み合わせることで、見落とされがちなリスクまで網羅的に把握できます。
- 優先順位付け(Prioritization)
発見された脅威の中から、対応すべき重要なものに優先順位をつけるプロセスです。技術的な脅威レベル(例:CVSSスコア)に加えて、事業への影響度や法令順守、顧客やブランドへの影響といったビジネス視点の要素を総合的に評価します。
- 検証(Validation)
特定された脅威が実際に攻撃可能かどうかを確認し、対策の有効性を評価するプロセスです。検証では、机上評価だけでなく、実際の攻撃シナリオを想定した検証を行い、理論的な脅威と実際のリスクとの違いを明確にします。
ペネトレーションテストでは、実際の攻撃手法を用いて脆弱性がどのように悪用されるかを検証し、現在の対策が実践的な攻撃に耐えられるかを評価します。想定外の経路や見落とされた抜け穴の有無も明らかになります。
- 動員(Mobilization)
最後に組織全体でのリスク対応体制を構築します。IT部門だけでなく、経営層や事業部門、法務など、すべての関係者が連携してリスク対応に取り組む体制の整備が必要です。
インシデント対応計画や復旧手順の策定、定期訓練、報告体制の整備を通じて、CTEMプロセス全体の実行力を高めます。
CTEM導入のメリット
CTEM導入によって得られるメリットは主に以下の3つです。
セキュリティ体制を強化できる
CTEMは、これまでの個別対応型セキュリティから脱却し、統合的かつ継続的な脅威管理体制を実現します。日々変化する攻撃手法にも、リアルタイムで対応できる柔軟性を備えた防御が可能になるでしょう。
本当に優先すべき脅威に集中して対策を講じられることで、セキュリティ投資の効果も最大化されます。
インシデント対応を効率化できる
CTEMでは、脅威の優先順位付けがあらかじめ行われているため、インシデント発生時には影響範囲を迅速に特定し、影響を最小限に抑えられます。
あらかじめ構築された部門横断の連携体制により、IT部門だけでなく事業部門や経営層とも連携しながら、ビジネス継続を重視したスムーズな対応がとれます。
リスク報告が容易になる
CTEMを活用したレポートやダッシュボードで、非技術系の関係者にもリスクの深刻度を伝えやすくなるでしょう。定期的なレポーティングと可視化された評価結果をもとに、経営層はタイムリーに戦略を見直し、必要な投資判断を下せます。
CTEM実装を成功させるポイント
CTEMの実装を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、組織的な課題にも対処する必要があります。ここでは、実装成功のための重要なポイントを3つに分けて説明します。
外部脅威への対応
外部脅威に対応するには、最新情報を継続的に収集し自社に反映する仕組みが必要です。脅威インテリジェンスの活用により、攻撃者の動向や新たな手口を早期に把握し、事前の対策につながります。
さらに、外部の専門機関やセキュリティベンダーとの連携体制を整えることで、社内リソースだけでは対応しきれない高度なリスクにも柔軟に対応できるようになります。
部門を横断した協力体制をつくる
CTEMはIT部門だけの取り組みではありません。事業部門・経営層・法務など多部門が連携する体制を整えることで、全社的なセキュリティ対応力が高まります。
各部門の役割や責任を明確にしたうえで、定期的な情報共有や訓練を実施し、CTEMに対する理解と主体的な協力を促す文化づくりが重要です。
適切なツールとプロセス選定
CTEMの効果を最大限に引き出すには、自社の規模や業種、既存システムとの相性を考慮したツール選びが不可欠です。
また、ツールの導入だけで終わらせず、それを有効に活用できるプロセス設計や継続的な改善サイクルの構築まで見据えることが、安定した運用と成果につながります。
まとめ
CTEMは見えにくいリスクを可視化し、優先順位をつけて対応まで一貫して行う新しいセキュリティの考え方です。サイバー攻撃がますます巧妙になる中で、守りを固めるには継続的な管理が欠かせません。
自社に合った形でCTEMの導入を進めていけば、限られたリソースでも十分に効果を発揮でき、将来のリスクにも備えられます。
CTEM導入ステップを参考に、自社の安全と信頼性を高めるためにぜひCTEMを活用してみましょう。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
野口 綾香
初心者の方にも理解しやすく、役立つ情報を発信することを大切にしています。