![]() コラム
コラム
BCP(事業継続計画)とは?
IT-BCPとの違いや策定の必要性と進め方を解説
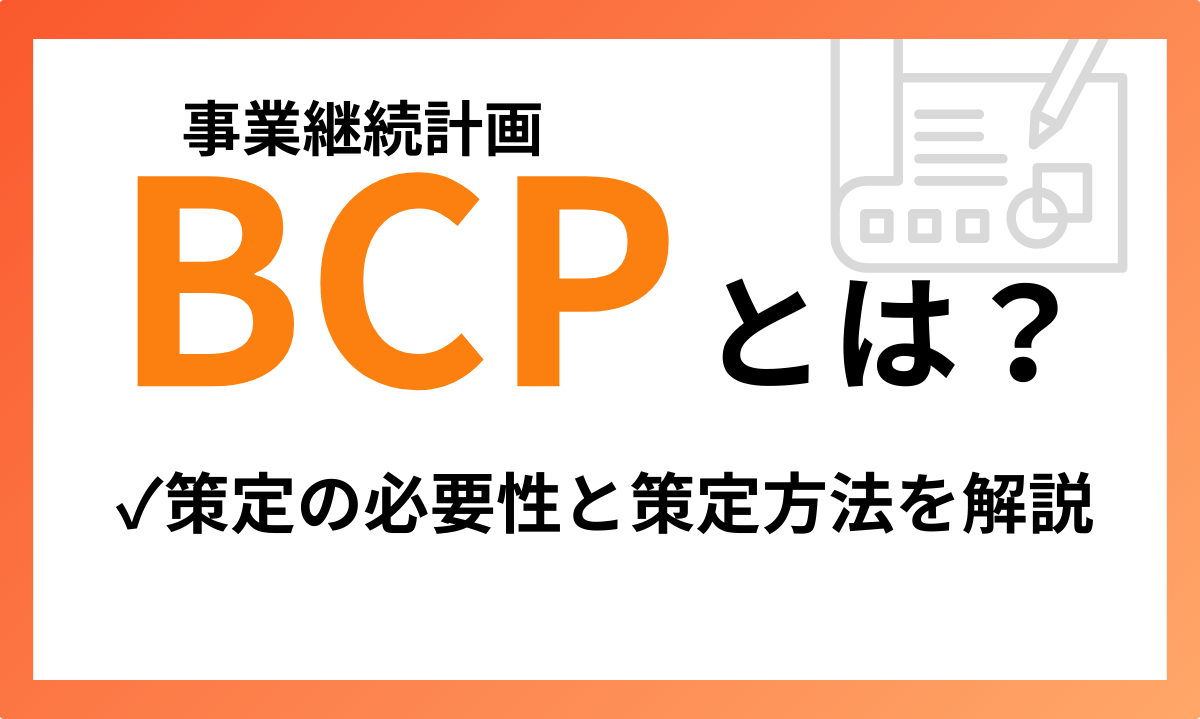
![]() 最終更新日:
最終更新日:
BCP(事業継続計画)は、自然災害や感染症の流行といった緊急事態が発生したときに、企業が重要業務を継続し、早期復旧を実現するための計画です。地震や台風などの災害リスクが高い日本では、BCPの策定は重要な経営課題といえます。
近年ではこれに加え、サイバー攻撃やシステム障害、通信断絶といったITリスクもBCPの重要な要素として位置付けられるようになっています。こうしたITリスクに備えるために策定されるのが「IT-BCP(IT事業継続計画)」です。IT-BCPはBCP全体の実効性を高める役割を担っており、企業のデジタル基盤を守る上で欠かせません。
この記事では、BCPの概要から策定のステップ、IT-BCPとの違いやITリスクに備えるための重要ポイントを解説します。
BCPとは?策定が求められる背景
まずBCPという言葉の意味と必要性が高まっている背景、策定の現状について解説します。
BCPの意味
BCPは、「Business Continuity Plan」の略称で、日本では「事業継続計画」と訳されています。自然災害や感染症の流行といった緊急事態に直面したとき、事業資産の損害を最小限に抑え、事業の継続・早期復旧を可能にするための計画です。
2005年に内閣府が公表した「事業継続ガイドライン」が発端となっている取り組みであり、長期に渡った計画策定が強く推奨されています。
BCPの必要性が高まる背景
2011年に発生した東日本大震災をはじめ、日本は自然災害のリスクを常に抱えています。さらに近年はサイバー攻撃やシステム障害といったITリスクが事業停止につながるケースも増加しています。
こうした状況に対応するためには、防災計画やセキュリティ対策だけでなく、組織全体の業務継続を支える包括的なBCPが必要です。
企業におけるBCPの策定状況
株式会社NTTデータ経営研究所が2024年に実施した調査によれば、「BCPを策定している」と回答した企業は47.0%、策定途中も含めると66.7%でした。
企業が3社あれば、そのうちの2社はBCPを策定している、もしくは策定途中である、という結果です。2018年に実施された同調査の値を上回って過去最高を記録しており、BCPに対する企業の関心度が高まっていることが読み取れます。
BCPが必要な理由と得られる効果
ここからは、企業にとってBCP策定が必要な理由と策定のメリットを見ていきましょう。
- 事業継続と早期復旧
緊急時に「何を優先すべきか」をあらかじめ定めておくことで、混乱を抑え、復旧までの時間を短縮できます。 - 顧客、取引先からの信頼維持
事業継続性を確保していることは、取引先や顧客からの信頼を得る上で重要です。 - 従業員の雇用維持と安全確保
従業員の安全を守ることはもちろん、企業が存続すれば雇用の維持にもつながります。 - 中核事業の可視化と生産性向上
優先度の高い事業や業務を整理する過程で、自社の強みや重要なプロセスが明確になり、平常時の生産性向上にも寄与します。 - 地域社会への貢献
経済活動を継続できる企業の存在は、地域の安定や復旧のスピードにも影響します。 - 法的義務、コンプライアンス対応
介護サービス事業所では2024年からBCPの策定が義務化され、災害拠点病院や金融機関、エネルギー事業者など一部業種でも策定が事実上必須とされています。その他の業種でも、策定していない場合は重大事故時にコンプライアンス面を問われるリスクが高まります。 - 危機管理意識の向上
策定プロセスそのものが従業員の危機意識を高める効果を持ちます。
IT-BCPとは?BCPとの違い
BCP全体の実効性を高めるためには、ITリスクを扱う「IT-BCP」を適切に組み込むことが欠かせません。ここではまず、IT-BCPの定義とBCPとの違いについて解説します。
IT-BCPの定義
近年、業務のデジタル化やクラウド活用が進む中で、ITシステムは企業活動の中枢となっています。
IT-BCP(Information Technology Business Continuity Plan)は、企業の情報システム、ネットワーク、通信インフラおよびそれらが扱うデータの継続性を確保することに特化したBCPです。サイバー攻撃やシステム障害、通信断絶などIT基盤全体に影響を及ぼすトラブルが発生した場合でも、業務を継続できる体制を整備することを目的としています。
例えば、ネットワークを二重化する、遠隔地へのデータバックアップを行うといった設備面の対策に加え、「多要素認証」や「ゼロトラストモデル」といったセキュリティの仕組みを整えることも重要です。
IT-BCPの考え方は、内閣官房 国家サイバー統括室が公表する「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン」にも示されています。ガイドラインでは、重要システムの特定、復旧目標(RTO・RPO)の設定、運用体制の構築、定期的な訓練や見直しの必要性が整理されており、民間企業にとっても参考となる内容です。
BCPとの違い
BCPは、自然災害や感染症などを含むあらゆる緊急事態に備えた企業全体の事業継続計画です。一方でIT-BCPは、BCPの一部でありながら、ITシステム、ネットワーク、情報資産といった“企業のデジタル基盤”を守ることに特化しています。
BCPが「全社的な事業継続のためのフレームワーク」であるのに対し、IT-BCPは「ITが停止したときに事業を止めないための具体策」にあたります。両者は密接に関係しており、IT-BCPが欠けるとBCPそのものが形骸化してしまう恐れがあるため、セットで策定・運用することが推奨されます。
IT-BCP策定で特に重要な4つの視点
IT-BCPを策定する際に重視すべきポイントを整理します。これは後述する「BCP策定の5つのステップ」の中でも意識して取り入れる必要があります。
- 重要システム・データの特定と重要度分析
ERP(企業資源計画)、受発注システム、顧客データベースなど、業務に不可欠なIT資産を特定し重要度を評価します。 - RTO・RPOの設定
- RTO(目標復旧時間):停止から何時間(何日)以内に復旧するか
- RPO(目標復旧時点):どの時点のデータまで復旧できるか
- 代替手段・冗長化とセキュリティ対策
クラウドや遠隔地データセンターの活用、ネットワークの二重化、多要素認証やゼロトラストモデルの導入など、セキュリティと可用性を両立させます。クラウドを利用する場合はSLA(サービス品質保証)や責任範囲も確認しましょう。これらの仕組みはIT-BCPの実効性を高め、事業停止リスクを軽減します。 - 運用手順書・訓練・見直し
緊急時対応フローを文書化し、定期的に訓練や見直しを行います。外部委託先も含めた実運用での動作確認が重要です。
BCP策定をスムーズに進めるための5つのステップ
IT-BCPはBCP全体の実効性を左右する重要な要素です。特にサイバー攻撃やシステム障害が事業停止に直結する現代では、IT-BCPをBCP全体の策定プロセスに組み込むことが不可欠です。
以下で紹介する「BCP策定の5つのステップ」では、各ステップでIT-BCPの観点をどう取り入れるかにも触れていきます。
BCPを策定する目的を明確にする
BCPを策定する際の最初のステップは、企業として「何を守るべきか」を明確にすることです。守るべき対象としては、従業員の安全、顧客や取引先との関係、企業の中核事業、ブランド価値などが挙げられます。ここで重要なのは、自然災害や感染症だけでなく、サイバー攻撃やシステム障害といったITリスクも対象に含めることです。目的を明文化することで、BCP全体の方向性が定まり、関係者全員が共通認識を持つことができます。特にITリスクを視野に入れなければ、IT-BCPの必要性も正しく認識されにくくなるため、この段階で対象をしっかりと整理しておきましょう。
中核事業とリスクを洗い出す
次のステップでは、自社の業務全体を棚卸しし、どの事業や業務が中核事業に当たるかを特定します。売上や顧客への影響が大きい業務、他の業務に依存されている業務、早期復旧が求められる業務を明らかにしていきます。中核事業を特定した後は、それらに影響を及ぼすリスクを網羅的に洗い出します。自然災害や感染症に加え、システム停止や通信断絶、サイバー攻撃といったITリスクも具体的に列挙することが大切です。IT-BCPはこのリスク整理を前提に具体的な対策を立てるため、この段階で漏れなくリスクを抽出しておくことが非常に重要です。
リスクに優先順位をつける
リスクを洗い出したら、それらに優先順位をつけます。すべてのリスクに対策を施すことは現実的ではないため、発生頻度や影響度といった観点から対応の優先度を決定します。この段階で、IT-BCP特有の指標であるRTO(目標復旧時間)とRPO(目標復旧時点)を設定すると効果的です。RTOは業務停止から何時間(何日)以内に復旧するかを示し、RPOはどの時点のデータまで復旧できるかを示します。優先順位を明確にすることで、限られたリソースをどのリスク対策に集中すべきかを判断でき、BCP全体の実効性が高まります。
具体的な対応策を決める
優先順位の高いリスクごとに、実行可能な対応策を決定します。緊急時に機能する体制を整えるため、指揮命令系統や責任者を明確にし、中核事業を復旧させるための手順書を作成します。このとき、BCP全体にIT-BCPの考え方を反映させることが重要です。例えば、「受発注システムを24時間以内に復旧する」という目標がある場合、ネットワークやシステムの冗長化、遠隔地バックアップの仕組み、さらに多要素認証やゼロトラストモデルといったセキュリティの仕組みを組み合わせて、対応策を具体的に設計します。
継続的に運用、見直しを行う
BCPは一度策定して終わりではなく、継続的に運用と見直しを行うことが求められます。定期的に訓練やシミュレーションを実施して、従業員全員に手順を周知し、実践の中で発見された課題を改善していきます。特にIT-BCPは、クラウドサービスやセキュリティ技術の進化に応じて復旧手順や対策を更新していくことが不可欠です。定期的なアップデートを行うことで、BCP全体の実効性を維持でき、有事の際にも確実に機能する体制を築けます。
総合セキュリティ対策なら
パロアルトネットワークス
企業にとっての脅威は、地震・台風などの自然災害だけではありません。システム障害やサイバー攻撃といった情報セキュリティ対策も、重要なリスク管理です。
パロアルトネットワークスは総合セキュリティ対策のスペシャリストとして、世界各地のステークホルダーから信頼を積み重ねています。「情報セキュリティ対策に課題を感じているけれど、自社の対応だけでは不安」といった悩みをお持ちの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
今回は、緊急時における企業の行動指針である「BCP」と、IT領域に特化した「IT-BCP」について解説しました。自然災害や感染症対策に加え、サイバー攻撃やシステム障害といったITリスクへの備えも不可欠です。
IT-BCPはBCP全体の実効性を高める重要な要素であり、情報システムやデータの復旧計画が組み込まれていなければ、有事に対応できない可能性があります。まだ策定していない、検討途中という場合は、BCPとIT-BCPをセットで策定・運用することをおすすめします。社内だけで対応が難しい場合は、セキュリティ対策や災害対策に精通した外部ベンダーに相談するのも有効です。自社の業務特性に合わせた実効性の高い計画を構築できるでしょう。

