![]() コラム
コラム
セキュリティインシデントとは?
発生した際の対応や防止策を解説
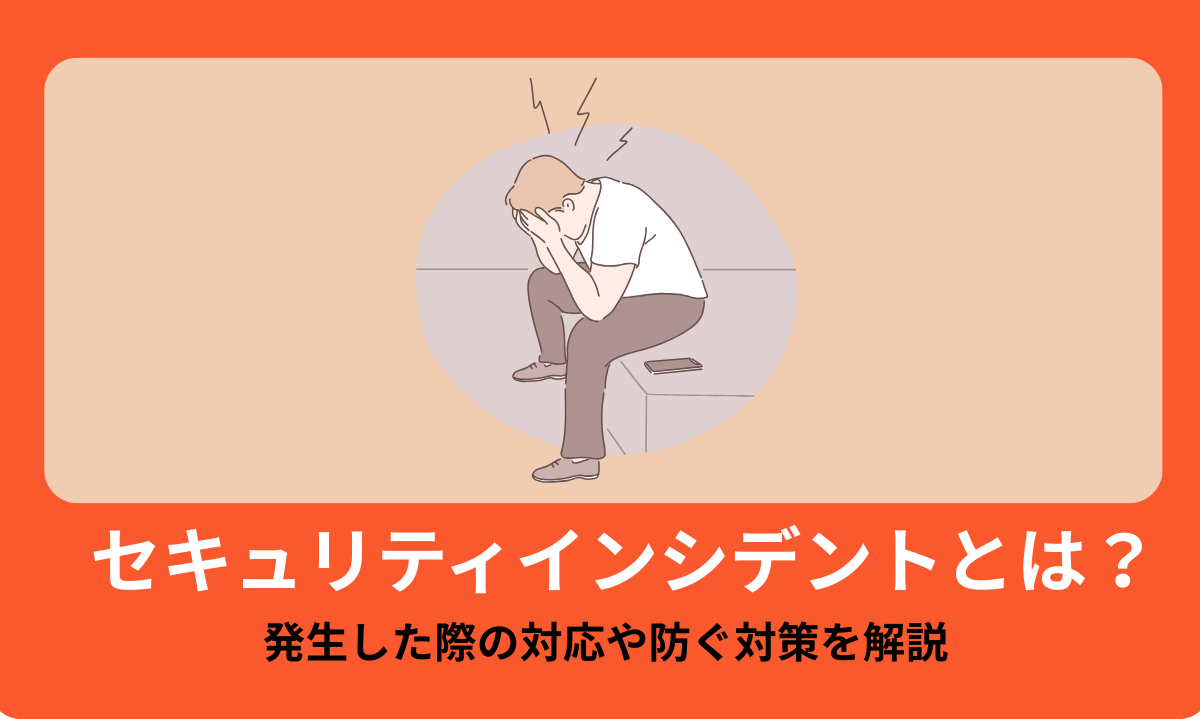
![]() 最終更新日:
最終更新日:
多要素認証(MFA:Multi-Factor セキュリティインシデントとは、企業や組織の情報セキュリティを脅かすあらゆる事象を指します。マルウェア感染や不正アクセス、情報漏洩、システム障害といったサイバー攻撃はもちろん、ヒューマンエラーや自然災害によるシステムトラブルなども含まれます。
本記事ではセキュリティインシデントの種類や原因、発生時の対応策、効果的な防止策について解説します。
セキュリティインシデントとは?
セキュリティインシデントとは、サイバー攻撃、不正アクセス、情報漏洩、システム障害など、企業や個人の情報セキュリティに影響を及ぼす事象を指します。
セキュリティインシデント対策の必要性
セキュリティインシデントが発生すると、企業は深刻な損失を被る可能性があります。
直接的な損失として不正送金や金銭要求、システム復旧や外部対応にかかるコストが挙げられます。ランサムウェアによる金銭被害もその一例です。
また、情報漏洩やサービス停止が報道やSNSで拡散されると企業の信用は大きく損なわれ、取引停止や顧客離れにつながります。売上機会の喪失や、BCP(事業継続計画)にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
こうしたリスクを最小限に抑えるには、迅速な初動対応、原因調査、再発防止策の徹底が不可欠です。
セキュリティインシデントの発生原因
セキュリティインシデントは、企業内部のヒューマンエラーや不正、外部からの攻撃、さらには自然災害やシステム障害など、さまざまな要因によって発生します。
内的要因
セキュリティインシデントの原因は、従業員の不注意や不正行為など、組織内部に起因する内的要因も多くのインシデントを引き起こしています。
独立行政法人 情報処理推進機構が発表した、情報セキュリティ10大脅威2024[組織編]では「内部不正による情報漏えい」が第3位、「不注意による情報漏えい」が第6位に挙げられており、内的要因が依然として大きなリスクであることが分かります。
内部要因の対策としては、従業員一人ひとりが情報管理の重要性を理解し適切な行動を取れるようにするための教育と、現場の実情に即したルールやガイドラインの整備が必要です。
外的要因
外的要因は企業の外部から行われるサイバー攻撃や不正アクセスなどの脅威を指します。これらの攻撃は、情報漏えいやシステム障害、業務停止といった深刻な被害をもたらす可能性があり、企業の信頼や事業継続に大きな影響を及ぼします。
代表的な攻撃手法としては、ランサムウェアやフィッシング、SQLインジェクション、不正アクセス、DDoS攻撃などが挙げられます。ランサムウェアでは企業のデータが暗号化され、復旧と引き換えに金銭を要求されるケースも珍しくありません。
こうした外的要因による被害を抑えるためには、OSやアプリケーションの最新化、アクセス権限の適正化、定期的な脆弱性診断に加え、従業員への継続的なセキュリティ教育と、強固な認証フローの整備が欠かせません。
災害・外部環境要因
人為的でない外的要因として、自然災害や予期しないシステム障害もセキュリティインシデントの原因となり得ます。地震による機器の故障や火災での設備破損、クラウドサービスや外部サーバーの障害によるデータ消失などがその一例です。
セキュリティインシデントの種類
セキュリティインシデントには、マルウェア感染、不正アクセス、DoS攻撃、フィッシング、ヒューマンエラーなど、さまざまな種類が存在します。
マルウェア感染
マルウェアとは、悪意のあるソフトウェアの総称で、コンピュータやネットワークに被害を与える目的で作られたプログラムを指します。代表的なものに自己増殖するウイルス、個人情報を盗むスパイウェア、システムを乗っ取るトロイの木馬、ファイルを暗号化して身代金を要求するランサムウェアなどがあります。中でも近年急増しているのがランサムウェアによる金銭要求です。
感染経路は多岐にわたり、不審なWebサイトへのアクセス、フィッシングメールの添付ファイルの開封、スパムメール経由のマルウェア拡散などが一般的です。感染済みのUSBメモリや外部記憶媒体を通じて社内ネットワークに拡大するケースも見られます。
不正アクセス
不正アクセスとは、本来アクセス権限を持たない第三者がサーバやシステム内部に無断で侵入する行為を指します。主な手口としては、OSやソフトウェアの脆弱性を突いた侵入、ログインIDやパスワードの不正取得、ブルートフォース攻撃などです。
不正アクセスが成功すると機密情報や個人データの漏洩、Webサイトの改ざん、マルウェアの仕込み、さらにはデータの削除や書き換えといった深刻な被害につながる恐れがあります。
DoS攻撃
DoS攻撃とは、特定のサーバーやWebサイトに大量のリクエストを送信し、システムに過剰な負荷をかけてサービスを停止させる攻撃です。アクセス集中によりリソースが枯渇し、正規ユーザーが利用できなくなる状況を引き起こします。
攻撃の目的は、競合サイトへの妨害、金銭目的の脅迫、特定コンテンツへの抗議などさまざまです。被害を受けるとWebサイトが停止し、機会損失・顧客離れ・企業の信頼低下などの影響を招きます。
ヒューマンエラー
ヒューマンエラーを原因とするセキュリティインシデントとして「メールの誤送信」や「記録媒体の持ち出し・紛失」などが挙げられます。
不注意によるヒューマンエラーは完全に防ぐことは難しいものの、誤送信防止機能の導入やクラウドサービスを活用することでPCの持ち出し自体を不要にするなどの対策でリスクを大幅に減らすことが可能です。
セキュリティインシデントが発生した際の対応
セキュリティインシデントが発生した際は、被害拡大を防いで信頼を維持するために、以下の3ステップで迅速かつ的確な対応を行う必要があります。
1. 検知・初動対応
インシデントが発覚したらただちに責任者へ報告し、関係機器やネットワークからの隔離、Webサイトの一時停止、ウイルス駆除などの対応を行います。
外部からの通報が発端の場合は、通報者情報を正確に記録しておくことが重要です。あらかじめ、対応フローと担当責任者・権限を明確にしておくことで、迅速な初動対応につながります。
2. 調査・報告・公表
初動対応後は、5W1H(いつ・誰が・どこで・何を・なぜ・どうした)を軸に事実関係と被害状況を調査します。システムログや端末ログの収集・保全を行い、EDRやSyslogなどを活用し、ログを外部に保存することも有効です。
調査結果がまとまり次第、社内外の関係者に状況を報告し、必要に応じて警察などへの届け出を行います。公表のタイミング、媒体選定は被害拡大のリスクや影響度を踏まえて慎重に判断しましょう。
3. 復旧・再発防止
報告を終えたら、速やかに相談窓口を設け、二次被害や追加報告に対応できる体制を整えます。
その後再発防止策を実施し、停止していたシステムやサービスを安全性を確認しながら復旧させます。
セキュリティインシデントを防ぐ対策
セキュリティインシデントを防ぐには、以下の対策が重要です。
自社の情報資産を把握する
情報資産の正確な把握と継続的な管理は、セキュリティインシデントの防止に直結します。端末やアカウント、ソフトウェア、クラウドサービスなど、業務に使われる情報資産は年々多様化・増加しており、管理が追いつかないことで脆弱性が放置されるリスクも高まります。
特に把握できていない端末や不要アカウント、更新されていないソフトウェアなどは攻撃者にとって格好の標的です。
こうしたリスクを抑えるには、手動管理に頼らずIT資産管理ツールの導入が有効でしょう。ベンダーが公開するアップデートや脆弱性情報を定期的にチェックし、必要なパッチを速やかに適用する仕組みを整えることが、実効性ある対策です。
社内のセキュリティ体制を整備する
セキュリティインシデントの発生リスクを低減するためには、インシデントレスポンス体制の構築が重要です。経済産業省は、以下の3つのステップを推進しています。
- セキュリティリスクを把握し、低減タスクを明確化
- 専門的知識を持つ「セキュリティ統括機能」を設置し、経営層の意思決定をサポート
- タスクを部署に割り当て、連携して実施
実際の事象を想定した訓練と教育を定期的に実施することで、インシデント発生時の迅速かつ効果的な対応が可能となります。また、対応手順や報告方法を明確に一覧化しておくことで、緊急時の行動を迅速に取れるようにし、被害拡大を防ぐための準備を整えることが重要と言えるでしょう。
研修や従業員教育でリテラシーを高める
セキュリティインシデントの一部は、従業員のヒューマンエラーや内部不正によるものであるため、社内ルールを明確にし従業員に遵守させることが必要です。
従業員がセキュリティインシデントの意味や対策を理解していなければ、適切な対応ができません。研修や訓練を通じて、従業員のリテラシーを高める取り組みが重要です。
OSやソフトウェアは常に最新の状態に保つ
OSやソフトウェアは、常に最新の状態を保つことが重要です。
古いソフトウェアやハードウェアを使用していると、攻撃の対象となりやすくなるため、こまめなアップデートや定期的な設備更新により、常に最新の状態で運用するようにしましょう。
セキュリティ対策ツールを導入する
安全性を強化するために、適切なセキュリティツールを導入することが重要です。以下の表にまとめたツールは、システムやネットワークの保護に役立ちます。
| ツール | 概要 |
|---|---|
| ウイルス対策ソフト | コンピュータウイルスを検知し、排除する |
| 脆弱性診断ツール | システムやアプリケーション内の脆弱性を特定する |
| ファイアウォール | 送信元と受信先に応じて、通信を許可するかを制御する |
| IDS/IPS | ネットワークやサーバでの異常な通信を検知し、防御する |
| WAF | Webアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃を防ぐ |
これらのツールを導入することで、異常を早期に発見でき、被害の拡大を防ぐ可能性が高まります。
総合セキュリティ対策なら
パロアルトネットワークス
セキュリティインシデントを防ぐためには、自社のIT資産管理や従業員教育、ソフトウェアのアップデートなどが重要です。
特にヒューマンエラーや外部攻撃に備え、適切な対策ツールの導入と対応体制を整えることが効果的です。定期的な研修や脆弱性の把握を行い、万一の際も迅速に対応できる準備を整えて、リスクを低減しましょう。
パロアルトネットワークスは、世界中の多様な組織のサイバーセキュリティパートナーとして信頼と実績を重ねています。総合セキュリティ対策を検討中の企業様は、ぜひパロアルトネットワークスまでお気軽にご相談ください。

