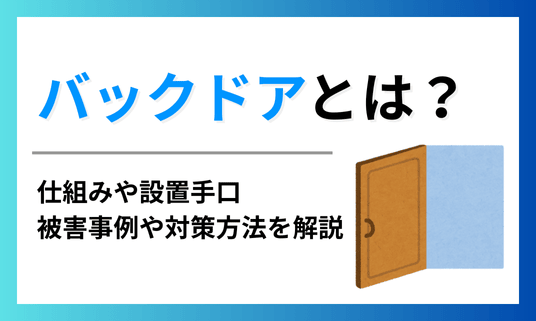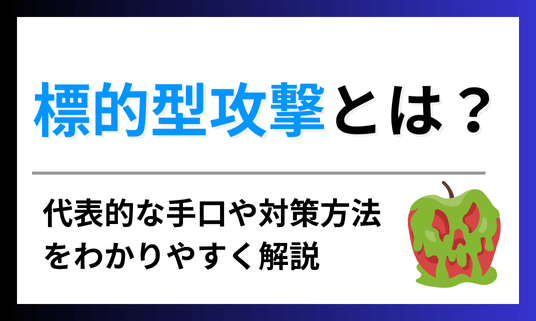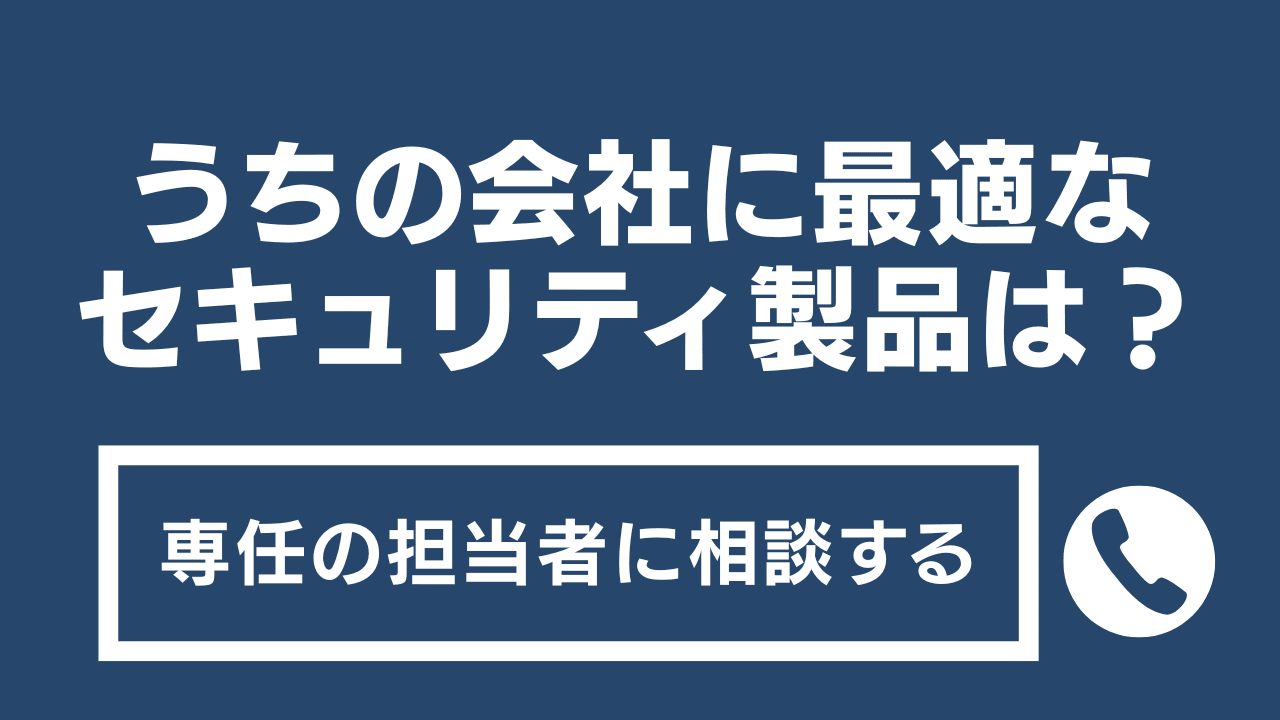2025.9.30

スパイウェアとは、ユーザーに気づかれないままデバイスに入り込み、個人情報や利用履歴を外部へ送信するプログラムです。IDやパスワード、クレジットカード情報など重要なデータが盗まれる危険がある一方で、中にはユーザー同意を得て利用されるケースも存在します。
本記事ではスパイウェアについて、コンピューターウイルスとの違いや主な感染経路、想定される被害などを解説します。
スパイウェアとは
スパイウェアとは、ユーザーの許可なくパソコンに侵入し、個人情報や行動履歴を外部へ送信するプログラムのことです。コンピューターウイルスのように悪質な印象を持たれがちですが、すべてが有害ではありません。
たとえばWebサイトの閲覧履歴や購入履歴を収集し、ユーザーの興味に合わせて広告を表示するといったマーケティング手法にも利用されています。
その一方で、ID・パスワードやクレジットカード情報といった重要データを盗み出す悪質なスパイウェアも存在します。気づかないうちに情報を送信され、金銭的被害に直結するケースも多いため、便利さの裏に潜むリスクを理解しておくことが重要です。
スパイウェアとコンピューターウイルスの違い
スパイウェアの厄介な点は、一目でわかるような異常が起きず、ユーザーが気づかないうちに情報が外部へ送信されてしまうことです。
コンピューターウイルスの多くは、パソコンに感染すると「パソコンを起動できない」「ファイルを削除される」といった異常が目に見える形で起こります。
これに対し、スパイウェアは「スパイ」という名称のとおり、ユーザーに気づかれないようひっそりと活動します。一見するとパソコンが通常どおり動作しているように見えるため、被害に気づきにくい点に注意が必要です。
スパイウェアの種類
スパイウェアは便利なものから悪質なものまで、さまざまな種類があります。代表的なものは以下5つです。
アドウェア
アドウェアとは、ユーザーに広告を表示することを目的としたプログラムです。Webサイト閲覧中や作業中にポップアップなどで広告を表示し、パソコン操作を阻害する動きをします。
無料ソフトウェアやサービスを利用する際、同時にインストールされることが多く、なかには悪質なものもあるため注意が必要です。
トラッキングクッキー
トラッキングクッキーとは、Webサイトの閲覧やサイト内での行動を追跡するために使用されるプログラムです。企業やサービスのマーケティングで用いられる「Cookie(クッキー)」とは異なり、トラッキングクッキーはユーザーの同意なく情報を収集します。
キーロガー
キーロガーとは、閲覧ページの情報や、パソコンで入力されたキーボードの操作内容を記録し、外部へ送信するソフトウェアです。ID・パスワードやクレジットカード情報など、機密性の高い情報を盗み出す目的で悪用されます。
ブラウザハイジャッカー
ブラウザハイジャッカーとは、Webブラウザの設定を勝手に変更するプログラムです。Webブラウザの起動時に有害サイトを表示させたり、ツールバーをインストールしたりして、ブラウザのセキュリティレベルを低下させます。
リモートアクセスツール
リモートアクセスツールとは、パソコンを遠隔操作するためのプログラムです。これ自体は悪いものではなく、初心者ユーザーの設定サポートのために活用されることもあります。
しかし、攻撃者に悪用されるケースもあるため、スパイウェアのひとつとして扱われています。
スパイウェアの主な感染経路
スパイウェアの感染経路はさまざまですが、主に以下のようなケースが考えられるでしょう。
フリーソフト
無料のソフトウェアにスパイウェアが仕込まれており、ソフトウェアと一緒にインストールされてしまうケースです。なかには、ユーザーに外部への情報送信許可を取るソフトウェアもありますが、ユーザーが内容をよく読まずに同意してしまう場合もあります。
不審なメール
メールの添付ファイルやURLをクリックさせ、スパイウェアに感染させるパターンです。実在する企業やサービスになりすまし、ユーザーの警戒心を解く「フィッシングメール」の手口がよく使われます。
偽警告
「お使いのパソコンはウイルスに感染しました」など偽のポップアップを表示させる手口です。ポップアップに驚きクリックすると、スパイウェアに感染し個人情報を抜き取られてしまいます。
不正なWebサイト
スパイウェアが仕込まれたWebサイトを閲覧することで感染するパターンです。前述のとおり、メールやSMSなどから不正なWebサイトへ誘導するケースもあります。
外部デバイス
パソコンのUSBポートやCD/DVDドライブなどを通じてスパイウェアに感染するケースです。USBメモリや外付けのハードディスクなどにスパイウェアが仕込まれており、デバイスを接続するだけで侵入することもあります。
デバイスの遠隔操作
パソコンを遠隔操作され、スパイウェアをインストールされるパターンです。悪意ある第三者から「契約に必要」「副業に必要」などと嘘をつかれ、遠隔操作アプリをインストールさせられ、個人情報を抜き取られてしまうといったケースがあります。
内部犯行
組織の内部に悪意を持つ人間がいて、知らない間にスパイウェアを仕込んでいるパターンです。家庭内では、近親者によりスパイウェアを仕込まれるケースもあります。
スパイウェア感染による被害
ここからは、スパイウェア感染による具体的な被害について解説します。
個人情報が漏洩してしまう
Webサイトの閲覧履歴やパスワード、クレジットカード情報などの個人情報が漏えいする恐れがあります。また企業の機密情報を暗号化し、データ復元を条件に身代金を要求される事例も少なくありません。
関連記事:暗号化とは?種類や方法、メリット・デメリットについて紹介
不正ログインによる金銭的被害
盗んだID・パスワードを利用してアカウントに不正ログインされ、なりすましによる送金や商品購入などの金銭的被害が発生する場合があります。SNSのアカウントを乗っ取られ、不正な投稿やアカウント削除などの被害に遭うケースも存在します。
関連記事:パスワード管理の重要性とは?情報漏洩による損害とパスワードの安全な管理方法を解説
デバイスの動作停止や作業効率の低下
スパイウェアは密かに活動するため、感染後もパソコンは正常に動作しているように見えるケースが大半です。しかしスパイウェアが活動することで、デバイスの処理能力が低下したり、動作が停止したりする場合もあります。
ブラウザのセキュリティ設定変更
ブラウザのセキュリティ設定を勝手に変更され、危険なサイトにもアクセスできる状態になってしまうケースもあります。ブラウザの多くは、ユーザーが危険なサイトにアクセスする際に警告文が表示する仕組みになっており、ユーザーはWebサイトを安全に閲覧することが可能です。
しかしスパイウェアの設定変更によりブラウザの警告が機能しなくなると、不正なファイルをインストールさせられ次なる被害につながるリスクが高まります。
不要な広告が表示される
パソコン画面上にポップアップを表示し、不要な広告を閲覧させようとします。ポップアップが次々表示されるケースや、ポップアップを何度消しても広告が表示されるケースもあり、作業が阻害される原因となります。
スパイウェアに感染しないための対策
スパイウェアに感染しないためには、以下のような対策を講じることが大切です。
不審なメールや広告はクリックしない
不審なメールの添付ファイルや、悪質な広告をクリックすることで、スパイウェアに感染するケースがあるため、少しでも怪しいと感じた場合は安易にクリックしない習慣をつけることが大切です。
開発元や提供元が不明なソフトはダウンロードしない
無料で使えるソフトウェアやアプリのなかには、スパイウェアが仕込まれているものもあります。パソコンにソフトやアプリをダウンロードする際は、公式サイトや信頼できるプラットフォームから入手するよう心がけましょう。またダウンロードの際には、同意文に書かれている内容をしっかり確認してください。
OSやアプリケーションをアップデートしておく
スパイウェアは、OSやアプリケーションの脆弱性を突いて侵入することがあります。開発元はそれらの脆弱性に対処するため、定期的なアップデートを行っています。セキュリティリスクを低減するためには、OSやアプリケーションを常に最新状態にアップデートしておくことが大切です。
関連記事:脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?種類から実施方法まで解説
デバイスやブラウザのセキュリティ設定を強化する
外部デバイスからの感染を防ぐために、USBメモリや外付けハードディスクなどの利用を制限し、一定のルールを設けるのも有効です。ブラウザのセキュリティ設定を強化しておくと、不正サイトへのアクセスや不正ファイルのダウンロードを防ぎやすくなります。
EDRを導入する
EDRとは「Endpoint Detection and Response」の略称であり、パソコンやサーバーなどのエンドポイントセキュリティ対策を強化するソリューションです。万が一スパイウェアに侵入された場合でも、EDRがその活動を迅速に検知することで、被害を最小限に抑えられます。
関連記事:エンドポイントセキュリティとは?主要技術や対策、導入ポイントを解説
スパイウェアの駆除方法
スパイウェアへの感染が疑われる場合は、デバイスをネットワークから速やかに切断しましょう。スパイウェアが検出された場合は状況に応じて以下の方法を試し、被害拡大を食い止めましょう。
ウイルス対策ソフトを使用する
多くのウイルス対策ソフトには、スパイウェアの検知機能だけでなく駆除機能が備わっています。定期的なスキャンによりスパイウェアの感染を早期に発見でき、被害の抑制に役立ちます。
ソフトウェアの手動削除
パソコンにインストールされたファイルを確認し、スパイウェアを手動で駆除する方法です。インストールした覚えのないファイルから、スパイウェアと思われるものを削除します。
ただしユーザーにとっては馴染みのないファイルでも、実は稼働に不可欠なソフトウェアである可能性もあります。そのためスパイウェアの手動削除には、ファイルの重要度を判断できるだけの十分な知識が必要です。
パソコンの初期化・復元
セキュリティソフトの駆除に不安が残る場合は、パソコンの初期化・復元も検討しましょう。パソコンを工場出荷状態に戻すことで、スパイウェアを含むすべてのファイルが削除されます。
最も確実性の高い駆除方法ではありますが、大切なファイルを消失しないよう必要に応じてバックアップを取ることが大切です。
まとめ
スパイウェアとは、ユーザーに気づかれないように個人情報を外部に送信するプログラムです。企業のマーケティングにも用いられることがありますが、悪質なものはログイン情報やクレジットカード情報などを不正に取得し、金銭的被害を引き起こす危険性があります。
スパイウェアによる被害に遭わないためには、感染防止の水際対策が不可欠です。「不審なメールの添付ファイルは開かない」「OSのバージョンを最新に保つ」などの基本的な対策を講じつつ、ウイルス対策ソフトやEDRなども活用しましょう。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
若園 直子
専門的な内容でも、読者にとって親しみやすく、実践につながる形で伝えることを大切にしています。