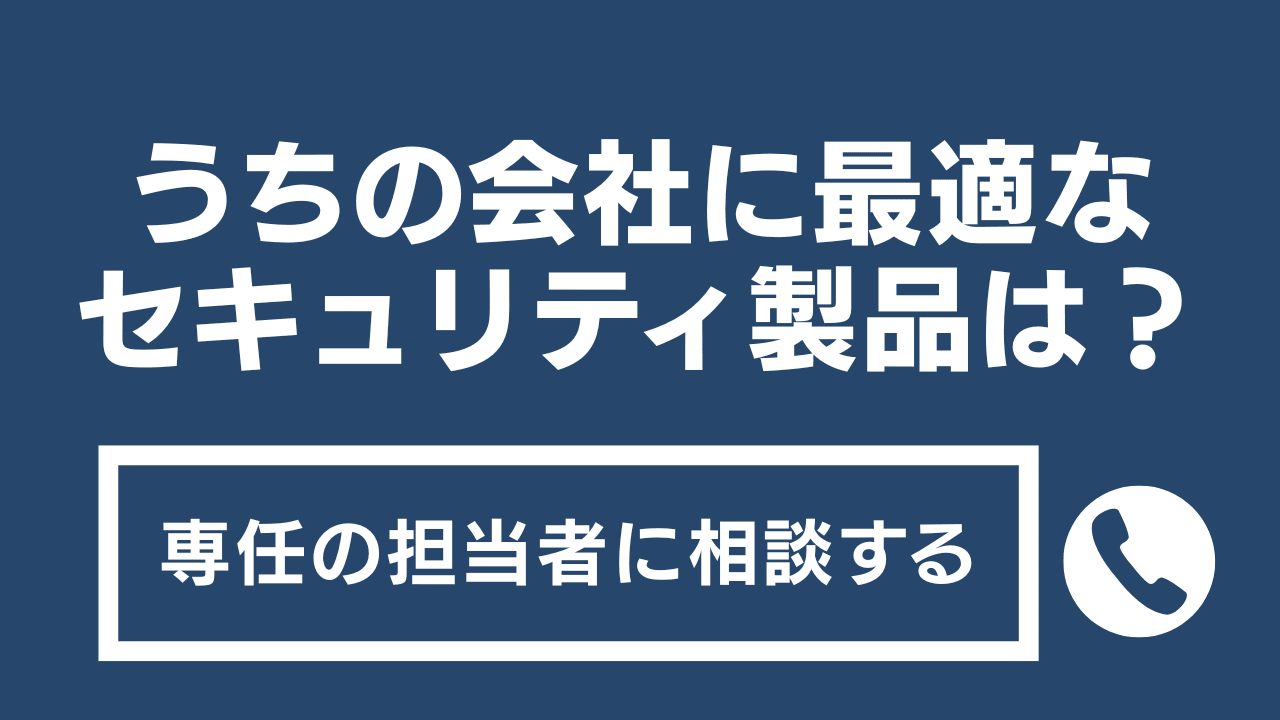2025.9.30
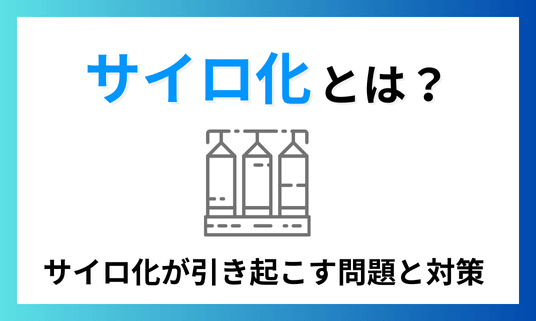
目次
サイロ化とは、部門ごとに情報やデータが閉じてしまい、全社で共有・活用できない状態を指します。
近年、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいますが、その障壁として「サイロ化」が顕在化しています。サイロ化が続けば、業務効率の低下や意思決定の遅延、さらにはセキュリティリスクの増大にもつながりかねません。
本記事では、サイロ化の原因から具体的な弊害、改善によるメリット、そして実践的な解消法までを詳しく解説します。
サイロ化とは?概要やDX阻害の要因になる理由
サイロ化とは、企業や組織内で部門ごと、あるいはシステムごとに情報やデータが孤立し、相互に連携・共有できない状態を指します。もともと「サイロ(silo)」とは、農産物や飼料を蓄える円筒形の貯蔵庫を意味し、各タンクが独立して中身が混ざらない構造から、孤立した組織やシステムのたとえとして使われるようになりました。
企業がサイロ化すると、必要な情報が他部署へ届かず、組織全体の協調が阻害されます。データを有効活用し、可能な限りサイロ化を可能な限り解消しなければ、DXを推進できずデジタル競争の敗者になりかねないと警鐘が鳴らされています。
サイロ化が起こる理由
サイロ化は偶発的に起こるのではなく、組織文化や構造上の問題、働き方の変化、システム戦略など複数の要因が絡み合って発生します。主な原因として以下が挙げられます。
縦割り組織の文化
機能別・職能別の縦割り組織は、各部門が独自のミッションや目標に集中しやすい傾向があります。これにより専門性の向上や部門内コミュニケーションの円滑化といったメリットがある一方で、他部門との関わりが希薄になることが懸念点です。
自部門の利益や目標を最優先する風土では、横断的な協力への関心が薄れ、他部署に無関心になったり批判的になったりする傾向が強まります。その結果、部署間の情報共有や協力体制が築かれにくくなり、組織のサイロ化を招いてしまうのです。
企業規模の拡大
社員数や事業拠点の増加もサイロ化を生みやすくします。小規模な組織では、メンバー全員の顔が見える範囲で働くため、日常的に偶発的な情報共有が起こりやすく、部署間の壁も感じにくいでしょう。
しかし、従業員が数百人、数千人規模になると、全員が同じ空間にいることは物理的に難しくなり、コミュニケーション相手が限定されがちです。さらに、効率化や専門性向上のため事業部制・職能別組織へ細分化が進むと、部門横断での関わり合いが減り、各部門内で閉じたコミュニケーションが増えていきます。
こうして部署間の距離が広がり、「自部門の業務だけに集中する」文化が形成され、サイロ化が深刻化する一因となります。
リモートワークの普及
近年普及したリモートワークも、サイロ化を加速させる一因です。オンライン会議やチャット中心の働き方では、オフィスの廊下ですれ違いざまに交わす雑談や何気ない対面コミュニケーションが激減します。
その結果、部署内外を問わず偶発的な情報交換や相談が起こりにくくなり、意思共有や信頼関係を築く機会が減少。こうした状況が続くと相互理解が進まず、組織内の一体感が弱まってサイロ化に拍車をかけてしまいます。
個別最適なシステム導入
各部門が自部門の業務に最適化されたアプリケーションやITツールを独自に選定・導入することも、サイロ化の要因です。部門ごとに異なるシステムを使い始めると、部署横断のシステム連携が考慮されていない状態になりやすく、データ形式の不統一やシステム間の非互換性が生じるからです。
その結果、別部署のシステム間でデータをやり取りするのに手間がかかり、リアルタイムな情報共有が困難になります。各部門ではそれぞれ使い勝手の良いシステムであっても、全社的にはかえって効率低下を招くかもしれません。
さらに、システムの種類やデータ量が増えるほど形式の違いによるデータ統合の難易度が上がり、サイロ化の解消は後からますます困難になっていきます。このように部門最適を優先したシステム導入は、全社的な情報共有を妨げ、サイロ化を深刻化させる原因となるでしょう。
サイロ化が引き起こす問題
サイロ化によって組織が直面する問題は多岐にわたります。では、それぞれの問題点について具体的に見ていきましょう。
業務効率・生産性の低下
サイロ化した状態では、部門ごとに分断されたシステムやデータのせいで、業務の二重・三重処理が発生しやすくなります。例えば、ある部署で作成した資料が他部署には共有されていない場合、別の部署で同じ資料をゼロから作り直してしまうような無駄が生じかねません。
また、部署間でデータ連携が取れないため、人手による情報集約や確認作業が頻発し、時間と労力を浪費します。各部門内では最適化され効率的に見える業務も、全社レベルでは非効率の塊となり、生産性が低下してしまいます。
サイロ化はリソースの重複利用やコミュニケーションコスト増大を招き、組織全体の業務効率を著しく悪化させるのです。
データ活用とDX推進の阻害
部門やシステムごとにデータが孤立していると、企業は自社に蓄積されたデータ資産を十分に活用できません。横断的なデータ分析や活用を行おうとしても、各システムのデータ形式が異なり統合が難しい、あるいはデータを提供してもらえないといった問題に直面し、時間と手間がかかります。
サイロ化した組織ではビッグデータの活用も妨げられ、AIによる高度な分析やデータドリブンな意思決定が困難になります。さらに、部門間のコミュニケーション不足でアイデアやナレッジが部門内に閉じ、新しい発想やイノベーションが生まれにくくなるという弊害もあるのです。
DX推進には全社的なデータ活用と部門を越えた協働が欠かせませんが、サイロ化された環境ではそれが実現できず、デジタル変革の足かせとなってしまいます。
意思決定の遅延
経営層が迅速かつ的確に意思決定を行うには、全社の正確な情報をタイムリーに把握することが必要です。しかしサイロ化によって情報収集に手間取る状況では、経営判断に必要なデータが各部門からすぐに集まらず、判断材料を揃えるだけで時間がかかってしまいます。
仮に集まったとしても、部門ごとにフォーマットや定義が異なるデータ同士の整合性を取る作業が発生し、さらに時間と労力を要します。こうした遅れが重なることで、市場や顧客の急激な変化に対する経営判断が後手に回り、スピード感を欠いた意思決定しかできなくなってしまうのです。
結果として機会損失を招いたり、競合他社に出遅れたりするリスクが高まり、企業の機敏な戦略遂行が阻害される可能性があります。
コスト増と冗長リソース
サイロ化はコスト面でも企業に負担を強いるでしょう。各部門がばらばらにシステムを導入・運用すると、同種のシステムやソフトウェアライセンスを重複して購入・維持する無駄が生じます。
また、全社でデータを集計・統合する際には、各部門から上がってきたデータの形式変換やクリーニング作業に多くの人件費が割かれます。さらに、サイロ化により複数の部署で同じような業務を重複して行うなど、貴重な人的リソースが有効活用されないまま浪費されるといった事態も起こりかねません。
このように、サイロ化は余計なコストと冗長なリソース消費を招き、企業経営の効率を下げる要因となってしまいます。
セキュリティ・ガバナンスの弱体化
組織内のデータや情報がサイロ化すると、セキュリティ管理やガバナンス(統制)の面でもリスクが高まります。部署ごとに別々のシステムでデータを管理していると、情報の不一致や抜け漏れが発生しやすく、統一的なアクセス制御や監査が行いにくくなるためです。
実際、Ivanti社の2025年サイバーセキュリティ調査によれば、回答企業の58%が「データのサイロ化」を実感し、62%がセキュリティ対応の遅れ、53%がセキュリティ体制の弱体化を感じていると報告されています。このように、サイロ化はセキュリティ対策の遅延や内部統制の形骸化を招き、企業の情報ガバナンスを低下させる大きな要因となりかねません。
サイロ化の解消は情報セキュリティ強化の観点からも急務です。一元的なデータ管理体制を敷き、アクセス権限の適切な設定や監査を行えるようにすることが求められています。
出典:2025年サイバーセキュリティ ステータスレポート|Ivanti![]()
関連記事:ゼロトラスト(ゼロトラストモデル)とは?重要視される理由と実装するための要素を解説
関連記事:SOC(Security Operations Center)とは?主な機能や役割、構築から運用体制まで解説
サイロ化を改善するメリット
サイロ化を解消し、組織全体でデータ・情報をスムーズに共有できるようにすると、多くのメリットが得られます。では、それぞれのメリットについて詳しく見てみましょう。
業務効率の向上
組織のサイロ化を解消すると、部門間の連携が取りやすくなり、重複作業や調整業務が減って業務フロー全体の効率が向上します。プロセスの標準化・統一によって部署間で何度も同じ情報をやり取りしたり、再作成したりする無駄がなくなり、情報探しや変換に費やす時間が減るでしょう。
さらに、コミュニケーションコストの面でもメリットがあります。サイロ化が解消されれば必要な人に必要な情報が行き渡りやすくなるため、細かな確認ミーティングの頻度が下がり、生産的な業務に集中できる時間が増えることにつながります。
コスト削減
サイロ化の改善は、コスト面でも大きな効果を発揮します。全社で情報基盤や主要システムを統合し、各部門の不要な個別システムを廃止・集約することで、システム開発・保守費やライセンス料の重複を削減できるでしょう。
統合プラットフォームを整備し一元管理に切り替えることで、ツールやソフトへの二重投資を避けられ、結果としてITコスト全体を大幅に圧縮できます。また、システム間のデータ連携にかかっていた手間や人的コストも、統合により不要となるため、人的リソースの節約にもつながります。
浮いたリソースや予算は、新たな価値創出につながるプロジェクトに振り向けることができ、経営資源の有効活用という意味でもサイロ化解消の効果は計り知れません。
迅速な経営判断
サイロ化を解消し、情報が社内でシームレスに共有される環境が整うと、経営のスピード感が飛躍的に高まります。各部門の最新データや報告がリアルタイムで経営層に届き、全社の状況を俯瞰した判断材料をすぐ入手できるようになるためです。
また、部門横断の情報連携がスムーズになれば、重要な経営会議のたびに各部署から情報をかき集める必要もなくなります。その結果、経営トップの素早い意思決定が実現し、市場変化や顧客ニーズへの迅速な対応が可能となるでしょう。
スピード経営の実現は競争優位性につながり、事業環境の変化に遅れず対応するうえで大きな武器となります。
DX推進の土台形成
サイロ化の解消は、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた盤石な土台を築きます。組織・システム・データのサイロ化を取り除き、部門横断でデータが利活用できる環境を整備することが、先進技術導入やビジネスモデル変革を加速させる前提条件です。
経済産業省も「企業文化・組織風土を変革し、急速な変化に対応できるようにすることがDX実現の基盤である」と指摘しています。まさにサイロ化解消による全社的な連携体制がその基盤にあたります。具体的には、全社で統一されたデータ基盤があることで、AIやBI、RPAなどの先進ツールを導入しやすくなるという利点があります。
このようにサイロ化を解消し、組織全体でデータ活用できる状態を作り上げることが、DXを全社的に加速させるための土台となるのです。
セキュリティ・ガバナンス強化
サイロ化の改善によって得られるメリットの一つに、情報セキュリティとガバナンス体制の強化があります。データを一元管理し、全社で統合的に扱うようにすれば、アクセス権限の統制やログ監査、不正検知などのセキュリティ対策を全社的に講じやすくなります。
各部署でバラバラに管理されていた時と比べ、情報の一貫性・整合性が保たれるため、異常値や不正の早期発見も可能です。例えば、社内データへのアクセスルールを一本化すれば、権限の過不足や認可されていないアクセスを厳格に管理でき、内部統制やコンプライアンス遵守を徹底しやすくなるでしょう。
さらに、組織全体で統一されたセキュリティポリシーを適用できるため、ガバナンス上の抜け漏れも防げます。サイロ化の解消は即ち情報ガバナンスの強化であり、信頼性の高いIT統制基盤を構築することにつながるのです。
関連記事:DLPとは?データ漏洩防止の仕組みから機能、導入効果を解説
サイロ化を改善する方法
サイロ化を解消するには、組織文化の改革から技術基盤の整備まで多角的なアプローチが必要です。では、サイロ化を改善する代表的な方法を紹介します。
経営層による方針明示
まず重要なのは、トップマネジメントが率先してサイロ化解消の方針を明確に打ち出すことです。経営層から部門横断の協力を促す強力なメッセージを発信し、全社共通の目標設定や情報共有の重要性を訴えることで、各部門の意識改革を促進できるでしょう。
具体的には、評価制度やKPIを見直し、「自部門の成果だけでなく他部門との協働の質」をマネージャー層の評価項目に組み込むといった施策が有効です。また、管理職に対して部門間協力への貢献を重視する評価体系を導入すれば、「自部署の目標最優先」から「全社最適を考える」意識へと行動原理が変わり、サイロ化の根本的な抑制につながります。
組織横断プロジェクト活用
部門間の壁を取り払う施策として有効なのが、組織横断的なプロジェクトチームの編成です。複数部署から人材を集めて共通のテーマに取り組むプロジェクトを立ち上げることで、普段接点のない部門同士が協働する機会を創出できます。
実際、「部門間の垣根を越えたプロジェクトチームの編成」や「ジョブローテーションの推進」は、サイロ化解消に有効な対策とされています。プロジェクト活動を通じてメンバー各自が他部署の業務内容や課題に触れ、相互理解が深まる効果が期待できるでしょう。
また、定期的な部門横断会議やワークショップの実施も、組織内のコラボレーション促進に役立ちます。現場の実務担当者やマネージャー同士が顔を合わせて課題を共有する場を設けることで、共通認識が醸成され、信頼関係の構築につながるでしょう。
共通プラットフォームと連携設計
サイロ化解消には、ITシステム面の統合と連携設計も欠かせません。企業全体で利用する共通のプラットフォームやデータベースを整備し、各部門が個別に使っている業務システムとの連携を図ることが重要です。
とはいえ、現実には企業規模が大きくなるほど、全てのシステムを一つに統一するのは難しいでしょう。それぞれの事業や職能に特化した機能は残さざるを得ません。そこで、全社的に集約すべきシステムと各部門で独自に運用すべきシステムを切り分けて定義したうえで、それらを円滑に連携できるように設計することが現実的なアプローチです。
具体的には、「各部門の個別システムが本当に必要か見極め、必要なものについては全社からその存在を把握できるようにし、他システムとAPI連携・データ統合が容易にできる状態にしておく」ことが重要になります。また、部門ごとのシステムであっても、定期的に全社データと同期・更新できるようインターフェースを整備しておけば、最新情報が行き渡り、リアルタイム連携が可能となります。
関連記事:バックドアとは?仕組みや設置手口、被害事例や対策方法を解説
コミュニケーション基盤の強化
サイロ化防止には、社内コミュニケーションの土台を強化することも有効です。情報共有やナレッジ交換を活性化させるための仕組みを整え、部署や拠点を越えた交流が生まれやすい環境を作りましょう。
具体的には、社内SNSやチャットツール、コラボレーション用のWiki、情報ポータルサイトなどを導入・活用して、社員が気軽に情報発信・質問できる場を増やすことが挙げられます。オンライン上の交流の場を意図的に用意することで、各部門の考え方や知見を発信・共有しやすくなり、相互理解の促進につながります。
さらに、オフィスにおいても部署を越えた人同士が交流しやすいレイアウトにする、定期的な全社集会や懇談の場を設けるなど、偶発的な情報交換が起こる機会を増やす工夫も効果的です。
教育と意識改革
人材教育や意識改革の取組みも、サイロ化改善には欠かせません。従業員一人ひとりが情報共有や部門協力の重要性を理解し、日々の業務で体現できるよう支援することが大切です。
具体策としては、社内研修やワークショップを通じた啓蒙活動があります。他部門の業務内容を学ぶ研修や、チームワーク強化のワークショップを開催することで、社員が自部署外の視野を広げるきっかけを提供できます。
お互いの業務をレビューし合ったり、異なる部署の人同士が協力して課題解決に当たる演習を行ったりすることで、組織全体としての一体感や共通目的意識が醸成されるでしょう。また、人事ローテーションで異部門を経験させることも視野を広げる教育施策となります。
上司やメンターによる部門を越えた視点での指導・フィードバックなども取り入れ、サイロ化に陥らない人材育成を推進していくことが望ましいでしょう。
関連記事:セキュリティアウェアネスとは?必要性・教育内容・導入のポイントを解説
まとめ
サイロ化は、情報やシステムの断絶によって企業の成長や競争力を阻害する重大な課題です。しかし、その原因を正しく理解し、組織的に対策を講じれば、時間はかかっても徐々に改善できます。
自社にサイロ化の兆候がないか定期的に点検し、もし問題が顕在化している場合は、できるところから少しずつでも解消に向けた行動を起こしましょう。全社一丸となってサイロの壁を崩し、風通しの良い会社を築くことが、これからのビジネス環境の激変にも柔軟に適応できる強い組織づくりにつながります。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
須賀田 淳
最新のトレンドや事例をリサーチ。専門的なテーマも、初めての方が理解しやすいように噛み砕いて発信しています。