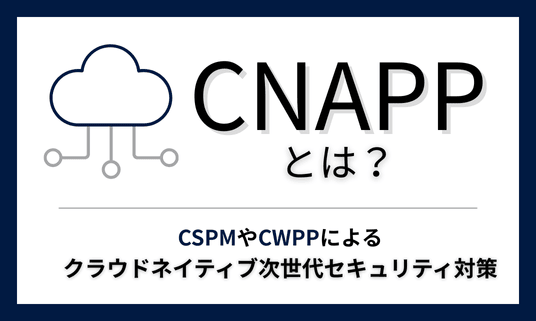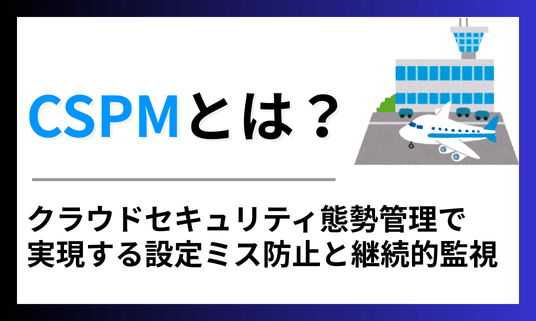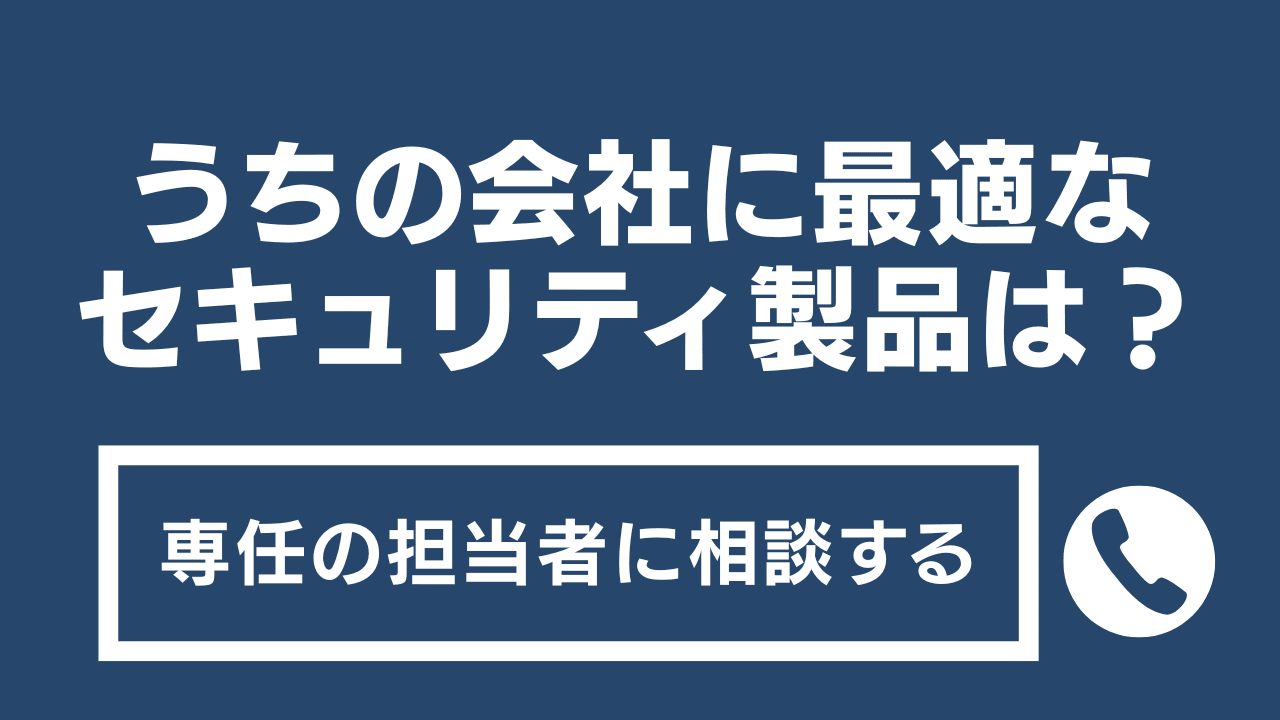2025.9.30
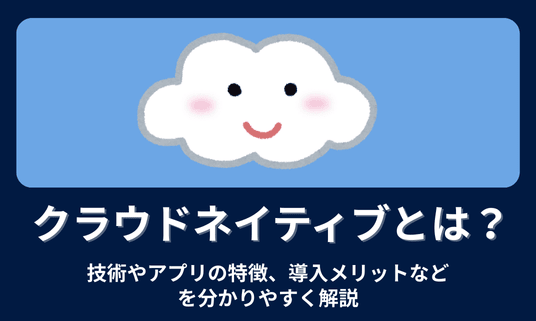
目次
クラウドネイティブとは、クラウドの特性を前提に設計・開発・運用することで、変化に強く、柔軟かつ効率的なシステムやアプリケーションを実現するアプローチです。
企業のデジタル変革が加速する中、従来のオンプレミス環境からクラウド環境への移行は単なるインフラの変更にとどまらず、アプリケーション開発・運用の根本的な変革を求めています。このような背景で注目を集めているのが「クラウドネイティブ」という概念です。
本記事では、クラウドネイティブの基本概念から実現技術、アプリケーションの特徴、導入効果、移行時の課題までわかりやすく解説します。
クラウドネイティブとは
クラウドネイティブとは、クラウドの利点を最大限に活用するためのシステム・アプリケーション設計のあり方を指します。単にアプリケーションをクラウド上で動かすのではなく、クラウド環境特有の特性(スケーラビリティ、可用性、弾力性)を前提とした設計・開発・運用アプローチです。
2015年に設立されたCNCF(Cloud Native Computing Foundation:クラウドネイティブ財団)による定義では、「クラウドネイティブ技術は、パブリック、プライベート、ハイブリッドクラウドなどの近代的で動的な環境において、スケーラブルなアプリケーションを構築・実行するための能力を組織にもたらす」とされています。
クラウドファーストとの違いについても理解しておきましょう。クラウドファーストは「SaaSを使うことをまず検討しよう」という戦略レベルの意思決定、クラウドネイティブは「クラウドを活かしたアーキテクチャで設計・開発しよう」という技術実装の指針です。
クラウドネイティブが重要な理由
現代の企業がクラウドネイティブを採用する理由は多岐にわたります。
会社のデジタル化(DX)を推進するため
デジタルトランスフォーメーションの実現には、迅速なアプリケーション開発とデプロイメントが不可欠です。クラウドネイティブアプローチにより、新機能の追加や市場の変化への対応を短期間で実現できます。
ビジネスのスピードアップと競争力強化
マイクロサービスアーキテクチャとDevOpsプラクティスにより、アプリケーションの開発・テスト・デプロイメントサイクルを大幅に短縮できます。これにより、競合他社より早く市場に新サービスを投入し、競争優位性を確保できるでしょう。
システムの拡張性や障害への強さを確保
クラウドネイティブアプリケーションは、トラフィック増加に応じた自動スケーリングと、部分的な障害が全体に波及しない障害耐性を備えています。これにより、安定したサービス提供と事業継続性を実現可能です。
関連記事:ゼロトラスト(ゼロトラストモデル)とは?重要視される理由と実装するための要素を解説
関連記事:SSEとは? SASEとの違いや導入メリット効果について解説
クラウドネイティブを実現する技術
クラウドネイティブを実現するための主な技術要素を解説します。
コンテナ
コンテナは従来の仮想技術より、設定ファイルが軽量で立ち上げも高速な仮想化技術です。DockerやContainerdなどのコンテナランタイムにより、アプリケーションとその依存関係を一つのパッケージとして管理できます。
コンテナの主な利点は、環境の一貫性です。開発環境、テスト環境、本番環境で同じコンテナイメージを使用することで、「開発環境では動くが、本番環境では動かない」という問題を解決できます。また、リソース使用効率も高く、仮想マシンと比較して起動時間が短いため、より多くのアプリケーションを同一ハードウェア上で実行できるでしょう。
マイクロサービス
マイクロサービスは従来の開発手法と異なり、各サービスが単一の機能を担うため、一部で障害が発生してもそのサービスだけを修正すれば済む技術パターンです。
従来のモノリシックアプリケーションでは、すべての機能が一つの巨大なシステムに統合されていました。しかし、マイクロサービスではユーザー管理、決済処理、在庫管理などの各機能を独立したサービスとして開発・運用します。これにより、機能ごとに異なる技術スタックを選択でき、開発チームの独立性も向上します。
サービスメッシュ
サービスメッシュは、コンテナ化したマイクロサービス間の通信を管理するための仕組みです。Istio、Linkerd、Consulなどのツールによりサービス間の通信制御、セキュリティ、可観測性を統一的に管理できます。
サービスメッシュにより、各マイクロサービスはビジネスロジックに集中できるほか、通信の暗号化、負荷分散、サーキットブレーカー、トレーシングなどの横断的関心事はインフラレイヤーで処理されます。
宣言型API
宣言型APIとは、「どのように実行するか」ではなく、「何を実現したいか」を伝えるAPIです。たとえばKubernetesでは、「Webサーバーを3台常に動かす」といった目標だけを設定すれば、あとはシステムが自動的にその状態を保ってくれるでしょう。また、サーバーが1台止まっても、自動で補充されるほか、常に目標通りの状態が保たれます。
イミュータブルインフラストラクチャ
イミュータブルインフラストラクチャとは、本番環境に直接変更を加えず、一度構築したインフラはそのまま使い、新しい変更は常に新しいバージョンを構築して入れ替えるという運用方針です。
これは「サーバーを大切に育てる」従来のペット型の運用から、「問題があれば丸ごと交換する」家畜型の運用へ切り替える考え方です。設定を変える必要があるときは、既存の環境に手を加えるのではなく、新たに変更を反映した構成を作って、古いものと置き換えます。これにより、設定のズレ(ドリフト)やリリース時のトラブルを大きく減らせるでしょう。
関連記事:SWGとは?セキュリティ機能や種類、CASBとの違いについて解説
関連記事:CASBとは?必要性や主な機能、導入方法やメリットを解説
クラウドネイティブアプリの特徴
クラウドネイティブアプリケーションには、従来のアプリケーションとは異なる特徴があり、その設計思想の1つとして「12-Factor Appの原則」が広く知られています。
12-Factor Appの原則
12-Factor Appは、クラウド環境に適したアプリケーションを構築するための12の基本原則をまとめたガイドラインのことです。以下に、主要な原則を紹介します。
| コード管理と外部サービスとの連携方法 | すべてのコードをバージョン管理システムで管理し、外部サービス(データベース、キューなど)は設定で切り替え可能にする |
| 設定情報と実際のプログラムを分ける | 機密情報や環境固有の設定は環境変数として外部化し、コードに埋め込まない |
| どこでも同じように動くプロセス設計 | ステートレスなプロセスとして設計し、どの環境でも同じように動作することを保証する |
変更しないインフラ
クラウドネイティブでは、一度作ったら変更せず、必要なら作り直す考え方を採用しています。
主要な特徴
| コードでインフラを管理する手法(IaC) | Infrastructure as Codeにより、インフラ構成をコードとして管理し、バージョン管理やレビューを可能にする |
| 設定がずれる問題を根本的に解決 | 手動での設定変更を禁止し、すべての変更をコード経由で実行することで、環境間の設定差異を防ぐ |
TerraformやAWS CloudFormationなどのツールにより、インフラ構成の再現性と一貫性を確保できます。
クラウドネイティブ導入で得られる効果
クラウドネイティブを取り入れることで、企業は多方面でのメリットを得ることができます。
障害時の影響を受けにくい
マイクロサービスアーキテクチャでは、各機能が独立して動くため、一つの不具合がシステム全体に影響するのを防げます。あるサービスに問題が起きても、他のサービスはそのまま動作し続けられるため、全体としての可用性が高まるでしょう。
さらに、複数のアベイラビリティゾーンやリージョンにサービスを分散して配置することで、大規模な障害にも耐えられる設計が可能です。自動復旧の仕組みも備えることで、万が一のトラブル時も迅速に元の状態へ戻せます。
コストを抑えられる
クラウドネイティブでは、アクセス量に応じて自動でリソース量を調整できるため、必要なときに必要な分だけ使うことができます。これにより、従来のようにピーク時に備えて過剰な設備を常時用意する必要がなくなるでしょう。
また、コンテナ技術を使えば同じサーバー上でより多くのアプリケーションを効率よく動かせるため、ハードウェア資源の無駄も減ります。さらに、DevOpsによる運用自動化で、管理にかかる人的コストも削減可能です。
アップデートや修正が簡単
マイクロサービスの構造により、個々のサービスを個別に更新できるため、システム全体を止めることなく機能追加やバグ修正が可能です。
CI/CDパイプライン(継続的インテグレーションと継続的デリバリー)によって、変更内容をスムーズに本番環境へ反映させられます。また、カナリアリリースやブルーグリーンデプロイといった手法を活用することで、リスクを抑えながら新バージョンを段階的に展開できます。
クラウドネイティブ移行の課題と対策
クラウドネイティブ導入には多くのメリットがありますが、同時に解決すべき課題も存在します。
組織と働き方の変化が必要
クラウドネイティブの導入は、単なる技術の変更ではなく、組織文化や働き方の転換も求められます。従来のような「開発」「運用」といった縦割り組織ではなく、DevOpsのように開発・運用が協力しながら進める横断的なチーム体制が必要になります。
ときには、開発とインフラの専門性を兼ね備えた「フルスタックエンジニア」のような、幅広い知識が求められることもあるでしょう。常に学び続け、新しいツールや仕組みに対応できる柔軟さが重要です。また、組織としては、失敗を許容しながら改善を繰り返す「挑戦できる風土」を育むことが求められます。
セキュリティとコンプライアンス対応
マイクロサービス化が進むと、通信の回数や経路が増えるため、セキュリティリスクも広がります。コンテナの安全性確保、サービス間通信の暗号化、ゼロトラスト(すべての通信を前提から信用しない)といった対策が欠かせません。
さらに、金融や医療など規制が厳しい業界では、コンプライアンス対応が特に重要です。たとえば「データがどこに保存されているか」を明確にすることや、「誰がいつアクセスしたか」を追跡できる監査ログの整備、細かなアクセス権限管理などが必要となります。
関連記事:暗号化とは?種類や方法、メリット・デメリットについて紹介
関連記事:DLPとは?データ漏洩防止の仕組みから機能、導入効果を解説
既存システムとの連携方法
多くの企業では、古いシステム(レガシー)と新しいクラウドネイティブな仕組みが混在する状況が一般的です。そうした中では一気にすべてを入れ替えるのではなく、既存のシステムと連携しながら段階的に移行する戦略が欠かせません。
APIゲートウェイやメッセージング基盤などを活用して、新旧システムがスムーズにやりとりできる環境を整える必要があります。たとえば「ストラングラーフィグパターン」という手法を使えば、古い機能を少しずつ新システムに移し替えていくことが可能です。こうすることで、ビジネスを止めることなく、移行のリスクも抑えられるでしょう。
まとめ
クラウドネイティブは、クラウドの特性を最大限に活かすための考え方と技術を組み合わせた、現代のIT基盤に欠かせないアプローチです。単にクラウドに移行するだけでなく、組織全体の開発・運用のあり方を見直すことで、真のデジタル変革を後押しします。
さらに、12-Factor Appの原則や「インフラは変更せずに作り直す」という考え方を取り入れることで、どの環境でも同じように安定して動作するアプリケーションを実現できます。結果として、障害に強く、コスト効率が高く、素早いアップデートが可能な運用体制が整うでしょう。
一方で、成功には組織文化の転換やセキュリティ・コンプライアンスへの新たな対応、レガシーシステムとの共存といった課題の克服が欠かせません。これらに対しては、段階的かつ計画的な移行戦略と、技術面と組織面の両方からのアプローチが重要です。
クラウドネイティブを正しく導入・活用することで、企業は変化に強く、競争力のあるデジタル基盤を構築し、持続的な成長につながるでしょう。
この記事の執筆者
SB C&S株式会社
ICT事業部
ネットワーク&セキュリティ推進本部
若園 直子
専門的な内容でも、読者にとって親しみやすく、実践につながる形で伝えることを大切にしています。