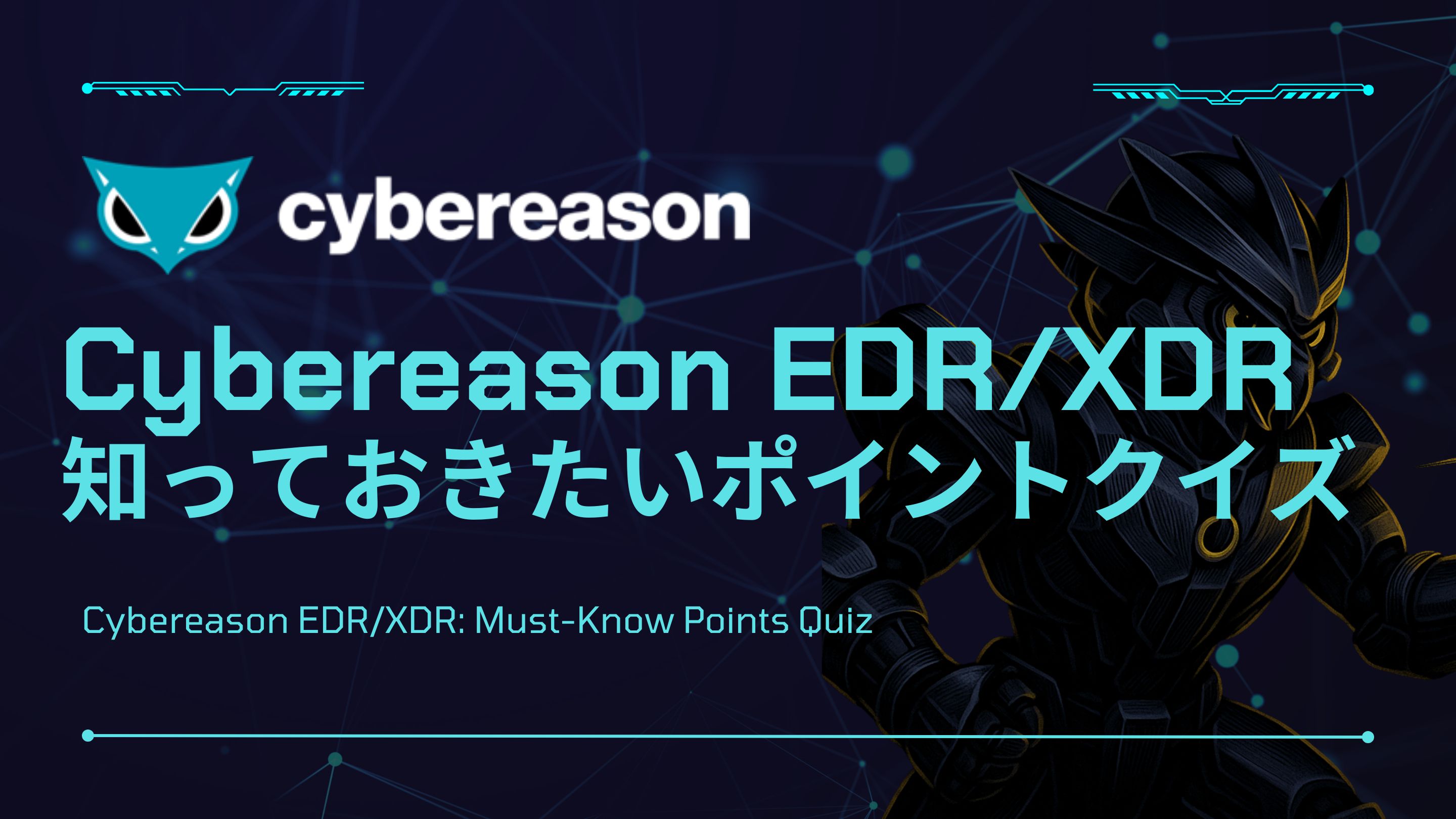
❏Cybereason EDR/XDRで知っておきたいコト!
こんにちは。SBC&S 橋本です。
Cybereason EDR/XDRの導入を検討される皆様とお話させて頂く機会をよく頂くのですが、その際に「これってどういうこと...?」とよくご質問頂く内容を本日はクイズ形式でご紹介させて頂きます!
これからCybereason EDR/XDRの導入を検討されている皆様も、すでに知っている皆様も是非チャレンジしてみてくださいね。
❏Q1. Cybereasonの「MalOp」とは何を指しますか?
A. サイバー攻撃で使用されたマルウェアファイルそのものの名称
B. ネットワーク侵入の瞬間から最終的な目的に至るまでの攻撃の一連の流れを一つの単位(オペレーション)として捉えたもの
C. センサーが検知したマルウェアプロセスのIDを表す社内コードネーム
==================================
正解:B
解説:MalOp(Malicious Operationの略)とは、Cybereason独自の概念で、サイバー攻撃の開始から完遂までの一連の悪意ある活動をひとまとめに表現したものです。
従来の製品が個々のイベントごとにアラートを出す「アラート中心」の考え方だったのに対し、MalOpでは「オペレーション中心」の考え方に移行しています。
例えば、ある端末への侵入(初期感染)から機密データの窃取やランサムウェアによる暗号化といった最終目的の達成まで、攻撃者の一連の動きを一本の筋道(ストーリー)として可視化するのがMalOpです。
そのため、分析者は攻撃の全貌を把握しやすく、点ではなく流れとして脅威に対応できるようになります。
❏Q2. CybereasonのMalOpアプローチは、従来のアラート中心の手法と比べてSOC(セキュリティ運用)業務にどんな利点をもたらしますか?
A. 関連するイベントを一つのシナリオに統合するため、アナリストが数多くのアラートに埋もれずに済む
B. 検知した全てのイベントについて逐一詳細なアラートを発行するため、見落としがなくなる
C. 脅威を検知すると即座に自動で無害化するため、アナリストが関与しなくてもよくなる
==================================
正解:A
解説:MalOpアプローチ最大の利点は、アラート疲れ(alert fatigue)の軽減です。
従来型のセキュリティ製品ではマルウェアの検知や疑わしい挙動ごとに個別のアラートが飛び交い、SOCアナリストは日に何千もの警告に対応しなければなりませんでした。
しかしCybereasonでは、関連する複数のイベントを自動で相関付けて一つのMalOp(攻撃シナリオ)にまとめ上げます。
結果として、「権限の不審な昇格」「新しいレジストリ変更」「怪しい通信」等、個別ではノイズとなりがちな何千ものイベントも、MalOpが統合された一つのシナリオとして浮かび上がらせてくれるのです。
そのためアナリストは本当に重要な脅威の全体像に集中でき、単発アラートの洪水に悩まされることが大幅に減少します。
これによりSOCの効率が上がり、見逃しのリスクも低減します。
❏Q3. Cybereason XDRが実現する「多層可視化」とは、簡単に言うとどういう意味でしょうか?
A. エンドポイントだけでなくネットワークやクラウド、ID管理システムなど複数の層のデータを収集・関連付けて、攻撃の全体像を一つのストーリーとして可視化すること
B. 社内の監視カメラ映像や物理センサーのデータまで含めてセキュリティ画面上に重ねて表示すること
C. パソコン画面のGUIを階層構造でズーム表示できる機能で、マルウェアを顕微鏡のように詳細観察できること
==================================
正解:A
解説: 「多層可視化」とは、その名の通りセキュリティ監視の対象範囲を多層(複数レイヤー)に広げて可視化することです。
Cybereason XDRでは、エンドポイントの振る舞い情報だけでなく、社内ネットワークのトラフィック、メールシステムのログ、クラウドサービスの利用ログ、ユーザー認証(アイデンティティ)情報など、企業IT環境全体から幅広くデータを収集します。
そしてそれらを一つのプラットフォーム上で相関分析することで、通常はバラバラに見える異なる層の出来事を統一された「攻撃のストーリー」として可視化します。
例えば「フィッシングメール(メール層)→端末マルウェア実行(エンドポイント層)→社内サーバー侵入(ネットワーク層)」という一連の攻撃も、XDRなら全ステップを繋げて表示できるわけです。
これにより、各レイヤーの点在するアラートを自分で突き合わせなくても、攻撃の全容を迅速に把握できるようになります。
また多層のデータをまとめて分析することで、根本原因となった脅威の特定や優先度付けも自動化されるため、担当者の負担軽減と効率化にもつながります。
❏Q4. Cybereason XDRは「オープンXDR」に分類されますが、これは何を意味していますか?
A. 単一ベンダー製品に依存せず、他社製セキュリティ製品のデータも柔軟に取り込んで連携できる開かれたXDRプラットフォームであること
B. 製品のソースコードが公開されており、コミュニティによって自由に改変・拡張できるXDRであること
C. 一度購入すれば全機能が無償で使い放題になる(オープン=無料の)XDRライセンス形態であること
==================================
正解:A
解説: XDRには大きく分けて、自社製品群だけで完結する「ネイティブXDR」と、複数ベンダーの製品と連携できる「オープンXDR」があります(さらに中間のハイブリッドXDRもあります)。
Cybereason XDRはオープンXDR型で、他社のセキュリティソリューションとも幅広くデータ連携可能なプラットフォームです。
例えば、エンドポイントセキュリティはCybereasonを使いつつ、ネットワークセキュリティ機器は別メーカー製、防御用のクラウドサービスや認証基盤はまた別メーカー製......といったマルチベンダー環境でも、Cybereason XDRはそれら様々な製品からログを集約して相関分析することができます。
単一ベンダーのみに統一しないとXDRの恩恵が受けられない、というロックイン状態にならないのが利点です。
オープンXDRであるCybereasonなら、既存のセキュリティ製品を活かしつつ、そのデータをまとめて一元管理・可視化できる柔軟性を持っているということです。
❏Q5.マルチOS環境で攻撃が発生した場合、Cybereasonはどのように対処しますか?
A. 攻撃者がWindowsからLinuxやmacOSへ横展開しても、各OSで発生したイベントを単一のMalOpに関連付けて分析し、一貫した視点で攻撃全体を可視化する
B. Windows向けの脅威だけを検知対象としており、LinuxやmacOSでの攻撃は基本的に検知・追跡できない
C. OSごとに別個の管理コンソールでモニタリングし、異なる形式のレポートがそれぞれ出力されるため分析者が統合的に判断する必要がある
==================================
正解:A
解説: CybereasonはWindows・Linux・macOSといった複数OS間にまたがる攻撃にも強いプラットフォームです。
仮に攻撃者が企業内でWindows端末を起点に侵入し、その後Linuxサーバーに移動(ラテラルムーブ)し、さらにはmacOSのマシンも悪用するといったケースでも、Cybereasonはそれらをバラバラの事件とは見なしません。
各OS上で発生した関連イベントを自動的に相関し、単一のMalOp(攻撃シナリオ)として統合表示するので、分析者は一つの連続したストーリーとして把握できます。
特に近年増えているmacOS標的の攻撃についても、Windows/Linux上の動きと同じMalOp技術で関連付けられ全体像を提供できるとされています。
このクロスOS対応により、「攻撃者がOSの違いをついて監視の目を逃れる」ことを防ぎ、ハイブリッドな環境下でも見落としのない包括的な検知・対応が可能です。
❏Q6.Cybereasonの検知アラートが「誤検知(フォルスアラーム)の少なさ」で評価されているのはなぜですか?
A. 複数のイベントを相関分析して文脈に沿った精密な検知を行うため、的外れな単発アラートが減り結果的に誤検知が少なくなる
B. AIが全てのアラートを自動精査して疑わしいもの以外はユーザーに表示しないため、表面的には誤検知が少なく見える
C. 検知エンジンのしきい値を極めて高く設定し、確実なマルウェア以外は一切アラートを出さないようにしているためである
==================================
正解:A
解説: Cybereasonの検知は精度の高さ、つまり誤検知の少なさでも知られています。その理由は、MalOpアプローチによってコンテキストを重視した関連イベントの統合検知をしているからです。
単一のイベントだけを見てアラートを出す場合、それが実害のない動きでも警告してしまうことがあります(=誤検知)。
しかしCybereasonでは端末やネットワーク上の複数の手がかりを付き合わせ、「これは明らかに攻撃の一部だ」と判断した場合に一つのMalOpとして検知します。
そのため根拠の薄いアラートが乱発されにくく、本当に重要な脅威だけを指摘する傾向になります。またAI駆動の分析によりノイズとなるイベントはある程度フィルタされ、代わりに「攻撃の全体像」としてまとまって提示されるので、アナリストから見ても誤検知が少なく扱いやすいのです。
実際にCybereasonはMITRE評価でも誤検知最小レベルの正確な検知を達成したと言及されており、信頼性の高いアラートだけを上げる設計が評価されています。
❏Q7. Cybereason EDR/XDRは市場でどのような評価・実績を持っていますか?
A. 日本国内におけるEDR導入シェアNo.1を誇り、第三者機関の評価テストでも最高水準の検知能力があると認められている
B. 欧米では評価が低いものの、日本独自の機能が評価され一部企業で試験的に導入され始めている段階である
C. まだ新興の製品で導入実績が非常に少なく、客観的な評価データもほとんど公開されていないのが実情である
==================================
正解:A
解説: CybereasonはEDR分野で世界的かつ国内的に高い評価と実績を持つ製品です。日本では2015年頃からいち早く市場に浸透し、国内シェアNo.1のEDRソリューションとも言われています (※調査会社による導入社数ベース等)。
また、第三者機関が実施する評価(例えば前述のMITRE ATT&CK評価や各種比較テスト)においても、Cybereasonは毎回トップクラスの結果を残しています。
実際、「第三者機関で最高評価を獲得し、日本国内シェアNo.1のEDR検知能力が基盤」と公式にも謳われており、その検知力・可視化能力には定評があります。
加えて導入企業の規模・業種も幅広く、金融機関や製造業、大手ゲーム会社、官公庁など数多くの組織で採用され実績を重ねています。
これらの事実から、Cybereason EDR/XDRは市場で信頼されリーダー的存在となっていると言えるでしょう。
❏Q8. Cybereasonの「攻撃ストーリー可視化」機能の強みは何でしょうか?
A. 攻撃経路をグラフ構造で表示し、感染源から被害拡大までを直感的に把握できる
B. 発生した全てのイベントを時系列のリストに並べるだけで詳細調査はアナリスト任せにする
C. 攻撃者が書いたコードを逆コンパイルし自動で解説する
==================================
正解:A
解説: Cybereasonは攻撃の流れを「ストーリー」として可視化する独自の機能を持っています。
これにより、どの端末から侵入し、どのユーザーアカウントが悪用され、どのサーバーへ横展開したのかが一目で分かります。単なる時系列ログではなくグラフィカルなマップ表示を採用しているため、専門知識が浅いエンジニアでも直感的に「攻撃の全貌」を把握できます。これは「点」ではなく「流れ」で脅威を理解するCybereasonならではの特徴です。
❏Q9. Cybereasonが提供する「MDR(Managed Detection & Response)」サービスの役割はどれでしょうか?
A. 専門アナリストが24時間体制で監視・分析を代行し、脅威が検出された場合には調査・対応をサポートする
B. ソフトウェアの脆弱性を自動的に修正するパッチ配布サービス
C. 社内のセキュリティ教育をオンライン研修で提供するサービス
==================================
正解:A
解説: CybereasonのMDRサービスでは、グローバル経験豊富なアナリストが顧客環境を24/7で監視・分析します。
MalOpを検知した際には、攻撃の深刻度評価や対応アクションの助言も提供してくれるため、専門のSOCを持たない企業でも高度な防御を享受できます。特に、日本国内では日本語対応可能なアナリストチームも存在し、運用負担の軽減に大きく貢献します。
クイズ形式でご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
答え合わせを通じて「なるほど!」と思うところや「意外と知らなかった」と感じる部分もあったかもしれません。
ここまでご紹介してきたように、Cybereasonは従来の「アラートの洪水」に悩まされるセキュリティ対策とは一線を画し「攻撃全体をストーリーとして可視化する」という独自の強みを持っています。複数のイベントを関連付けて理解できるからこそ、誤検知が少なく、SOC業務の効率化にもつながりますね。
オープンXDRとして多様な製品と連携できる柔軟性や、マルチOS対応でハイブリッド環境でも包括的な防御を実現できる点は、これからのセキュリティ運用に欠かせない大きな魅力です。
サイバー攻撃が高度化・複雑化するいま、重要なのは「点」ではなく「全体像」をいかに早く把握し、適切に対応できるか。
その答えの一つがCybereasonにあると考えています。
もしご興味を持っていただけた方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。みなさまのセキュリティ強化に少しでもお役立ていただければ幸いです。
■注目のCybereason CNAPPについても是非どうぞ
著者紹介

SB C&S株式会社
ICT事業本部 技術本部 ソリューション技術統括部 ソリューション技術部 1課
橋本 紗代子
関西の湖畔で動物たちと暮らしています。








